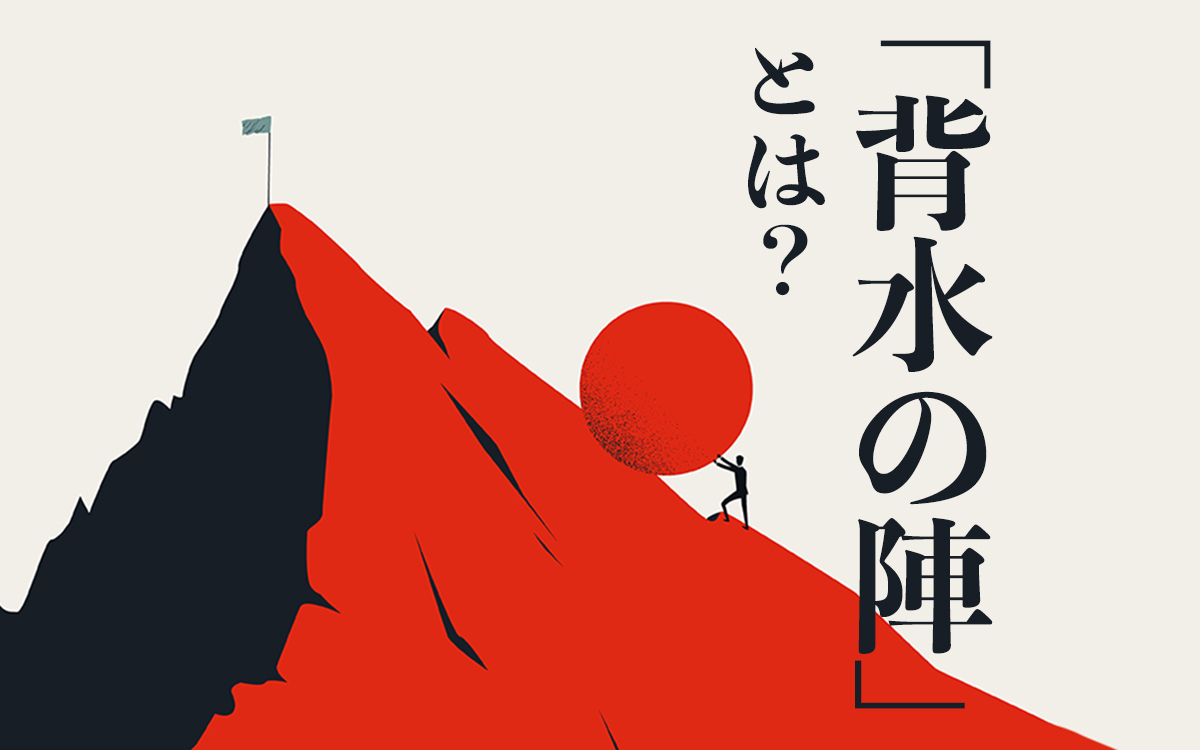目次Contents
「面壁九年」の意味と由来
「面壁九年」は、中国の故事に由来する言葉とされています。
そもそも「故事」とは、過去から現代へと伝わる由緒ある事柄のことです。「面壁九年」は、「碧巌録(へきがんろく)」という故事に登場します。「碧巌録」のなかで達磨(だるま)大師は、座禅を組み、9年をかけて悟りを開いたとされます。
転じて「面壁九年」は、努力することの大切さを説く言葉として用いられるようになりました。
めんぺき‐くねん【面壁九年】
出典:小学館 デジタル大辞泉
菩提達磨(ぼだいだるま)が、中国の少林寺で無言のまま9年間も壁に面して座禅し、悟りを開いたという故事
▼あわせて読みたい
「面壁九年」の由来となった達磨大師とは?
達磨大師は、インドから中国へ「禅」を広めたといわれる人物です。達磨大師のほか、達磨禅師などと呼ばれます。
そもそも「禅」とは仏教用語のひとつで、心が静かに落ち着いた状態を意味する「禅定(禅那)」を略したものです。近年は、心を落ち着かせる「坐禅(ざぜん)」や「マインドフルネス瞑想」などがビジネスシーンでも注目されている傾向がみられます。その「禅」を広めたとされる達磨大師は、「だるま」の起源とも。
ここでは、「面壁九年」の由来となった達磨大師についてみていきましょう。

達磨大師は「だるま」の起源
赤く丸い形をした「だるま」は、達磨大師の座禅の姿を模したものです。紅衣をまとって座禅する姿を表しています。
「だるま」は日本の伝統的な縁起物として古くから親しまれてきました。これは、倒れても起き上がる姿が「七転び八起き」の精神を表しているためという見方もあります。
達磨大師が長年かけて悟りを開いたことにあやかり、大願成就の願いを込め、目を入れる風習があります。これは、江戸時代に始まったとされる風習です。一般的には、願いを込めながら片目を入れ、願いが叶ったときに感謝を込めてもう一方の目を書き入れます。
近年はカラフルな「だるま」も人気です。また、地域性のある「だるま」も生産されています。
▼あわせて読みたい
「面壁九年」の使い方
「面壁九年」は、ビジネスシーンで活用できる四字熟語です。粘り強い努力が求められる場面や、その大切さを伝えたいときは以下のように使用してみましょう。
・新薬開発までには長い道のりが予想されるが、面壁九年の精神でのぞみたい
・思うようにいかないからといって、すぐに諦めてしまうのはもったいないよ。何事も面壁九年といわれるように、粘り強さが大切だよ
・面壁九年の努力が実り、ついに念願だったレストランの開店にこぎつけた
・資格試験に合格したと聞いたよ。面壁九年、本当によくがんばったね
▼あわせて読みたい
「面壁九年」と意味の似ている故事成語・四字熟語
「面壁九年」と似たような意味を持つ言葉としては、以下のようなものが挙げられます。
・十年一剣(じゅうねんいっけん)を磨く
・背水之陣(はいすいのじん)
適切に使い分けられるよう、それぞれの意味を確認していきましょう。
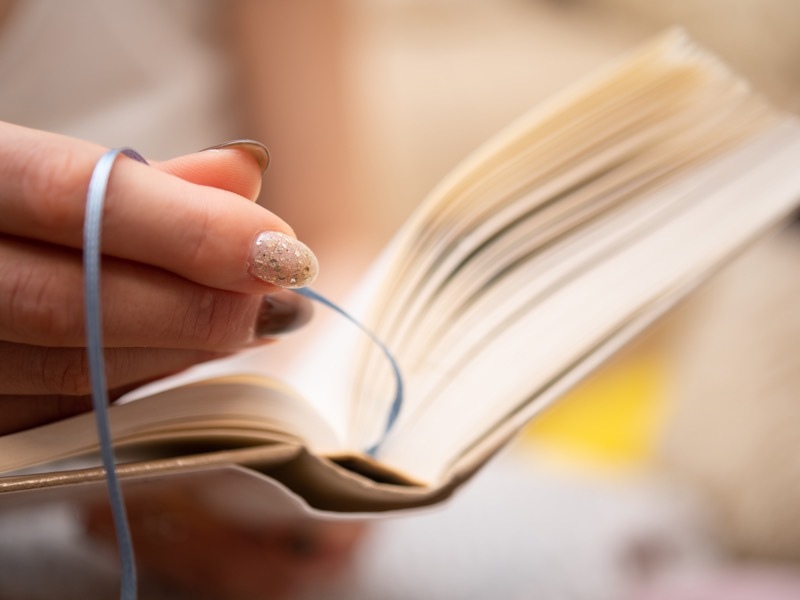
「十年一剣(じゅうねんいっけん)を磨く」
「十年一剣」とは、長い間努力をし、その成果を発揮する機会を待つことです。「一剣」には、ひとふりの剣を磨き続けるという意味があります。
「面壁九年」と共通しているのは、粘り強く努力するという意味が含まれる点です。以下のように、目標達成に向かい、努力する姿を表す際に使用します。
・十年一剣、今日の試験のために就業後も勉強を続けてきた。今回こそは納得いく結果を出したい
「背水之陣(はいすいのじん)」
「背水之陣」とは、必死になって物事にのぞむことです。言葉の由来は、中国の故事にあります。川や海を背にし、後に引けない状況になった陣が決死の覚悟で前進したところ、勝利をおさめたというのが言葉のはじまりです。
「面壁九年」が長年の粘り強い努力を指すのに対し、「背水之陣」は覚悟をもって物事にのぞむ姿を表しています。
・今回のコンペに落ちたら後がないんだ。これはもう、背水之陣でのぞむしかない
▼あわせて読みたい
「面壁九年」の意味や由来への理解を深めよう
「面壁九年」は、物事に粘り強く取り組むことの大切さを説いた四字熟語です。由来である達磨大師は、縁起物として親しまれる「だるま」の起源でもあります。
何かを成し遂げるためには、諦めずに継続する気持ちと行動力が必要です。「面壁九年」の意味や由来への理解を深め、ビジネスシーンに活かしていきましょう。
メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock