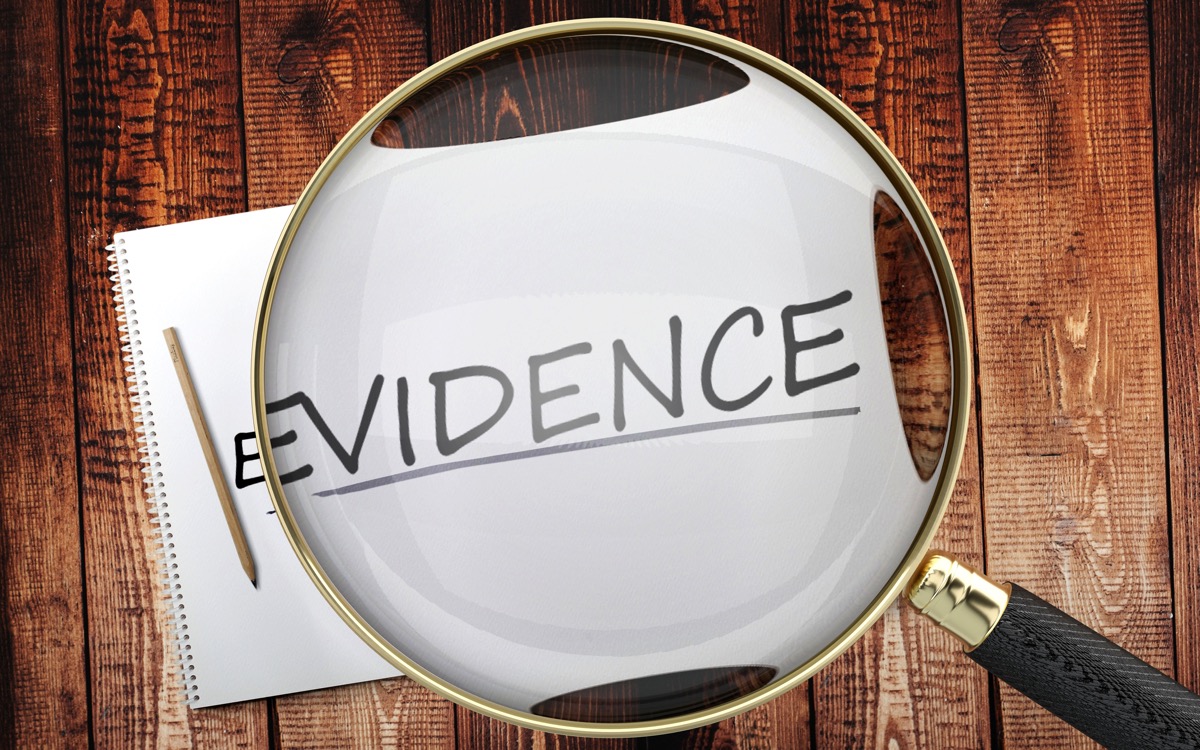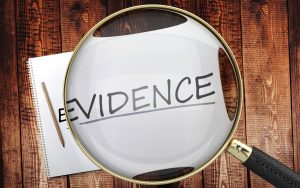目次Contents
「門前の小僧、習わぬ経を読む」の意味
「門前の小僧、習わぬ経を読む(もんぜんのこぞう ならわぬきょうをよむ)」は、寺の門前に住む子どもが毎日お経を聞くうちに、自然と内容を覚えてしまう様子を表しています。転じて、人は環境により良くも悪くも変化することを意味することわざです。
環境から影響を受けるのは、小さな子どもだけではありません。ビジネスでは、企業の考え方が従業員の働き方に影響を及ぼす可能性も。
周囲の環境によりモチベーションが上がることもあれば、下がることもあるなど「門前の小僧、習わぬ経を読む」は、現代の日常生活に関係することわざといえるでしょう。
門前の小僧、習わぬ経を読む
出典:小学館 デジタル大辞泉
ふだん見聞きしていると、いつのまにかそれを学び知ってしまう。環境が人に与える影響の大きいことのたとえ。
「門前の小僧、習わぬ経を読む」は「いろはかるた」の読み札
「いろはかるた」は、江戸時代後期に登場したとされる娯楽のひとつです。「いろはにほへと」から始まる47字に「京」の1字を加え、計48字の絵札と、同じく48枚の読み札を使います。
「も」を頭文字にする「門前の小僧、習わぬ経を読む」も、そのひとつ。かるたによっては「餅は餅屋」、「桃栗三年柿八年」などの読み札も存在します。

「門前の小僧、習わぬ経を読む」の使い方と例文
周囲の環境が人に影響を与える、という意味をもつ「門前の小僧、習わぬ経を読む」は、日常生活で以下のように活用できます。
- BGM代わりに韓流ドラマを流していたら、いつの間にか簡単な単語は聞き取れるようになっていた。まさに門前の小僧、習わぬ経を読むといったところだ
- パソコンの扱いは不慣れだったが、門前の小僧、習わぬ経を読むといったところで、毎日データ処理をするうちにタイピングの速度が上がった
- 門前の小僧、習わぬ経を読むなのか、先輩の真摯な仕事ぶりに日々接するなかで、仕事への意識が前向きなものへと変化した
「門前の小僧、習わぬ経を読む」と似た意味の類語・言い換え表現
「門前の小僧、習わぬ経を読む」の類語は、「勧学院の雀は蒙求を囀る(かんがくいんのすずめは もうぎゅうをさえずる)」です。
「勧学院」とは、平安時代に藤原氏の子弟教育のためにつくられた学校のこと。「蒙求」は、歴史上の教訓を記した啓蒙書を指します。
「勧学院の雀は蒙求を囀る」は、学生たちが朗読する蒙求を聞く雀が、声をあわせてさえずる様子を表す言葉です。転じて、身近で見聞きすることは自然に覚えられることを意味しています。
- 「武芸に長けているだけでなくピアノもお上手なのですね」
「ありがとうございます。母がピアノ教室の講師だったので、子どもの頃から音楽は身近な存在でした」
「勧学院の雀は蒙求を囀る、環境が与える影響は大きいですね」

「門前の小僧、習わぬ経を読む」の対義語
「門前の小僧、習わぬ経を読む」と反対の意味をもつ対義語は、「習わぬ経は読めぬ(ならわぬきょうはよめぬ)」です。習っていないお経は読めないように、知識や経験がないことは、求められても実行できないことを表します。
また「習わぬ経は読めぬ」は、学びの大切さも表しています。何事も、基礎が身についていなければ難しい分野にチャレンジできません。
趣味でも仕事でも、物事を成功させるためには学びの姿勢が重要です。「門前の小僧、習わぬ経を読む」が環境の重要性を説く言葉であるのに対し、「習わぬ経は読めぬ」は自らの姿勢を省みる大切さを表しているといえるでしょう。
「門前の小僧、習わぬ経を読む」以外の「いろはかるた」の読み札
ここからは「門前の小僧、習わぬ経を読む」以外の「いろはかるた」の読み札をチェックしていきましょう。
古くから親しまれてきた「いろはかるた」には、日常生活の規範となることわざが使われています。知っているようで知らない正しい意味を、例文を参考に確認してみてください。

「犬も歩けば棒に当たる」
「犬も歩けば棒に当たる(いぬもあるけばぼうにあたる)」は、2つの意味をもちます。
1つは「何か行動すると、災難に遭うことが多い」という意味です。これは、犬が棒に当たる様子をネガティブな意味合いで捉えています。
もうひとつは、「出歩けば思わぬ幸運に出会える」というポジティブな意味です。行動を起こすことで思いがけないチャンスに出会える可能性を指しています。
- ミスを挽回しようとしたのだが、かえって新たな混乱を招いてしまった。犬も歩けば棒に当たるといったところだ……
- 自分から動き出さなければチャンスもやってこないよ。犬も歩けば棒に当たるというでしょう
▼あわせて読みたい
「論より証拠」
「論より証拠(ろんよりしょうこ)」は、あれこれ言葉を並べるより、証拠を示すほうが物事は明らかになるという意味の言葉です。「抽象的な議論はかえってまわりくどい」というニュアンスで用いられることもあります。
- 彼の実績に不安があることはわかります。ただ、論より証拠。作品を手に取ってもらえば、その実力がおわかりいただけるはずです
▼あわせて読みたい
「花より団子」
「花より団子(はなよりだんご)」は、季節を楽しむ花見より、団子を食べるほうが大事な様子を表します。転じて、風流なことより利益を優先する態度を意味することわざです。
また、外観の良さではなく、物事の本質を尊ぶ様子も指します。「食いしん坊」というニュアンスをもつ言葉だと思われがちですが、本来の意味を正しく理解しておきましょう。
- 「取引先を招いて夜桜を楽しむ会が催されてね。2時間があっという間だったよ」
「桜はどうだった?」
「それが名刺交換と会食に忙しく、あまり印象になくて……」
「まさに花より団子といったところだね」
▼あわせて読みたい
「門前の小僧、習わぬ経を読む」の意味を知り日常生活に役立てよう
「門前の小僧、習わぬ経を読む」は、環境が人に与える影響の大きさを説く言葉です。「いろはかるた」の読み札のひとつとして、現代に受け継がれています。
また、対義語である「習わぬ経は読めぬ」は、物事における学びの重要性を意味します。いろはかるたの読み札や類語など、さまざまな語句の正しい意味を知り、日常生活でぜひ活用してください。
メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock