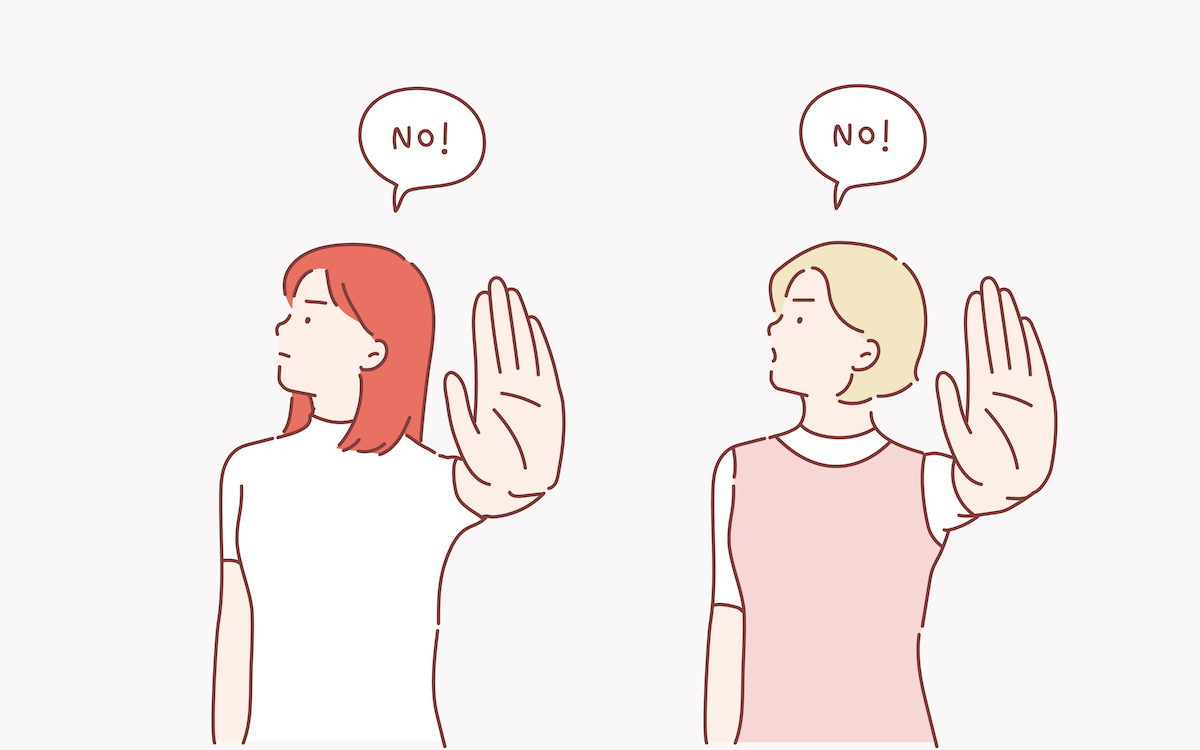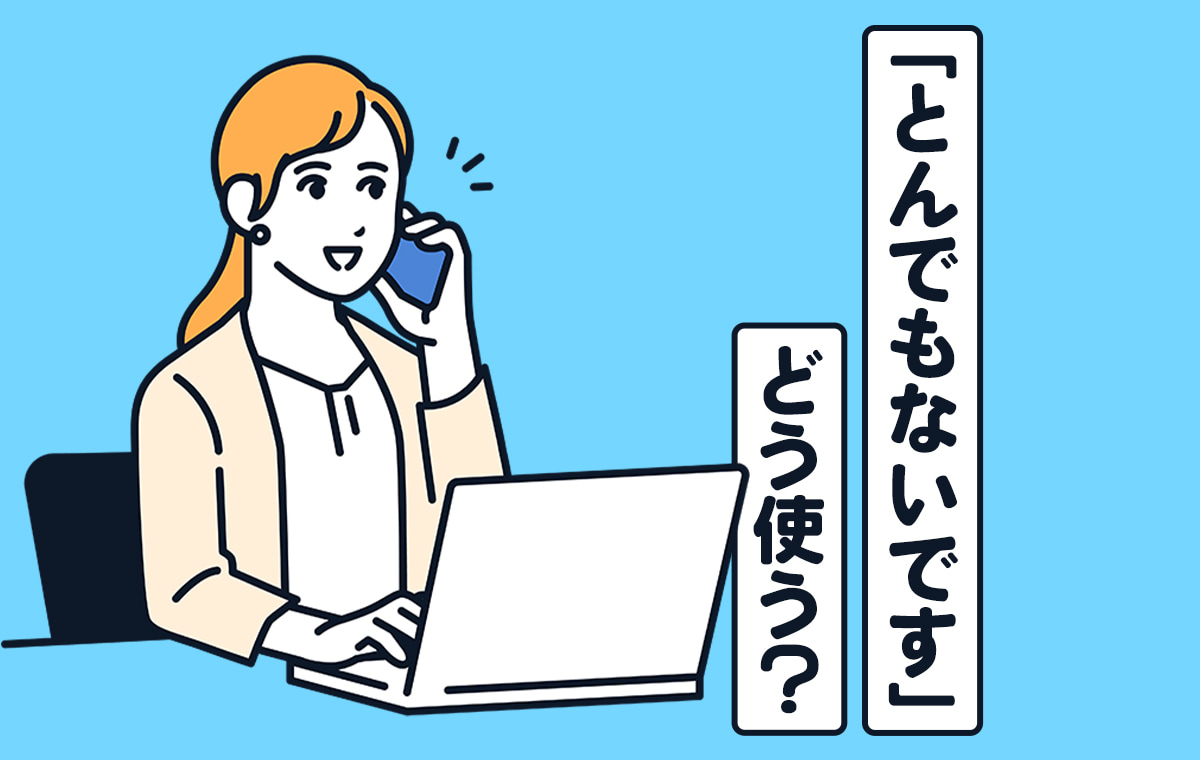言語道断(ごんごどうだん)の意味とは?
言語道断(ごんごどうだん)とは、言葉で言い表せないほどひどいことや、とんでもないことを指す言葉です。他人の行動を責めるときや、常識から照らし合わせてかけ離れてひどいことを表現するときに使われます。
・他人のものを盗むなんて、言語道断だ
・君の行動は言語道断だ。そのような無神経な振る舞いをするなんて、まったくどうかしている
・それが言語道断な行いであることは、あなたもよくわかっているでしょう?
言い訳のしようがないほどに間違っているときなどに使われることから、強い否定のニュアンスがあるといえます。相手に強いインパクトを与えることもあるため、適切なシチュエーションか考えて使うようにしましょう。
もともとは奥深い心理を指す仏教用語だった
言語道断は、仏教由来の言葉です。もともとは「奥深い真理は言葉で表現できない」といった意味で使われていたため、ネガティブな意味合いはなく、仏の教えを称えるポジティブなニュアンスがあるといえるでしょう。
仏教では、物事を理解する際に言葉による認識を離れることが悟りへの道と考えられています。言葉による認識から離れ(言語を「断つ」)、言葉だけでは表現できない境地へ進むことで真理に近づいていく意味から「言語道断」という言葉が生まれたようです。
ポジティブな意味もある
現在ではネガティブな意味で使われる「言語道断」ですが、言葉で言い表せないほど立派なことや様子を意味する言葉でもあります。
たとえば、鎌倉時代に成立したといわれる平家物語では「時々刻々の法施祈念、言語道断の事どもなり」と、信心深さを褒める意味合いで言語道断が用いられています。
ごんご‐どうだん〔‐ダウダン〕【言語道断】
出典:小学館 デジタル大辞泉
[名・形動]
1 仏語。奥深い真理は言葉で表現できないこと。
2 言葉で言い表せないほどひどいこと。とんでもないこと。また、そのさま。もってのほか。「人のものを盗むとは言語道断だ」「言語道断な(の)行い」
3 言葉で言いようもないほど、りっぱなこと。また、そのさま。
「時々刻々の法施祈念、―の事どもなり」〈平家・一〉
4 表現しがたいほど驚嘆した気持ちを表す語。感動詞的に用いられる。
「―、ご兄弟のご心中を感じ申して」〈謡・春栄〉
言語道断の言い換えに使える言葉を例文でチェック
もともとはポジティブな意味の「言語道断」ですが、現在ではほとんどの場面でネガティブな意味や相手を責めるときに使われ傾向がみられます。言語道断と似た意味合いを持つ言葉としては、次のものが挙げられます。
・論外
・的外れ
・もってのほか
・とんでもない
・甚だしい
・極端
各言葉の使い方やニュアンスの違いを、例文を通して見ていきましょう。

論外
論外(ろんがい)とは、「当面の議論に関係のないこと」や「論じる価値もないこと」の意味で使われる言葉です。言語道断と同じく相手を非難するときに使われることがあります。
・君の事情はここでは論外に置いておこう
・貸したお金を返さないなんて、論外な奴だ
・まったくもって論外な発言だ。聞いて呆れるよ
言語道断と比べると、非難するというよりは呆れているといったニュアンスがあります。相手の発言が的外れなときなどに使えるでしょう。
的外れ
的外れ(まとはずれ)とは、矢が的をはずれる意味合いから、「大事な点を外していること」や「見当違いなこと」、もしくはそのような様子について使われる言葉です。
・彼に尋ねても的外れな返答が返ってきた
・君は私を責めるが、その非難は的外れだ
・彼女の努力の方向性は的外れといえるだろう
相手が要点を理解していないときや、理解している内容に齟齬がありそうなときに使われます。状況によっては相手を責めるニュアンスにもなる極端な表現のため、使うときには注意が必要です。
▼あわせて読みたい
もってのほか
もってのほかとは、「とんでもないこと」や「けしからぬこと」、もしくはそのような様子について使われる言葉です。漢字では「以ての外」と表記します。
・先生に家まで足を運んでもらうなんてもってのほかです。私がご自宅にお迎えに上がります
・いくらカジュアルフライデーだからといって、タンクトップにショートパンツはもってのほかだろう
・途中退席はもってのほかです。最後までしっかりと話を聞いてください
もってのほかも相手を責めたり、相手の行動や選択を全否定するニュアンスがあります。極端な表現になりかねないため、状況に応じて他の言葉で言い換えるようにしましょう。

とんでもない
とんでもないとは、「思いもかけない」「意外である」「もってのほかである」という意味の言葉です。
・会社からの帰り道、とんでもない人にであった
・これはすごいよ。とんでもない発明だ
・猫はかわいい顔をしているが、時折とんでもない悪さをする
相手の言葉を強く否定するときにも使われます。
・(褒められたときに)そんな、とんでもないです
・(責められたときに)とんでもないです。私は無関係です
「とんでもない」は一語のため「ない」を「ありません」や「ございません」と置き換えるのは不適切とされています。しかし、近年では「とんでもありません」や「とんでもございません」との表現も一般化してきている傾向が見られます。
▼あわせて読みたい
甚だしい
甚だしい(はなはだしい)とは、「普通の度合いをはるかに超えている」という意味です。甚だしい自体はニュートラルな表現で、特に責める意味合いや褒めるニュアンスはありません。
・場違いも甚だしい
・今度の台風は、日本各地に甚だしい被害をもたらした
・非常識も甚だしい。君はまともに話せないのか?
甚だしいという表現自体はニュートラルな表現といえますが、極端な意味合いを持つため、相手に不快な印象を与えることもあるかもしれません。状況に応じたニュアンスの言葉を使うのがよいでしょう。
▼あわせて読みたい
極端
極端(きょくたん)とは、「普通の程度から大きく外れていること」「一方に偏っていること」を意味します。
・君の発言はいつも極端だ
・気に入らないから関係を切るって、どうしてそんなに極端なの?
・極端に言えば、彼は異常者だ
甚だしいと同様、言葉に強いニュアンスがあるため、使う場所やシチュエーションに注意が必要です。
▼あわせて読みたい
言語道断は使うシチュエーションを選ぶ言葉
言語道断はもともとはポジティブな言葉ですが、現在はそうとは言い切れません。非難する意味に受け取られることもあるため、使うシチュエーションを選ぶ必要があります。
相手を責めるとき以外は「的外れ」や「とんでもない」程度の言葉を選ぶほうがよいケースも。常に相手の気持ちに立ち、言葉を選びましょう。
メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock