重厚長大とは?
重厚長大は「じゅうこうちょうだい」と読み、重化学工業やその特質を表します。戦後から高度経済成長期にかけて誕生した言葉です。
ここでは、重厚長大の意味や言葉が生まれた背景、対義語についてみていきます。
重化学工業を指す言葉
重厚長大とは、おもに重化学工業を中心とした産業全般を指します。この表現は単に産業の種類を区分するだけでなく、その産業が持つ特質や性格を表現する際にも用いられる言葉です。
言葉の由来は、そこで扱われる製品や設備が「重く、厚く、長く、大きい」といった特徴を備えていることにあります。
実際に該当する分野としては、鉄鋼業やセメント産業、非鉄金属の製造、さらに大規模な造船業や各種の化学工業などが挙げられます。
これらはいずれも膨大な資本や大型の設備を必要とし、規模の大きな生産活動を伴う点で共通しており、重厚長大産業と総称されてきました。
じゅう‐こう‐ちょう‐だい〔ヂユウ‐チヤウ‐〕【重厚長大】
引用:小学館 デジタル大辞泉
鉄鋼・造船・セメント・石油化学などの重化学工業やその特質を言い表す言葉。重く・厚く・長く・大きい製品を扱うことから。「重厚長大産業」→軽薄短小。
言葉が生まれた背景
重厚長大という言葉が生まれた背景には、戦後復興と重化学工業の発展があるようです。第二次世界大戦後、日本は復興を進める中で基盤産業を強化しました。
鉄鋼、造船、セメント、化学などの重化学工業は、社会インフラの整備や大規模な生産活動を支えるために不可欠であり、重点産業と位置づけられていたのです。
1950年代後半から1970年代前半にかけての高度経済成長期には、これらの産業が日本経済を牽引しました。大量の設備投資を行い、重く・大きく・長大な製品を生み出す産業が「重厚長大」という特徴的な言葉で総称されるようになったのです。
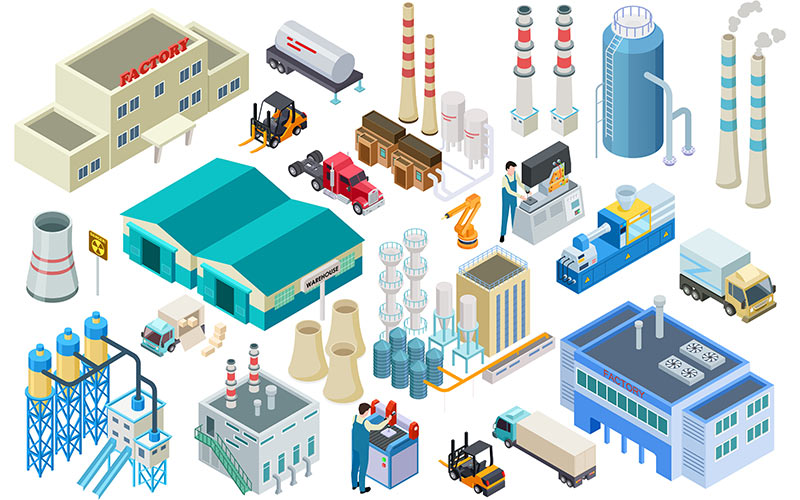
対義語は「軽薄短小」
重厚長大の対義語は「軽薄短小(けいはくたんしょう)」で、重厚長大と同じ背景で生まれた言葉です。
1980年代ごろ、エレクトロニクスや精密機器、半導体といった「小型で軽く、高機能で付加価値の高い製品」を生み出す産業が台頭しました。これらの産業は、それまでの鉄鋼・造船などの伝統的産業である「重厚長大」と対比的に表現するために「軽薄短小」と呼ばれるようになったのです。
時代を経るにつれ、重厚長大は単なる産業区分ではなく、古い体質・時代遅れといった批判的ニュアンスで使われるケースも見られます。
けい‐はく‐たん‐しょう〔‐セウ〕【軽薄短小】
引用:小学館 デジタル大辞泉
機械製品・電気製品などが、軽量化・薄型化・小型化したことを表す語。文化的な面にもいう。→重厚長大。
重厚長大の使い方・例文
重厚長大の使い方について、例文をみながら確認していきましょう。
・戦後の日本経済は、重厚長大な鉄鋼・造船産業の発展によって急速に復興した
・この地域は、重厚長大なプラントや工場が立ち並ぶことで知られている
・近年は重厚長大な産業の縮小が課題となり、新たな成長分野への転換が求められている
・鉄鋼業や化学工業のような重厚長大な事業は、大量の資本と高度な技術力を必要とする
・重厚長大な設備を維持するためには、熟練の技術者と綿密な管理体制が欠かせない
重厚長大産業の特徴
重厚長大産業は多額の資本投資と多くの労働力が必要であり、生産サイクルが長いという特徴があるといえます。
ここでは、重厚長大産業の特徴を簡単にみていきましょう。
多額の資本投資と大規模な労働力が必要
重厚長大産業は、鉄鋼や造船、化学などの重化学工業を中心とするため、多額の資本投資と大規模な労働力を必要とします。
大型の設備やプラントの建設には膨大な資金がかかり、運用や維持にも専門技術者や熟練労働者が欠かせません。そのため、初期投資や人材確保の負担が大きい一方で、安定した生産体制と高い技術力が国の経済成長を支える重要な要素となっているといえるでしょう。
生産サイクルが長い
重厚長大産業では、大規模な設備や複雑な製造工程を必要とするため、生産サイクルが長いことが特徴です。鉄鋼や造船、化学工業などでは、1つの製品が完成するまでに数か月から数年単位の時間がかかることも珍しくありません。
長期にわたる計画と綿密な工程管理が求められるため、生産効率の向上や需要予測の正確性が事業の成否に大きく影響するといえるでしょう。
現代社会での重厚長大の評価と課題
かつて国の経済成長を支えた重厚長大産業は、現代社会でも高い技術力や安定した生産能力という点で評価されている傾向にあります。一方で、現代の市場や社会の変化に対応する上で課題も少なくありません。
ここでは、現代社会における重厚長大産業の評価と課題をみていきます。

現代の経済環境とのギャップ
重厚長大産業は、高度な技術力や大量生産能力を持つ一方で、現代の経済環境とはギャップが生じやすいのが特徴といえるかもしれません。
短期間での収益改善や柔軟な事業展開が求められる傾向にある現代では、多額の設備投資や長期の生産サイクルが足かせになることも。
これらの産業が持続的に競争力を維持するには、効率化や新技術の導入などが求められるでしょう。
環境問題や労働人口の減少
重厚長大産業は大量の資源やエネルギーを消費するため、環境負荷が大きく、地球温暖化や廃棄物問題への対応が重要課題となっています。
また、少子高齢化による労働人口の減少は大規模な生産や長期的なプロジェクト運営に影響を与え、熟練技術者の確保や技術継承も難しくなっているのが実情のようです。これらの課題に対応するため、省エネ技術や自動化の導入が求められています。
重厚長大の意味や今後の課題を理解しよう
重厚長大とは、重化学工業を中心とした産業や、それらの特質を表す言葉です。重く・厚く・長く・大きな製品を扱うことに由来し、具体的には鉄鋼業、セメント、非鉄金属、造船、化学工業などが該当します。
これらの産業は多額の資本投資や大規模な労働力を必要とし、生産サイクルも長いため、短期的な利益よりも長期的な安定性や規模の経済が重視されるといえます。
しかし現代では、環境規制の強化や労働人口の減少、グローバル競争の激化などにより、従来の重厚長大産業のビジネスモデルには課題も少なくありません。そのため、環境保護対策や効率化、技術革新などが求められています。
メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock























