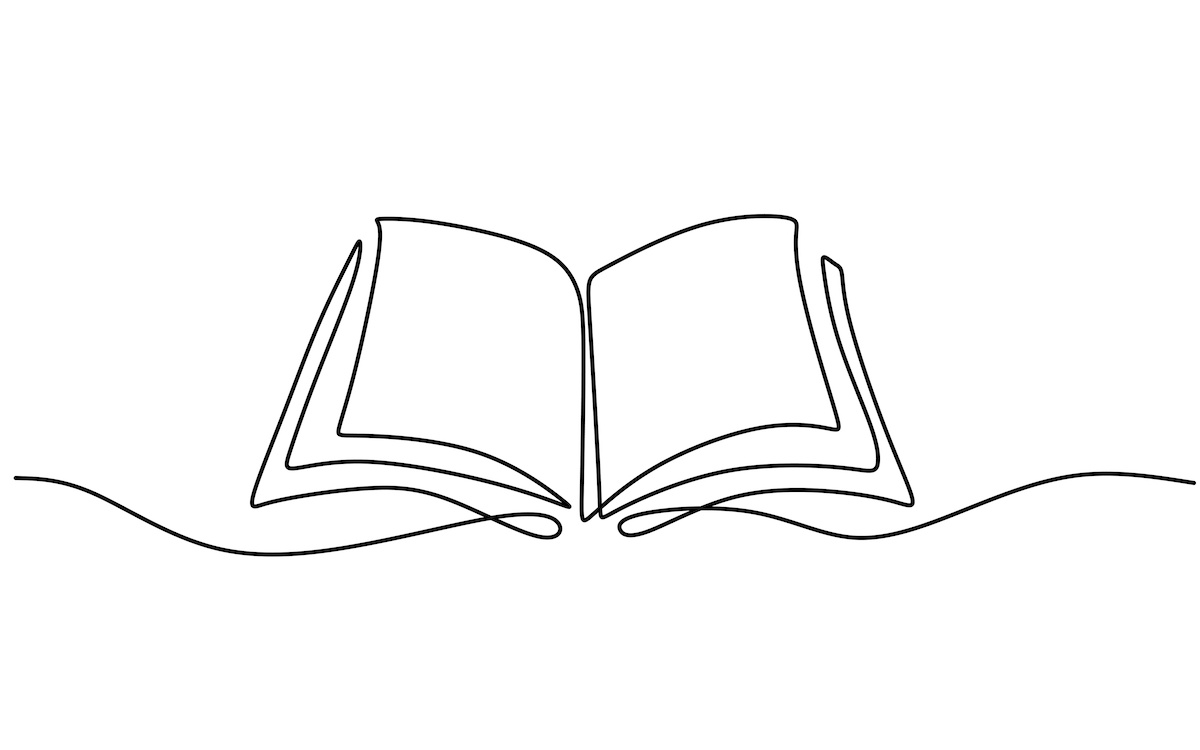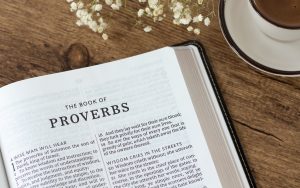悪人正機説とは? 意味を簡単にチェック
「悪人正機説(あくにんしょうきせつ)」とは、阿弥陀仏(あみだぶつ)の本願は悪人を救うことであるという考え方のことです。
あくにんしょうき‐せつ【悪人正機説】
阿弥陀仏(あみだぶつ)の本願は悪人を救うためのものであり、悪人こそが、救済の対象だという考え方。親鸞(しんらん)の念仏思想の神髄とされる。
引用:小学館 デジタル大辞泉
阿弥陀仏とは西方浄土の教主で、すべての衆生を救おうと48の誓いを立てた仏です。浄土宗や浄土真宗では阿弥陀仏を本尊とし、念仏による極楽往生を説きました。阿弥陀仏は、阿弥陀如来(あみだにょらい)や阿弥陀、弥陀とも呼ばれます。
浄土真宗や浄土宗のお題目は、南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ、なもあみだぶつ)です。南無阿弥陀仏にはさまざまな解釈がありますが、一説には「はかりしれない光と命を持つ阿弥陀仏を尊ぶ」や、「阿弥陀仏におまかせして人生を歩む」といった意味があるといわれています。南無阿弥陀仏と唱えるなら、悪人であっても善人と同様、極楽往生が叶うと考えられています。
そもそも「正機」とは?
「正機(しょうき)」とは、仏の教えや救いを受ける資質を持つ人々を指す仏教用語です。つまり悪人正機とは、悪人であるということが、仏の救いを受ける資格を持つという意味になると考えることができます。
本来ならば善人こそが仏の救済を受けると印象を抱きそうなものですが、親鸞聖人は悪人が正機だと説きました。逆説的な言い方が強いインパクトを持ち、数百年のときを越えて現代に伝わっています。
しょう‐き【正機】
仏語。仏の教えや救いを受ける資質をもつ人々。「悪人—」
引用:小学館 デジタル大辞泉
悪人正機説は親鸞聖人の師・法然上人の言葉?
『歎異抄』は親鸞聖人の言葉が集められた書物として知られているため、悪人正機説も親鸞聖人の言葉だといわれることがあります。しかし、『歎異抄』の悪人正機説の箇所は親鸞の師である法然の書から引用しているため、親鸞聖人の師である法然上人の言葉と解釈するほうが自然といえるかもしれません。
なお、法然上人は親鸞聖人と同じく最初は比叡山で学んでいましたが、その後、野に下りて衆生に説くようになりました。悪人こそが救われるという急進的な考え方は伝統的な仏教勢力から攻撃を受け、法然は讃岐に、親鸞は越後に流罪に処されたといわれています。
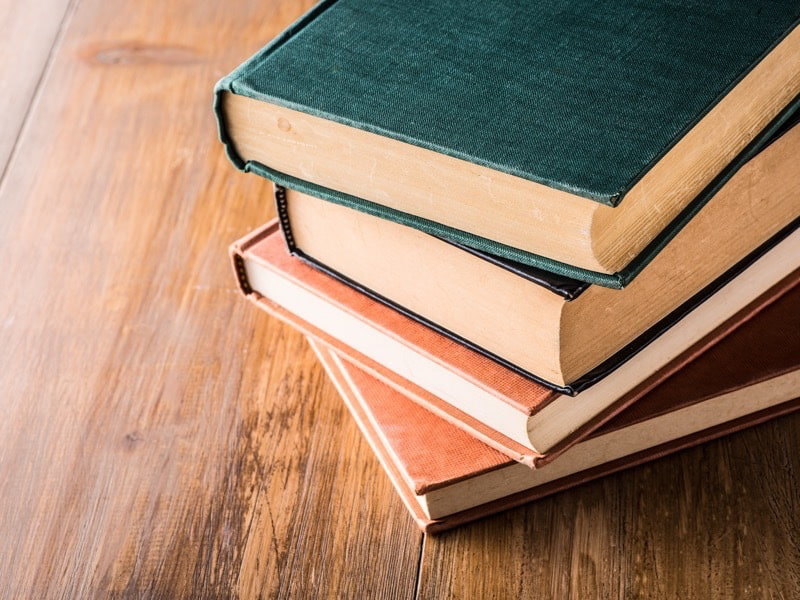
悪人正機説の原文
親鸞聖人が鎌倉時代に開いた浄土真宗の聖典『歎異抄』には、次のように記されています。
| 善人なをもて往生をとぐ いはんや悪人をや (意訳:善人でさえ往生できるのだから、まして悪人ならなおのこと往生できます) |
また、続く言葉も意訳で紹介します。
| しかしながら世の人々は、悪人が往生できるなら、善人も往生できるといいます。 その理屈はもっとものように聞こえますが、本願他力の趣旨とは合いません。 その理由は、自分で善行を積める人は阿弥陀仏に頼る心が欠けているため、阿弥陀仏が助けたいと願う対象とはならないからです。 しかし、自分でなんとかしようという気持ちを捨てて阿弥陀仏に頼るなら、本当に往生を実現できます。 |
往生(おうじょう)とは仏教用語で、極楽浄土に往って生まれ変わることを指します。善人が往生できるなら、阿弥陀仏の救済対象である悪人も往生できるはずです。
また、善人なら自分で善行を積めますが、悪人は善行を積めないため、阿弥陀仏に頼るしかありません。つまり悪人だからこそ極楽浄土に行けるのだと、親鸞聖人は語りました。
悪人正機説の「悪人」とは?
悪人正機説の「悪人」とは、「自分の力で迷いを捨てられない人」を指すとされています。自分では迷いを捨てられないからこそ、阿弥陀仏に頼り、阿弥陀仏に救ってもらう必要があると考えられたのでしょう。

悪人正機説とキリスト教
キリスト教の聖典である新約聖書には次のように書かれています。
| わたしが来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです |
ここの「わたし」とはイエス・キリストのこと。悪人正機説と同様、善人ではなく罪人を救済対象としていることがうかがえます。
善悪を超えた絶対的な救い
福音書の中では、「よい人だから救われる」「悪い人だから救われない」といった二元論的な考え方は記載されていないようです。人間の善悪を超え、絶対的な救済というものが存在することを述べていると考えられます。
悪人正機説でも同様といえるでしょう。「よい人だから」「悪い人だから」といった考え方に限定されず、すべての人に開かれた救済の道を説いていると推測されます。
「善人」はいない
新約聖書では「善を行う者はいない。ただの一人もいない」との記載もみられます。人はすべて罪人だという考え方を理解し、自分も罪人と認識したときに、キリストによる救済の対象となるのかもしれません。
さまざまな考え方に触れてみよう
世の中には多くの考え方があり、それぞれ類似する部分や異なる部分があります。ひとつの視点からだけでなく、角度を変えて見てみれば、考え方が変わることもあるのかもしれません。多くの考え方に触れ、幅広い視野を身につけていきたいですね。
メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock