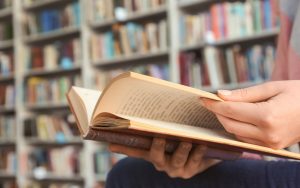「金襴緞子(きんらんどんす)」という言葉を聞くと、どこか華やかな響きを感じるのではないでしょうか? しかし、「金襴緞子」って具体的に何なの? と聞かれたら、意外と答えられる人は少ないかもしれません。
そこで、この記事では、「金襴緞子」の意味や特徴、そして有名な歌詞に込められた背景まで、紹介していきます。
「金襴緞子」とは?
まずは、「金襴緞子」の意味や特徴を整理していきましょう。

「金襴緞子」の読み方と意味
「金襴緞子」は、「きんらんどんす」と読みます。辞書で意味を確認しましょう。
きんらん‐どんす【金×襴×緞子】
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
金襴や緞子。また、高価な織物。「―の帯」
ここでいう「金襴」とは、綾織や繻子地(しゅすじ)に金糸を織り込んで文様を表した、きらびやかな織物のことです。一方の「緞子」は、室町時代末期に中国から伝わったとされる絹の織物で、繻子地に裏組織を使って文様を織り出すのが特徴とされています。
金襴も緞子も、ともに高価な織物です。ですから、「金襴緞子」という言葉は、これらの豪華な布地を並べて表現したもので、一般的にはきわめて高価で華やかな織物を指すときに使われます。
「金襴緞子」が出てくる楽曲とは?
「金襴緞子」という言葉は、童謡『花嫁人形(はなよめにんぎょう)』の歌詞の中に登場します。この楽曲は、蕗谷虹児(ふきや・こうじ)が作詞し、杉山長谷夫(すぎやま・はせお)が作曲した抒情的な作品として知られています。
『花嫁人形』には、「花嫁が金襴緞子の帯を締めているのに、どうして泣くのだろう」といった意味の歌詞が出てきて、豪華な装いをした花嫁が涙を流している情景が描かれています。
このフレーズには、華やかな見た目と裏腹に、花嫁の心にある寂しさや不安がにじんでいるようにも感じられます。外見の美しさと内面の揺れが重なることで、フレーズに独特の余韻が生まれていますよ。

「金襴」と「緞子」とは? 歴史や使用用途を知る
「金襴」と「緞子」。このふたつの織物は、見た目の美しさだけでなく、歴史や文化と深く結びついています。それぞれの特徴を知ると、和装や装飾の背景にある意味が見えてくるかもしれません。
「金襴」とは?
「金襴」は、金糸を使って文様を織り出した豪華な織物のことです。中国の宋代から伝わり、日本には鎌倉時代に禅僧が袈裟の裂として持ち帰ったとされます。室町時代には中国との貿易品として盛んに輸入され、茶道の仕覆や書画の表装などにも用いられ、「名物裂(めいぶつぎれ)」として大切にされてきました。
金襴に使われる金糸の多くは、平たく薄い箔を用いた平金糸で、撚りをかけた糸はあまり使われません。織り地には綾や繻子などがあり、織り込み方にもいくつかの技法があります。
日本での本格的な製織は、16世紀半ばの京都で始まったと考えられており、以降は西陣が金襴の一大産地となりました。小袖や帯、羽織裏、夜具地、袈裟地など、格式のある装飾や衣装に使われることが多く、現代でもその美しさは受け継がれています。
参考:『世界大百科事典』(平凡社)

緞子とは?
「緞子」は、繻子組織を基本とする絹の紋織物で、光沢に富み、文様がはっきりと浮かび上がるのが特徴です。「段子」、「鈍子」などの字でも書かれ、中国では元代にはすでに織られていたことが確認されています。
日本には中世に伝わり、一部は茶道具などを包む「名物裂」として受け継がれました。江戸時代には京都・西陣が主な産地となり、小袖、帯、羽織の裏地、夜具、袈裟など、さまざまな用途で使われてきました。
江戸時代末には、群馬県桐生でも緞子の織製が始まり、特に明治10年代から20年代にかけては緞子の最盛期とされます。しかしその後、他の紋織物の台頭により徐々に姿を消し、現在では表具や茶道具の仕覆、袱紗(ふくさ)など、限られた用途の中で使われています。
参考:『日本大百科全書』(小学館)
最後に
「金襴緞子」という言葉には、ただ華やかで高価な布という以上に、日本人が大切にしてきた感性や情緒がにじんでいるかのようです。見た目の美しさの奥にある物語に目を向けてみることで、ふだん何気なく聞く言葉が、少し深く心に残るものに変わるかもしれません。時代を越えて受け継がれてきたその響きに、耳を澄ませてみたくなりますね。
TOP画像/(c) Adobe Stock