「弁慶の立ち往生」という言葉を聞くと、どのようなイメージが浮かびますか? 「弁慶」という名前は、歴史の教科書などで見聞きする機会はあっても、意味や背景までは知らない人も多いかもしれません。
そこで、この記事では、「弁慶の立ち往生」の由来から具体的な使い方、『名探偵コナン』での登場回まで丁寧に紹介していきます。
「弁慶の立ち往生」とは? 意味と逸話を紹介
ここでは、「弁慶の立ち往生」の意味と成り立ちを見ていきます。
「弁慶の立ち往生」とはどんな意味?
「弁慶の立ち往生」は「べんけいのたちおうじょう」と読みます。辞書で意味を確認しましょう。
弁慶(べんけい)の立(た)ち往生(おうじょう)
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
《弁慶が大長刀(なぎなた)をつえにして立ったまま死んだというところから》進退きわまってどうにもならないことのたとえ。
「弁慶の立ち往生」は、進退きわまり、どうすることもできないことのたとえとして使われます。
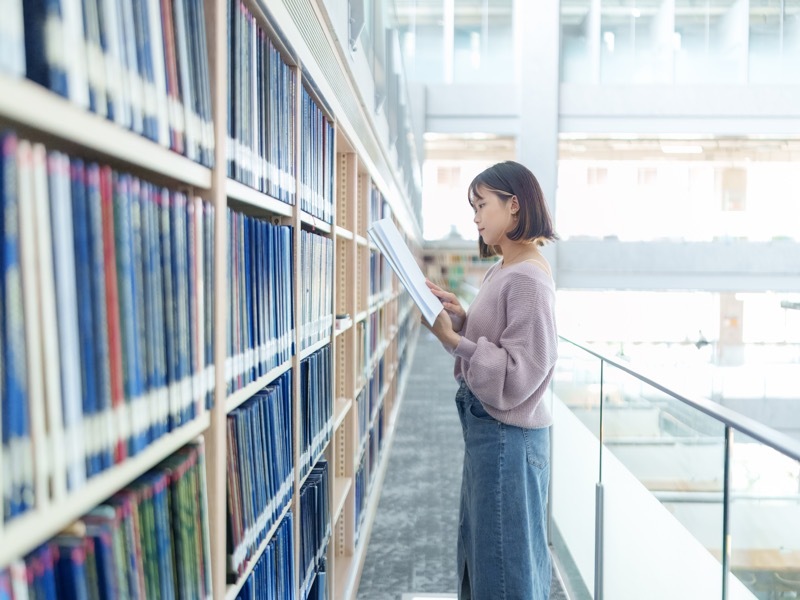
どんな逸話や伝説があるの?
弁慶は、伝説色の濃い豪勇の法師です。鎌倉時代初期、武蔵坊(むさしぼう)と称し、源義経の忠実な家臣として数々の戦いに挑みました。
なかでも有名なのが、衣川の合戦での最期の場面です。弁慶は義経を守るため、橋の中央に大なぎなたを突き立てて仁王立ちの姿勢をとり、全身に矢を浴びました。死しても倒れず立ったままの姿であったという伝説が「弁慶の立ち往生」として語り継がれています。
参考:『故事俗信ことわざ大辞典』(小学館)
「弁慶の立ち往生」、どう使う? 具体的な例文とともに紹介
歴史上の出来事としてだけでなく、「弁慶の立ち往生」という言葉は日常の中でどのように使ったらいいでしょうか? 例文を紹介していきます。
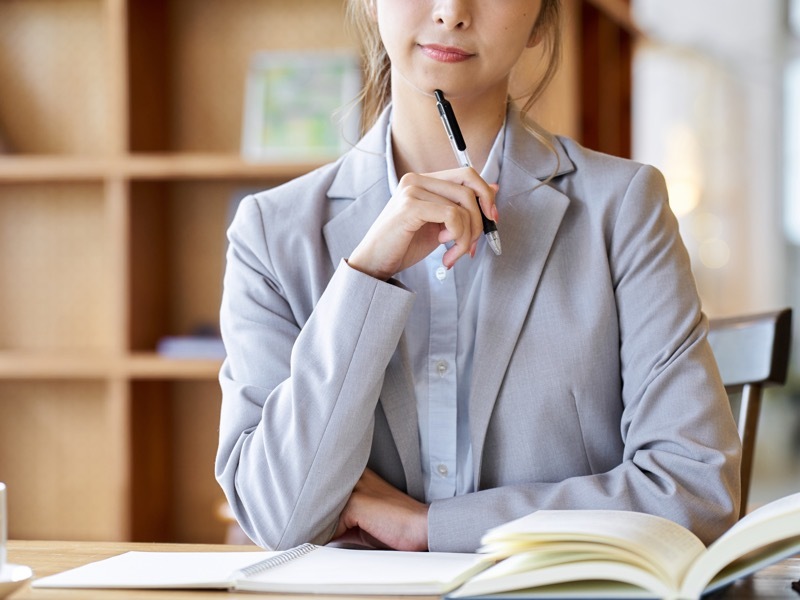
彼は上司にも取引先にも言い訳が通じず、まさに弁慶の立ち往生のような状況に追い込まれていた。
この例文では、「弁慶の立ち往生」という言葉で、身動きの取れない窮地に立たされた状態を表現しています。ビジネスシーンにおける追い詰められた状況を表すのにぴったりの用法です。
自分の意見を押し通した結果、誰からも賛同を得られず、弁慶の立ち往生のような状態に陥ってしまった…。
この例文では、誰からも賛同を得られない状況を「先にも進めず、後にも引けない」という「弁慶の立ち往生」の本義(進退きわまる)に沿った形で表現しています。
『名探偵コナン』にも「弁慶の立ち往生」が登場!
『名探偵コナン』では、歴史上の伝説などが物語に取り入れられることがあります。「弁慶の立ち往生」も象徴的なシーンの一つとして描かれました。以下で紹介していきましょう。

コナンに登場した「弁慶」モチーフ
『名探偵コナン』9巻に収録されている「小五郎の同窓会殺人事件」では、「弁慶の立ち往生」を象徴するシーンが登場します。物語の舞台は温泉旅館「弁慶」。小五郎の大学時代の柔道部の仲間が集まる同窓会の中で、同窓生・由美が命を落とす事件が起こります。
当初は自殺と思われた由美の死でしたが、小五郎やコナンは遺体の状態や証言の矛盾から他殺の可能性に気づきます。コナンは、旅館の廊下に飾られていた「弁慶が仁王立ちする像」に注目。多数の矢が刺さりながらも立ち尽くすその姿を見て、弁慶の立ち往生に着想を得たトリックが用いられた可能性に気づくのです。
気になる話の結末は、ぜひご自身の目でご確認ください。
最後に
「弁慶の立ち往生」は、強い信念や覚悟を象徴する言葉として今なお語り継がれています。日常の中ではあまり使われない表現かもしれませんが、由来を知ることで、言葉に込められた思いに気づかされることもありますね。
TOP画像/(c) Adobe Stock























