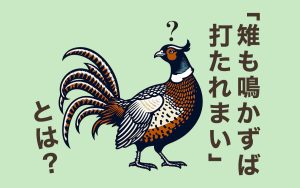「泥中の蓮」という言葉を、耳にしたことはありますか? 古くから使われる言葉ですが、実は私たちの生きる指針ともなり得る深い意味が込められています。この美しい言葉の意味や使い方を見ていきましょう。日々奮闘するあなたに寄り添うヒントをお届けします。
「泥中の蓮」とは? 読み方と意味、語源を確認
「泥中の蓮」とは、内なる清らかさを失わずに生きる姿勢を表す言葉です。詳しい意味を見ていきましょう。

読み方と意味
「泥中の蓮」は、「でいちゅうのはちす(もしくは、でいちゅうのはす)」と読みます。意味を辞書で確認してみましょう。
でいちゅう‐の‐はちす(または、はす)
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
汚れた環境の中でもそれに影響されずに、清らかさを保っていることのたとえ。
「泥中の蓮」は、泥の中に咲く蓮の花を指す言葉で、「逆境にあっても心清く、美しく生きる人」のたとえとして使われます。 どんなに周囲の状況が厳しくても誠実さを失わず、品位を保つ態度を、蓮の花になぞらえていますよ。
語源は仏教用語
「泥中の蓮」の語源は、仏教の経典『維摩経(ゆいまきょう)-中』にあります。
蓮が泥の中で清らかな花を開くところから、煩悩や俗世の汚れの中にあっても、清浄を保っているもののたとえとして使われるようになったのです。
参考:『日本国語大辞典』(小学館)
蓮の花と泥の関係
蓮の花にとって、泥は成長に必要不可欠な栄養源です。泥の中で根を張りながら成長する植物ですから、基本的にはきれいな清流やおしゃれなプランターの中では育ちません。 この「汚れ」と「美しさ」の対比が、人間の成長や生き方とも重なり、仏教用語を超えて多くの人の心を打つ言葉となりました。

「泥中の蓮」の使い方と具体的な例文を紹介
現代でも「泥中の蓮」は、清くたくましく生きる人を称える場面で使われます。仕事や環境に悩み、人生の波に揉まれながらも、自分らしく咲くすべての人に贈りたい言葉です。
「彼女はどんな環境にいても心を濁さず、まるで泥中の蓮のようだ」
周囲がトラブルや不穏な空気に満ちていても、自分を見失わずに静かに努力を重ねる人をたとえた表現です。 心の中に鬱憤を抱えていても笑顔で乗り越えていく姿は、まさに理想的な人柄といえるでしょう。
そんな逆境に負けない強さを持つ人は、過去の困難を乗り越えてきた経験があるからこそ、今の姿があるのかもしれません。
「泥中の蓮のように凛と咲きたい」
例文のように、自分自身に言い聞かせるような使い方もよくされます。「座右の銘」にしている人も多いでしょう。 苦しい状況に置かれている時こそ、自分の信念を大切にして乗り越えていきたいものです。
苦難に直面した時は、心のどこかに「泥中の蓮」のイメージを持っておくことで、少し心が軽くなるかもしれませんね。
「泥中の蓮」の類語と対義語を紹介
「泥中の蓮」と近い意味を持つ言葉や、対照的な意味を持つ表現を紹介します。 言葉のニュアンスを把握して、場面に応じた使い分けに役立ててください。

類語・掃き溜めに鶴(はきだめにつる)
価値のない場所や場違いな環境に、ひときわ優れたものや美しいものが存在するさまをたとえた表現です。「掃き溜め」とは、ゴミや塵などが集まる場所のこと。そこに気高く美しい鶴がいるという、対照的なイメージから生まれた言い回しです。
掃(は)き溜(だ)めに鶴(つる)
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
つまらない所に、そこに似合わぬすぐれたものや美しいものがあることのたとえ。ごみために鶴。塵塚(ちりづか)に鶴。
対義語・朱に交われば赤くなる
「人は付き合う相手や環境によって、よくも悪くも影響を受ける」という意味のことわざです。悪い環境に身を置けば心も曇ってしまうし、反対にいい仲間といれば自分も成長できる、という意味でも使われます。
揺るがなさを称える「泥中の蓮」とは異なり、「人は流されやすい」という戒めの言葉です。
「朱(しゅ)に交(まじ)われば赤(あか)くなる」
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
人は交わる友達によって、善悪どちらにも感化される。
最後に
「泥中の蓮」は、ただ美しいだけの言葉ではありません。 それは、日々のプレッシャーに悩みながらも、一歩ずつ前に進んでいる頑張り屋さんの姿そのもののように感じられます。無理に清く咲こうとしなくてもいいですし、泥にまみれても大丈夫です。その中から、あなたらしい花がきっと咲きますよ。
TOP画像/(c) Adobe Stock