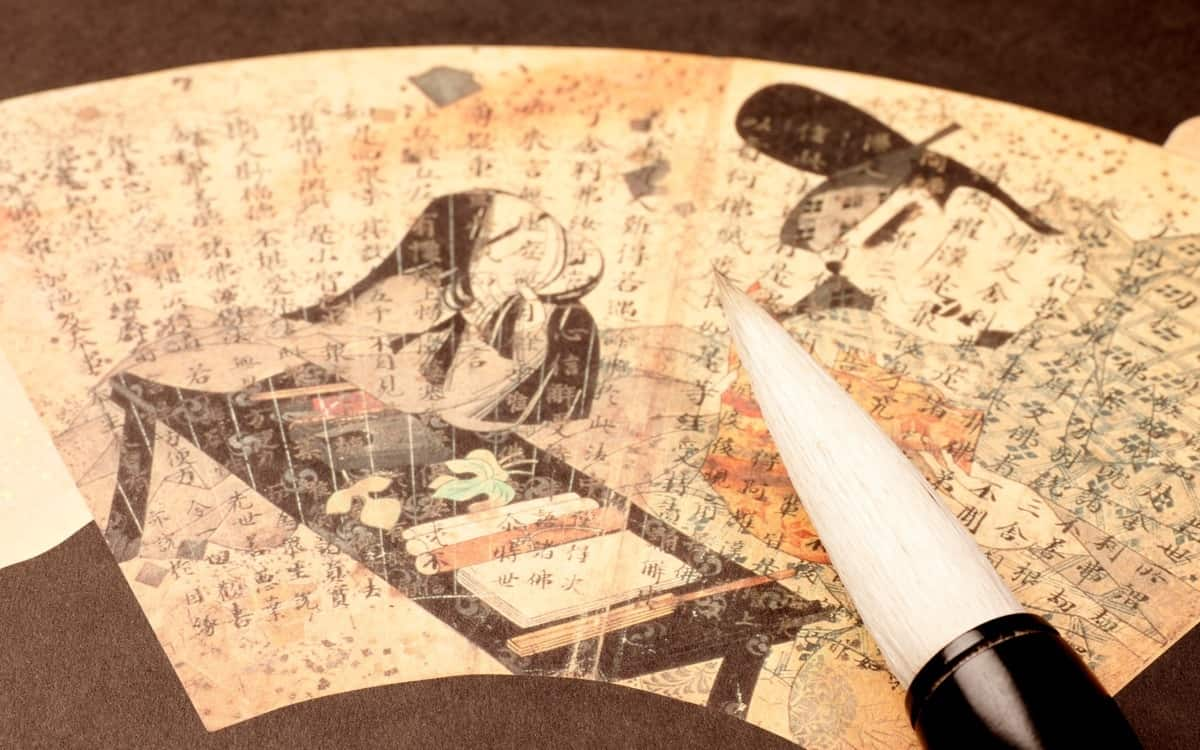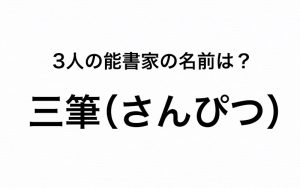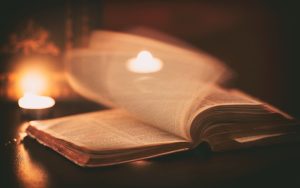歴史の授業で「検非違使」を習ったのを覚えているでしょうか? 最近では人気ゲーム『刀剣乱舞』での登場によって再び注目を集めています。そこで、本記事では、検非違使の基本的な情報を確認しつつ、刀剣乱舞での役割まで解説していきましょう。
「検非違使」とは? その意味や読み方を解説
「検非違使」という言葉は、日本史に関心のある人にはおなじみかもしれません。まずは基本的な情報を確認していきましょう。

「検非違使」の読み方と意味
「検非違使」は「けびいし」と読みます。辞書の定義を確認しましょう。
けびい‐し〔ケビヰ‐〕【▽検非違使】
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
1 平安初期に設置された令外(りょうげ)の官の一。初め京都の犯罪・風俗の取り締まりなど警察業務を担当。のち訴訟・裁判をも扱い、強大な権力を持った。平安後期には諸国にも置かれたが、武士が勢力を持つようになって衰退した。けんびいし。
2 諸国に置かれた検非違使の事務を扱う所。検非違使所。
もともとは、平安時代に設置された役職で、京の治安維持や犯罪の取り締まりを担当する官職を指していました。その役割は、現代の「警察」や「裁判官」のようなもので、都市および地方の秩序を守るために活躍していたとされています。
「検非違使」の歴史的背景とは?
「検非違使」が平安時代にどのような役割を果たしていたのかを詳しく見ていきましょう。
検非違使の歴史
検非違使は、平安時代初期に京内の治安維持と犯罪の取り締まりを目的として設置されました。やがて、その権限は広がり、遠国への出動や民事訴訟の処理、市場管理、道路や河川の修復といった民政まで関与するようになりました。
時代が進むと検非違使の力は弱まり、鎌倉時代以降は武士による支配が主流となったため、次第にその権限を失っていきました。
参考:『日本大百科全書』(小学館)

「検非違使庁」とは?
「検非違使庁」は、検非違使の業務を行う官庁です。左右の使庁が設置されていましたが、947年以降は左庁のみで業務が行われるようになりました。使庁の業務は、律令法に基づいた犯罪捜査や裁判を中心に行われ、独自の法規集「検非違使式」なども整備されていたとされています。
その後、武士の台頭によって権限が縮小されましたが、中世以降も形式的な存在ながら役割を維持し続けました。
参考:『世界大百科事典』(平凡社)
「検非違使忠明」とは?
「検非違使忠明(けびいしただあきら)」という名前をご存じでしょうか? 古典文学に登場し、学校の教科書でも取り上げられることがあります。「検非違使忠明」の概要を見ていきましょう。
「検非違使忠明」とは?
「検非違使忠明」は、『宇治拾遺物語』に収録された説話に出てくる人物のことです。説話の中では、平安時代の検非違使である忠明の勇敢さを描いています。
物語では、若き日の忠明が清水の舞台付近で京の若者たちと争いになります。彼らに囲まれた忠明は、本堂の蔀戸(しとみど)の下方を脇に挟み谷へと飛び降り、難を逃れます。
このエピソードは、忠明の機転と勇敢さを象徴しています。教科書にも採用され、古典文学の学習素材として親しまれていますよ。
「検非違使」と『刀剣乱舞』の関係とは?
「検非違使」という言葉は、人気ゲーム『刀剣乱舞』においても重要な存在として登場します。ゲーム内での「検非違使」の役割について見ていきましょう。

『刀剣乱舞』における「検非違使」の役割
『刀剣乱舞』では、「検非違使」は特定の条件下で出現する強敵として設定されています。「検非違使」は通常の敵よりも強力で、プレイヤーにとって大きな挑戦となります。
「検非違使」の出現条件と影響
「検非違使」は、特定のマップを一定回数以上クリアすることで、そのマップに出現するようになります。これにより、プレイヤーは通常の敵よりも強力な「検非違使」との戦闘を余儀なくされます。
特に、レベルの低い刀剣男士を育成中の場合、「検非違使」の出現は大きな障害となることがあるでしょう。
最後に
「検非違使」という言葉は、歴史的な役職でありながら、現代のゲームにも登場することで多くの人々に知られています。特に『刀剣乱舞』のプレイヤーにとっては重要な要素の一つです。歴史的な背景を理解することで、さらに楽しみが広がるのではないでしょうか。
TOP画像/(c) Adobe Stock