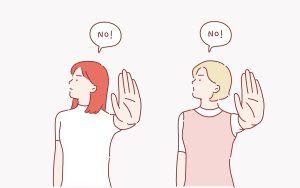目次Contents
この記事のサマリー
・「老いては子に従え」は、「年老いてからは何事も子に任せ、その判断に従うのがいい」という意味のことわざです。
・語源は仏典『大智度論』などです(諸説あり)。
・対義語には、「亀の甲より年の功」「老馬の智」などが挙げられます。
「老いては子に従え」という言葉は、かつては家庭内の教訓として語られてきました。世代交代や価値観の多様化が進む現代にも通じる含蓄があります。親子関係だけでなく、職場や社会でも「譲る」「任せる」ことの大切さを思い起こさせる言葉です。
この記事では意味と語源、そして現代における受け止め方までを、信頼できる辞書・文献に基づいて解説します。
「老いては子に従え」の意味と背景
現代の人間関係にも通じる、「老いては子に従え」という言葉。意味や由来、歴史的背景をひも解くことで、より深く理解できます。
意味
「老いては子に従え」とは、「年老いてからは何事も子に任せ、その判断に従うのがいい」という意味のことわざです。
辞書では次のように掲載されています。
老(お)いては子(こ)に従(したが)え
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
《「大智度論」九九から》年をとってからは、何事も子に任せて従ったほうがよいということ。
語源と歴史的背景
「老いては子に従え」の語源は諸説ありますが、その中の一つに仏教の大乗仏典『大智度論』の一節だというものがあります。
そこでは「女人之体、幼則従父母、少則従夫、老則従子(女性は幼いときは親に、若いときは夫に、老いては子に従う)」とあり、人生の段階に応じて従うべき相手が変わる教えが説かれています。
興味深いのは、このことわざが当初は女性への規範とされた側面がある一方で、時代を経て、男性や一般の年長者にも広く使われるようになった点です。実際、江戸時代の「いろはかるた」では、男性の老人が描かれ、ことわざの対象が男性にまで拡大されていたことが確認されています。
参考:『故事俗信ことわざ大辞典』(小学館)

「老いては子に従え」に違和感? 現代の声と反対語の考察
現代では、「老いては子に従え」に違和感を持つ人も多いようです。ここでは、ことわざの是非や使い方について考察していきましょう。
現代における解釈|「老害」という言葉とどう違う?
現代社会において、「老いては子に従え」ということわざに違和感を覚える人も少なくありません。背景には、「老齢による弊害」といった意味で使われる「老害」という言葉の浸透があります。
ただし、「老いては子に従え」はもともと相手を非難するための言葉ではなく、年を重ねた人が自ら退き、次世代に委ねるという知恵ある行動を促す言葉です。
一方の「老害」は、他人を批判的に形容する現代的スラングであり、用法や立場の異なる表現です。
この違いを理解せずに、「老いては子に従え」を「誰かを責めるためのセリフ」として使ってしまうと、場の空気を悪くする可能性があります。あくまでこのことわざは、「年長者自身のあり方」に目を向けた言葉であることを忘れずに使いたいものですね。
反対語から読み解く価値観の違い
「老いては子に従え」という言葉に対して、「老いても自分の考えは曲げたくない」「経験があるからこそわかることもある」と感じる人もいるでしょう。
このような気持ちを表す言葉として、「亀の甲より年の功」「老馬の智」といった対照的な表現も存在します。
年長者は長年経験を積んでいるだけあって、若者が及ばない知恵があるという意味があります。

「老いては子に従え」の使い方|英語表現・例文も紹介
実際の使い方や応用例を確認し、「使える言葉」にしましょう。
メールや会話での例文
「老いては子に従え」は、会話の中で使うと、世代交代やリーダーシップの譲渡を円滑に伝える言葉として活用できます。
例えば、年老いた親が子に業務を任せる場面で、次のような言い方が考えられます。
例:「老いては子に従えということわざのとおり、店のことは息子に任せることにした」
親を説得しようとする時に、冗談めかして使うこともあります。
例:「そんなに渋らないで、一緒に出かけようよ。老いては子に従えって言うじゃない」
両親が重い腰をなかなか上げてくれない時に、このように冗談めかして誘うことで、言うことを聞いてくれるかもしれませんよ。
英語で言うと?
「老いては子に従え」を英語で表現するなら“When you get old, you had better take your children’s advice.”がいいでしょう。慣用表現です。
参考:『プログレッシブ和英中辞典』(小学館)

「老いては子に従え」に関するFAQ
ここでは、「老いては子に従え」に関するよくある疑問と回答をまとめました。参考にしてください。
Q1. 「老いては子に従え」は誰に向けた言葉ですか?
A.年長者自身に向けた教訓的な言葉です。
Q2. 「老いては子に従え」の類語には何がありますか?
A. 近い意味を持つ言葉としては、「負うた子に教えられて浅瀬を渡る」や「騏驎も老いては駑馬に劣る」などが挙げられます。
Q3. NGな使い方はありますか?(使い方の地雷)
A.「老いては子に従うべきだ」と説教のように使うのは控えましょう。
皮肉や非難に聞こえる可能性が高く、関係性を損なう原因になります。
最後に
「老いては子に従え」とは、「年をとってからは、何事も子に任せて従ったほうがいい」ということ。両親が話を聞いてくれないという場合には、例文で紹介したように軽く促してみることで考えを変えてくれるきっかけになるかもしれませんよ。
目上の人との付き合いかたのヒントとして、「老いては子に従え」を覚えてみてはいかがでしょうか?
TOP画像/(c) Adobe Stock