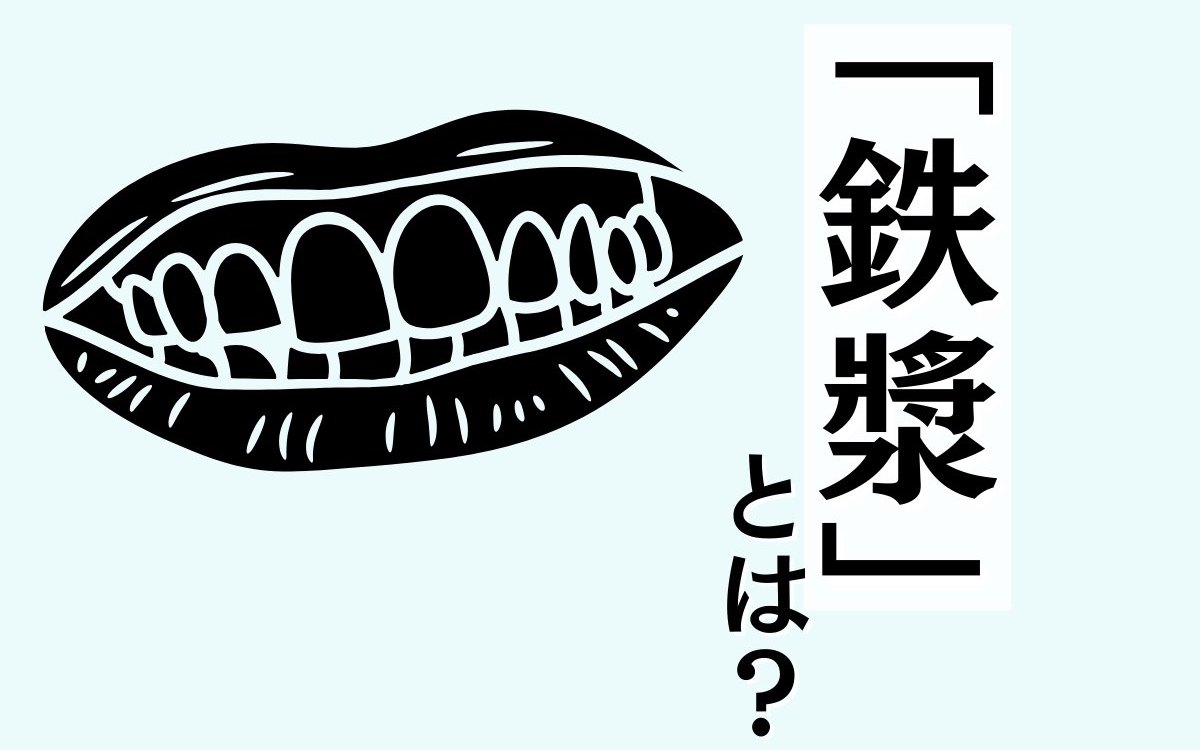「海松色」ってどんな色?
緑色といっても、深みのある色から明るい色まで、さまざまな色味があります。海松色(みるいろ)は、くすんだ濃い黄緑色で、見る人に落ち着いた印象を与える色です。
ここでは、海松色の名前の由来や海松色と相性のよい色とされている「若草色(わかくさいろ)」について解説します。平安時代から登場している海松色について、理解を深めていきましょう。
海松色(みるいろ)の意味
「海松色(みるいろ)」は、海藻の一種である「海松(みる)」に由来します。黒みがかった黄緑色で、やや茶色みを感じる色合いです。
この「海松」という言葉は、万葉集の時代から登場していたものの、色の名前として定着したのは平安時代からだとか。伝統的な装束においては、表に萌葱、裏に青を合わせた襲の配色で、海中の岩場に付着する海松の風合いを巧みに表現しました。なお、表は黒萌葱、裏は白という説もあります。
みる【海=松/水=松】
出典:小学館 デジタル大辞泉
1 ミル科の緑藻。干潮線から水深約30メートルの岩上に生え、高さ20~40センチ。体は丸ひも状で二またに分枝を繰り返し、扇状となる。食用。みるめ。みるぶさ。みるな。またみる。《季 春》「汐満ぬ雫うれしや籠の―/召波」
2 「海松色」に同じ。
みる‐いろ【海=松色/水=松色】
出典:小学館 デジタル大辞泉
1 黒みがかった萌葱色。木賊色。みる。
2 襲の色目の名。表は萌葱、裏は青。また、表は黒萌葱、裏は白。

海松色の由来
海松(みる)はY字型に枝分かれし、扇を広げたような形をしています。最大で約40センチほどに成長するとされる海藻です。
現在ではあまり食用とされることはありませんが、古代日本では一般的な食用海藻として重宝されていたようで、『万葉集』にも「見る」という語と掛け合わせて詠まれた歌がみられます。
海松の先端が整った特徴的な形状は、古来より美しい模様として意匠に取り入れられ、「海松模様(みるもよう)」として親しまれてきたとか。
▼あわせて読みたい
海松色に合う若草色(わかくさいろ)
海松色と相性の良い色には、若草色(わかくさいろ)が挙げられます。若草色は、春の訪れを感じさせる明るく鮮やかな緑です。
海松色はやや落ち着いたトーンなのに対し、若草色は軽やかでフレッシュな印象を与える色といえます。2色を一緒にともに用いることで、穏やかさの中に若々しいエネルギーを感じる配色になるでしょう。
海松色のほかにも! さまざまな「緑色」
緑色には、海松色をはじめとするさまざまな色彩があります。たとえば、清々しく透明感あふれる翠色(すいしょく)は、自然のなかで見る新緑を連想させるでしょう。また、青柳(あおやぎ)は深い森の中で輝く若葉のようで、森林の生命力を象徴した色合いです。
これらの色は、自然界の豊かな表情を象徴し、私たちの心を豊かに彩ります。ここでは、さまざまな緑色についてみていきましょう。

翠色(すいしょく)
「翠色(すいしょく)」とは、カワセミの羽のように鮮やかで美しい緑系の色を指します。読み方は「みどりいろ」や「みどり」とされることもあり、別名は「翠緑(すいりょく)」です。
日本では昔から、緑に関するさまざまな表現が存在していました。しかし「翠色」という言葉が広く使われるようになったのは、近代以降とされているようです。
青柳(あおやぎ)
「青柳(あおやぎ)」は、春に芽吹いた柳の若葉のような、やや黄みがかった鮮やかな緑色のことです。
平安時代以降に用いられていた「襲の色目(かさねのいろめ)」の名でもあり、表裏とも濃い青、または表は青・裏は薄青の色の取り合わせとされています。
なお、青柳にちなんだ色として、「青柳鼠(あおやぎねず)」のような派生色も存在します。
深碧(しんぺき)
「深碧(しんぺき)」とは、濃い緑色のことです。緑碧玉(りょくへきぎょく)という鉱物の色とされているようです。一般的な「碧色(へきしょく)」よりもさらに深みの増した緑色を表します。
緑碧玉とは、石英(クォーツ)の結晶です。さまざまな不純物が含まれ、含まれている不純物の種類によって結晶の色が変わります。
孔雀緑(くじゃくみどり)
孔雀緑(くじゃくみどり)は、孔雀の羽根のように鮮やかな青緑色。その名の通り、孔雀の羽に見られる青みのある緑色から着想を得ています。「ピーコックグリーン」という英語の色名が日本語訳されたことで誕生したようです。
柚葉色(ゆずはいろ)
柚葉色(ゆずはいろ)は、その名の通り柚子の葉の色にちなんだ深みのある緑色です。「ゆばいろ」と読まれることもあります。
柚子はミカン科に属する常緑樹で、爽やかな香りとほどよい酸味を持つ果実として知られています。奈良時代にはすでに日本で栽培されていた記録があり、当時から薬として、あるいは料理の風味付けに用いられてきたようです。
なんて読むの? どんな色? 難読カラーをチェック
日本にはさまざまな色があり、なかには漢字が難しく「難読」とされる色もあります。たとえば、深い緑とも茶色ともつかない神秘的な色合いである「楝色」です。森林の奥深くに光が差し込むような印象を与えます。
また、淡い赤茶色の丁子色は日本の伝統的な色彩のひとつであり、温かみのある色合いです。ここでは、難読カラーについてみていきます。

楝色(おうちいろ)
やわらかな青みを帯びた淡い紫色は、「楝色(おうちいろ)」と呼ばれます。この「楝(おうち)」は、センダン科に属する落葉高木の古い呼び名であり、古くから人々に親しまれてきました。初夏に咲く、薄紫の花の色が名前の由来です。
丁子色(ちょうじいろ)
淡くやわらかな茶系の色合いの「丁子色(ちょうじいろ)」は、古くから伝わる日本の伝統色です。開花前に摘まれた丁子(ちょうじ)の蕾を用いて染め上げたことから、この名前がつきました。
丁子はクローブとして知られる木のことであり、生薬や香料、スパイスとしても広く活用されています。原産地は東南アジアで、当時の日本ではとても貴重だったため、上流階級の人々のみが使える特別な色とされていました。
空五倍子色(うつぶしいろ)
「空五倍子色(うつぶしいろ)」は、ほんのり紫がかった灰みの濃い茶色です。ウルシ科の植物・白膠木(ぬるで)の枝にアブラムシという虫が寄生することでできる、虫こぶから生まれます。
その瘤は「付子(ふし)」または「五倍子(ごばいし)」と呼ばれ、砕いて煮出すと、タンニン酸を多く含んだ濃い染液が得られます。
▼あわせて読みたい
身近にある海松色を探してみよう!
海松色(みるいろ)のように身近な色でも、聞き馴染みのない名前がついているかもしれません。色名を知ることで、日常の色彩に新たな深みが加わります。海松色のような繊細な色合いや、楝色(おうちいろ)、丁子色(ちょうじいろ)、空五倍子色(うつぶしいろ)まで、それぞれに歴史があります。さまざまな色を通じて、自然や文化の豊かさを感じ取ってみましょう。
メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock