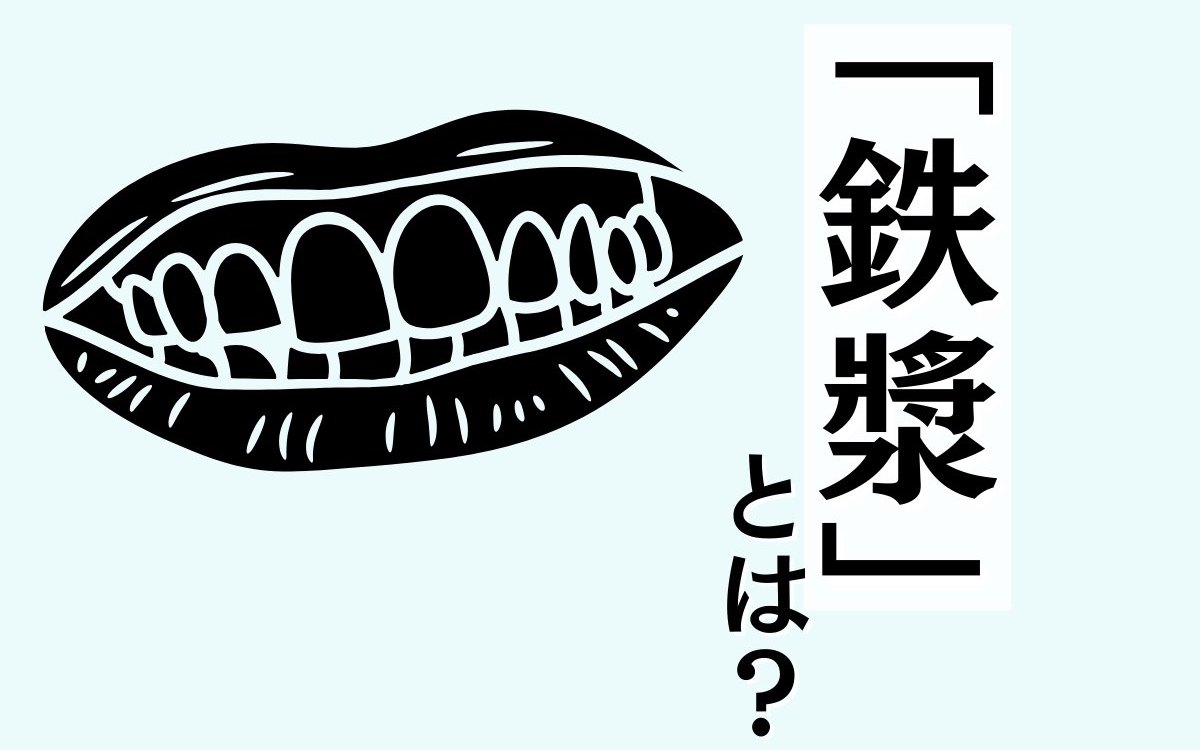鉄漿とは?
鉄漿は「かね」と読みます。お歯黒に使われていたため、鉄漿はお歯黒を指して使うことも。
ここでは、鉄漿の意味やお歯黒について解説します。
お歯黒に使う液のこと
鉄漿は、鉄を水に浸して作った、黒い液のことです。鉄片を濃い茶の中に入れ、粥や酒などを加えて酸化させて作ります。鉄漿は、お歯黒という歯を黒く染める風習で使われていました。
お歯黒では、筆に鉄漿を含ませ、五倍子(ごばいし)粉と呼ばれる粉とともに歯に塗ることで、黒い皮膜を作ります。一度塗るだけでは真っ黒には染まらないため、数日おきに繰り返し塗って歯に染み込ませていたとか。
鉄漿は熱すると臭気が強いため、朝、家族が起きる前に塗っていたとされています。また、五倍子粉はタンニンを多く含むため、非常に渋かったようです。そのため、歯黒を塗ったあとはよく口をゆすがなければなりませんでした。
かね【鉄=漿】
出典:小学館 デジタル大辞泉
お歯黒に用いる液。茶の汁や酢、酒に鉄片を浸して酸化させたもの。おはぐろ。
お歯黒を指して使うこともある
鉄漿はお歯黒で使う染料のことですが、お歯黒そのものを指して使われることもあります。お歯黒は、平安時代に上流階級の女性の間で行われていた風習で、平安後期には公家や武家の男性も行っていたようです。
のちに民間にも流行が広がり、江戸時代には既婚女性のシンボルに。お歯黒の風習は、その後明治初期まで続いたといわれています。
お歯黒は女性の習慣だった?
お歯黒(鉄漿)の歴史は古く、日本では紀元前にもお歯黒の形跡が見られているとか。
ここでは、お歯黒の由来や歴史、習慣が長く続いた理由を見ていきましょう。
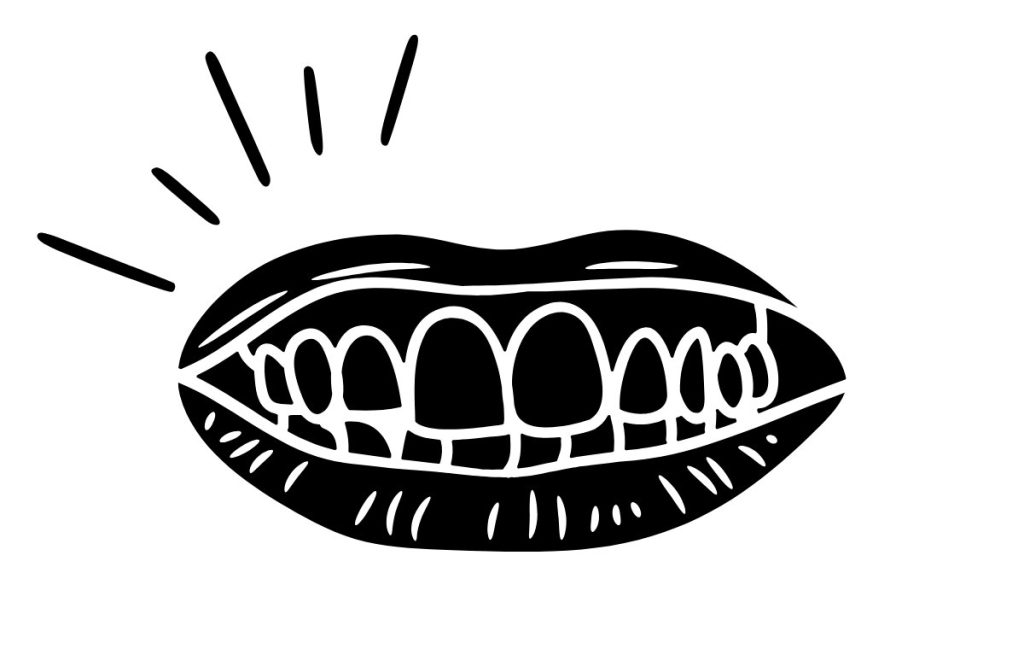
お歯黒の由来
お歯黒の歴史は古く、紀元前3世紀ごろの古墳内の人骨に形跡がみられていることから、弥生時代から古墳時代にかけて定着したのではとも考えられているようです。
お歯黒の由来には、日本古来あったという説や他国から伝わったという説など諸説がありますが、どれも明らかではありません。
また、3世紀末に書かれた中国の歴史書「三国志」魏志倭人伝の冒頭には「歯黒国アリ」という記述があり、お歯黒が行われていたと推測されています。
お歯黒の歴史
お歯黒は、平安時代に上流階級の象徴とされ、広がりをみせました。貴族の男性・女性の成人の儀式としてお歯黒をしていたということです。
鎌倉時代には下級武士にも広がり、戦国時代には公家や大名、上級武士に限られるようになったとされています。
江戸時代に入ると庶民にも広がり、女性だけの習慣に。黒は何色にも染まらない色ということで貞操を表し、結婚している女性の象徴となったようです。
その後、お歯黒は明治時代まで続き、明治政府の近代化政策により禁止されました。貴族階級に向けてお歯黒をやめるよう通達が出されたものの、長年続いた習慣をすぐにやめることには戸惑いもあったようです。昭憲皇太后が自らお歯黒をやめたことで、一般にも浸透していったとされています。
お歯黒の習慣が長く続いた理由
お歯黒の習慣が1000年以上と長く続いた理由は、単なる流行ではなく、成人式の儀式や婚約・結婚の通過儀礼として定着していたことが挙げられるでしょう。江戸時代は既婚女性のシンボルであり、封建制度下における女性を人妻として制約する役割も果たしたようです。
また、当時は黒光りする歯が美しいとされ、艶のある黒い歯が当時の女性にとっておしゃれだったということも、長く続けられていた理由といえるかもしれません。
このほか、歯並びの悪さや虫歯の変色を隠せるといった理由で好まれていたという見方もあるようです。
お歯黒の豆知識
お歯黒は既婚女性の習慣だったというイメージがありますが、実は虫歯の予防効果があったとされること、男性もお歯黒をしていたことはあまり知られていないのではないでしょうか。
ここでは、お歯黒の豆知識を紹介します。

お歯黒は虫歯の予防効果があった?
墓から掘り起こされたお歯黒の歯には、虫歯がほとんどなかったとか。
これは、お歯黒に塗る鉄漿とタンニンを含んだ五倍子紛が、虫歯予防につながったのではと考えられています。また、お歯黒をする際にまず楊枝で歯垢を取り除いたことも、虫歯の進行を防いだ理由の一つかもしれないようです。
男性もお歯黒をしていた
前の項目でも少し触れましたが、江戸時代より前の時代には男性もお歯黒をしていました。男性がお歯黒をするようになったのは、平安時代の鳥羽上皇のころといわれています。
上皇は虫歯があったために、人と話をするのを避けていたとか。臣下は政務の裁可を仰がなければならず、話をしてもらうために、お歯黒をして「自分たちも歯が黒い」ということを示したという逸話があります。
平安時代には元服と呼ばれる成人の儀式としてお歯黒をし、それから公卿や皇族寄りの武家などの間で広がっていったようです。源平合戦の際には、武将もお歯黒をするようになったといわれています。
鉄漿とはお歯黒にまつわる言葉
鉄漿は「かね」と読み、お歯黒に使う染料のこと。お歯黒自体を指して使うこともあります。お歯黒は日本で古くから続いてきた習慣で、江戸時代から明治初期までは既婚女性のシンボルとなっていました。
お歯黒は虫歯予防の効果もあったと考えられ、長く続いた理由のひとつではないかとされています。
メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock