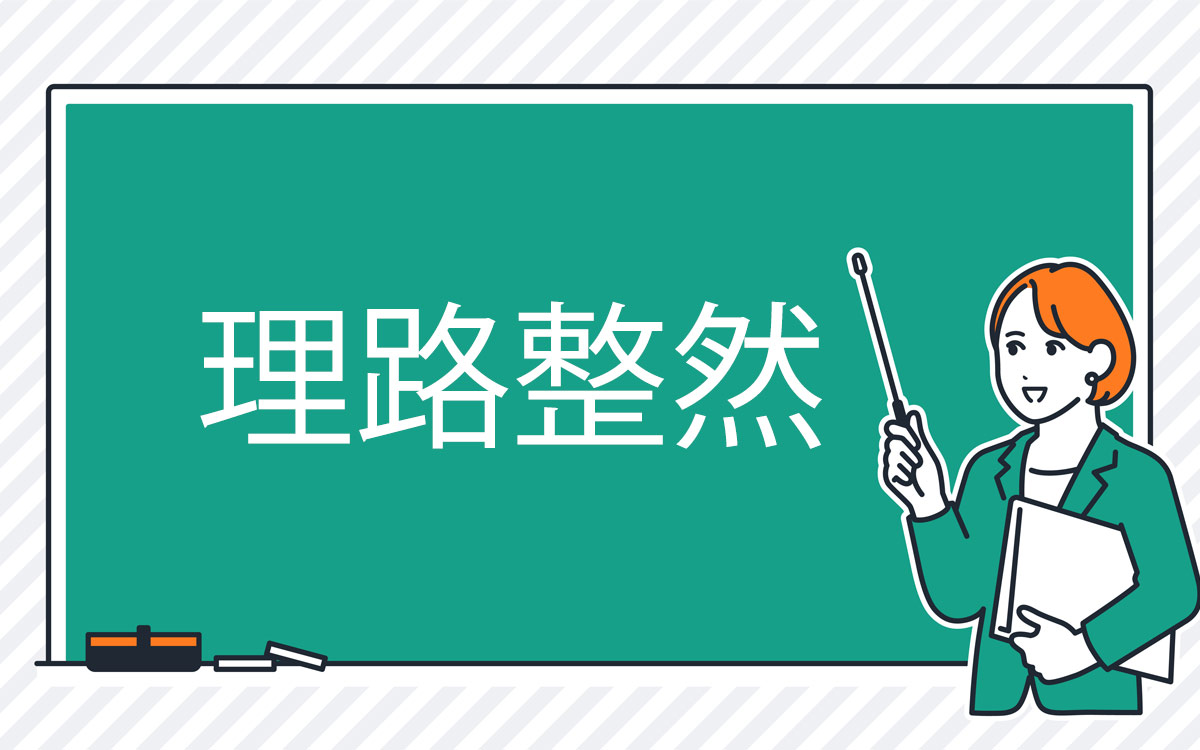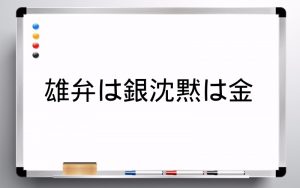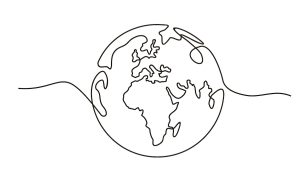目次Contents
「獅子吼」の意味と読み方
「獅子吼(ししく)」とは、意気盛んに大演説をすることです。「吼」には「ほえる」という意味があり、まるでライオンが吼えるかのように、雄弁に語るさまを表します。
また、仏教では説法を「獅子吼」と言うことがあります。そもそも説法とは、仏教の教えをよくわかるように、話して聞かせることです。
日常生活では「雄弁に演説する」というニュアンスで使うのが一般的ですが、獅子吼には2つの意味があることを覚えておきましょう。
しし‐く【×獅子×吼】
出典:小学館 デジタル大辞泉
[名](スル)
1 雄弁をふるうこと。意気盛んな大演説をすること。「壇上に獅子吼する」
2 仏の説法。獅子がほえて百獣を恐れさせるように、悪魔・外道げどうを恐れ従わせるところからいう。
「獅子吼」の由来
「獅子吼」という言葉は仏教の経典でよく使われる表現で「法華経(ほけきょう)」にもその場面があるとされています。「法華経」は、お釈迦様の説いた教えをまとめたものです。
お釈迦さまは仏教の開祖であり、信者にとって、その教えは畏れ多いものでした。そのため、獅子が吼え多くの獣を恐れさせる様子にちなんで、法の説法で悪魔や外道を従わせるさまを「獅子吼」とたとえるようになったとか。
転じて、獅子が吼えるように雄弁に語るさまも「獅子吼」と言い表すようになりました。現代社会では、大勢の前で自分の意見を主張するような演説の場面で頻繁に用いられています。

「獅子吼」の使い方
人の心を打つ迫力ある演説や、堂々と語るさまを表す際は、以下のように「獅子吼」を活用してください。
・選挙の投票日を明日に控え、候補者が獅子吼する姿が各地で見られた
・壇上で獅子吼する彼女の姿に、誰もが胸を打たれた
・部下に対し仕事の流儀を語る上司は、まさに獅子吼だった
・誰もが経営の先行きに不安を抱える中、彼女だけが今こそ新事業に乗り出すべきだと獅子吼した
「獅子吼」の類語や言い換え表現
以下の類語や言い換え表現は、「獅子吼」と似た意味をもつといえます。
・流暢(りゅうちょう)
・雄弁(ゆうべん)
・弁が立つ(べんがたつ)
・舌を振るう(したをふるう)
それぞれの正しい意味と使用例、「獅子吼」との違いを知り、状況に応じて使い分けましょう。

「流暢(りゅうちょう)」
「流暢」とは、よどみなく次々と言葉を発することです。言葉に詰まらず語るさまは「獅子吼」と共通しているといえるかもしれません。
異なるのは「獅子吼」のような「雄弁に演説する」という意味合いはもたない点です。おもに「英語を流暢に話す」のように、言葉をすらすらと発するさまを表します。
・留学経験のある彼女は、海外の取引先との商談で英語を流暢に話した。
・日本に滞在して1年というイギリス人と会食したのだが、あまりにも日本語が流暢で驚いた。
「雄弁(ゆうべん)」
説得力をもつ、力強い話し方は「雄弁」と表します。「獅子吼」と、とてもよく似た意味合いをもつ言葉です。
「演説する」というニュアンスが強い「獅子吼」に比べると、「雄弁」はより幅広いシーンで活用できます。
登壇者の語り口はもちろん、対面でとったコミュニケーションの印象を表すこともあるでしょう。以下のように、物から受けた印象を伝えたいときにも使用できます。
・ビジネスが成功するまでどのような困難を乗り越えてきたのか、自身の経験について彼は雄弁に語った
・今回のセミナーの登壇者は、雄弁な指導者として知られている
・倒壊した家屋の状況が、自然災害のすさまじさを雄弁に語っていた
・彼女は多くを口にしなかったが、その目は真実について雄弁に語っているように思えた
▼あわせて読みたい
「弁が立つ(べんがたつ)」
「弁(べん)」とは、人の話し方のことです。また、物事の筋道や道理など、理屈立てて話すさまも表します。
「弁」に「立つ」を重ねた「弁が立つ」は、話し方がうまく雄弁な様子を表す言葉です。ただし「ライオンが吼えるかのような迫力ある話し方」という意味は含まれません。
「獅子吼」と比べると、理路整然と話したり、他者を納得させるほど話し方がうまかったりというようなニュアンスが強くなるといえます。
・弁が立つ政治家のスピーチに、その場にいた人々は思わず耳を傾けた
・弁が立つ彼女のおかげで、会議がスムーズに進行した
▼あわせて読みたい
「舌を振るう(したをふるう)」
盛んに話したり、雄弁に語ったりすることは「舌を振るう」と言い表します。
そもそも「振るう」とは、物事が充実し勢いが盛んなことです。また、存分に力を発揮するという意味も含まれます。
「舌を振るう」は「振るう」を使った慣用句です。ほかにも、体の一部を使った「振るう」の慣用句には、「腕を振るう」があります。
「腕を振るう」とは、自分の力を存分に見せつけたり、技能を存分に発揮したりすることです。「舌を振るう」とあわせ、ひとつの知識としておさえておきましょう。
・セキュリティ対策の重要性について、彼女は舌を振るって力説した
・週末は自宅に同僚を招き、久しぶりに料理の腕を振るった

ことわざ「河東の獅子吼」の意味とは
「河東の獅子吼(かとうのししく)」は、嫉妬深い妻が夫にがみがみいうこと。夫に対する口うるさい妻の様子を獅子にたとえ、皮肉ったことわざです。ただ小言を言うのではなく、ライオンが吼えるかのような激しい口ぶりを表しています。
中国で生まれたことわざで、「河東」は中国の黄河の東側を意味しています。
・隣の家では、また夫が妻に怒鳴られているようだ。河東の獅子吼とは、まさにこのことだな
・残業で帰りが遅い日が続いているからか、妻が以前より輪をかけて河東の獅子吼になった気がする
「獅子吼」は雄弁に話す様子を表す言葉
まるでライオンが吼えるかのように、力強く雄弁に話すさまは「獅子吼」と表します。おもに、大勢の前で意見を述べるような演説の場面に適した表現です。
類語の種類や活用法を知れば、シーンに応じた的確な言い回しを実現できます。「獅子吼」の意味をおさえたうえで、それぞれをビジネスや日々のコミュニケーションに取り入れていきましょう。
メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock