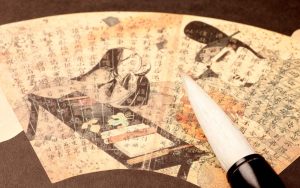「百家争鳴」という言葉を目にしても、読み方に迷ったり、少し難しく感じる人もいるかもしれません。少し硬い印象のある言葉ですが、今の社会をとてもよく言い表している一面があります。
この記事では、歴史的な背景をふまえながら、「百家争鳴」の意味や使い方、どんな場面で使われる言葉なのかを紹介していきます。
自由な議論が飛び交う「百家争鳴」とはどんな言葉?
「百家争鳴」の読み方と意味、使われるようになった背景について整理します。
「百家争鳴」読み方と意味を確認
「百家争鳴」は「ひゃっかそうめい」と読みます。あまり聞きなれない言葉かもしれませんね。辞書の引用を見ながら言葉の意味を確認しましょう。
ひゃっか‐そうめい〔ヒヤクカサウメイ〕【百家争鳴】
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
多くの知識人・文化人が、その思想・学術上の意見を自由に発表し論争すること。中国共産党の文化政策スローガンの一。1956年「百花斉放」とともに提唱された。
「百家争鳴」とは、多くの人が自由に意見を述べ合い、さまざまな考えがぶつかり合うような状態を表しています。

「百家争鳴」の由来と背景
「百家争鳴」は、もともと古代中国で思想家たちが自由に意見を述べ合い、活発に議論を交わす様子を表す言葉として使われていました。
1956年に、中国共産党はこの言葉をスローガンとして掲げ、知識人による自由な発言を促す政策を進めました。「百花斉放(ひゃっかせいほう)」と並ぶ文化方針のひとつとされ、学問や芸術の分野で多様な意見が尊重されることが期待されました。
しかし、党への批判が強まったことから、翌年には方針が転換され、言論の自由は次第に制限されていきました。
参考:『日本大百科全書』、『日本国語大辞典』(小学館)
「百家争鳴」の使い方を例文とともに確認
「百家争鳴」という言葉は、場面に合った使い方をすれば、意味がすっと伝わる表現です。現代の文脈では、どのように使われているのでしょうか。いくつかの例を通して見てみましょう。
「現代社会はまさに百家争鳴の時代です」
インターネットやSNSでは、多様な立場からの意見が自由に交わされています。今の社会こそ、誰もが自分の考えを自由に発信できる時代なのかもしれません。
こうした状況を表す言葉として、「百家争鳴」は今でも自然に使える表現です。

「学会は百家争鳴の様相を呈していた」
「百家争鳴」は、専門的な分野で、さまざまな意見が交わされている状況を表すときにも使うことができます。知的な議論の場を描写するときに、自然に使える言い回しですね。
「百家争鳴」の関連語と英語表現を紹介
「百家争鳴」と関係のある言葉や、英語表現を紹介します。
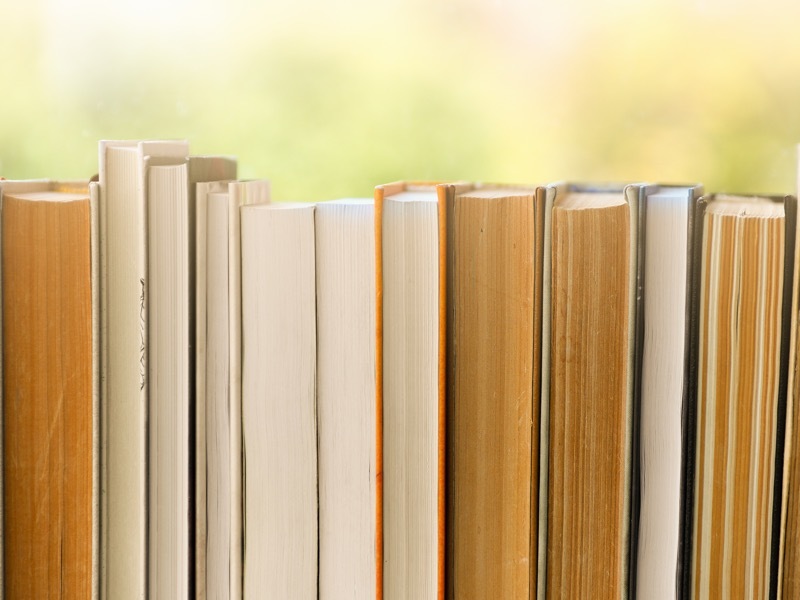
「百花斉放」との違い
「百花斉放」は、「ひゃっかせいほう」と読みます。意味を辞書で見てみましょう。
ひゃっか‐せいほう〔ヒヤククワセイハウ〕【百花斉放】
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
《いろいろの花が一斉に咲き開く意》文学・芸術において、多くの人々が活発に運動を展開すること。
「百花斉放」は、芸術や文化の分野で、多くの人が自由に表現し、創作活動が盛んに行われている様子を表します。一方の「百家争鳴」は、学問や思想の分野でさまざまな意見が交わされる状態を意味します。
どちらも1956年の中国の文化政策に使われた言葉ですが、それぞれ扱う領域が異なる点に注意が必要です。
「諸子百家」
「諸子百家(しょしひゃっか)」とは、古代中国の春秋戦国時代に現れた、多くの思想家や学派の総称です。例えば、儒家の孔子や孟子、道家の老子や荘子、ほかにも墨家、法家、兵家などが含まれます。
「百家争鳴」は、こうした「諸子百家」が活発に議論を交わしていた状況を指す言葉です。
参考:『デジタル大辞泉』(小学館)
“Let a hundred schools of thought contend.”
「百家争鳴」は、英語の“Let a hundred schools of thought contend.” という表現で知られています。通常は“Let a hundred flowers blossom and a hundred schools of thought contend.” と続け、「百花斉放・百家争鳴」として紹介されることが多いでしょう。
多様な意見や思想が自由に語られるべきだ、という考えが込められており、1956年中国共産党の文化政策スローガンとして掲げられました。
参考:『プログレッシブ和英中辞典』(小学館)
最後に
「百家争鳴」は、多くの人が自由に意見を述べ合うことを意味する言葉です。もとは古代中国で、思想家たちが活発に論じ合っていた様子を表していましたが、のちに政治的なスローガンとしても使われるようになりました。
意見の違いに出会うことが多い今だからこそ、「百家争鳴」が示していた姿勢から学べることは多いように思います。互いの考えの違いを認めながら、落ち着いて向き合おうとする姿勢を、日頃から大切にしたいですね。
TOP画像/(c) Adobe Stock