「見参(けんざん)」という言葉には、どこか古風な感じがします。とはいえ、ゲームであったり、作品名でも目にする機会があるため、意外と身近な言葉であるともいえるかもしれません。
この記事では、「見参」の意味や「見参に入る」の解説、「参上」、「推参」との違いから『龍が如く 見参!』まで丁寧にひもといていきます。
「見参」とは?|読み方と基本の意味を解説
「見参」という言葉には、どこか古風な響きがありながら、現代でも舞台や文学の中などで目にすることがあります。まずは、その読み方と意味を整理してみましょう。
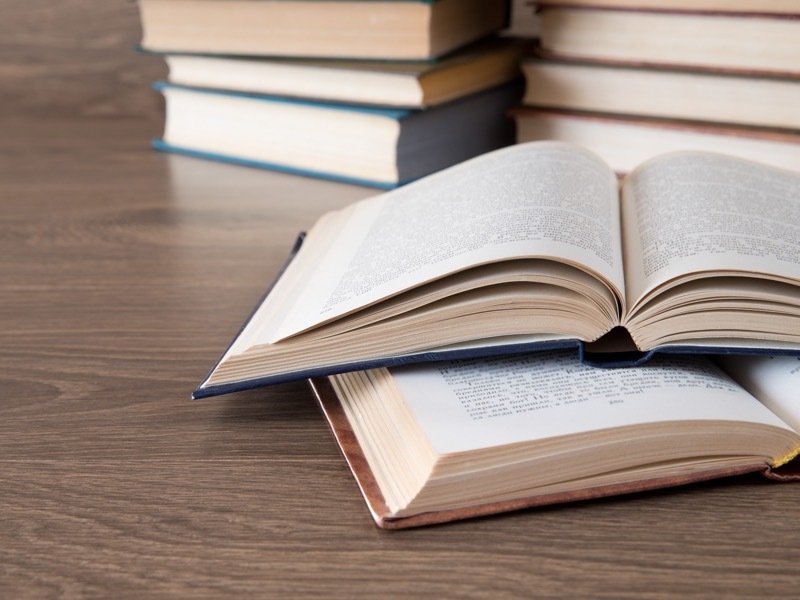
「見参」の読み方と意味
「見参」は「けんざん」「げんざん」「げざん」「げんぞう」などと読みます。いずれも同じ意味です。辞書には次のように記されています。
げん‐ざん【▽見参】
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
[名](スル)《「けんざん」とも》
1 参上して目上の人に対面すること。げざん。げんぞう。
「婿が岳父(しゅうと)に―するという風に」〈鴎外・雁〉
2 目上の人が目下の者に会ってやること。げざん。げんぞう。
「我御前(わごぜ)があまりにいふことなれば、―して帰さん」〈平家・一〉
3 節会(せちえ)や宴会などに出席すること。また、出席者が記名して、その主人の前に差し出すこと。げざん。げんぞう。
「陣に付きて宣命、―を見給ひける間」〈著聞集・三〉
つまり「見参」は、尊敬や格式をともなう場面で「人前に姿を現すこと」や「目上の人物と会うこと」を意味します。日常会話ではあまり使われませんが、時代劇や古典文学、伝統的な式典などで見かける言葉だといえるでしょう。
「見参に入る」とは?
「見参に入(い)る」という表現も、時代劇などで耳にする機会があるかもしれません。
こちらも辞書で意味を確認しましょう。
見参(げんざん)に入(い)・る
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
一(「入る」が四段活用の場合)貴人に対面する。お目にかかる。
「法皇の―・らばや」〈平家・四〉
二(「入る」が下二段活用の場合)貴人に対面させる。お目にかける。
「頸をば判官の―・れんとて取りてゆく」〈平家・一一〉
「見参に入る」には、二通りの意味があります。一つは、「自分が貴人の前に出て、直接お目にかかること」。もう一つは、「誰かを目上の人に紹介し、面会させること」です。
現代では、もっぱら時代劇や文学作品で使われています。

「見参」と「参上」、「推参」の違いとは?
「見参」、「参上」、「推参」は、いずれも“人のもとを訪れる”という広い意味では似た言葉ともいえますが、使い方には違いがあります。ここでは、それぞれの言葉の違いを整理してみましょう。
「参上」と「見参」の違い
まずは、「参上」の意味を辞書で確認しておきましょう。
さん‐じょう〔‐ジヤウ〕【参上】
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
[名](スル)目上の人の所に行くこと。また、人のもとに行くことをへりくだっていう語。まいること。うかがうこと。「御殿に―する」「明日―いたします」
「参上」は、相手に敬意を表しながら自分の行動をへりくだって述べる謙譲語です。現代でも、「後ほど参上いたします」などというように、ビジネスや改まった場面で使われることがあります。
一方「見参」は、参上そのものを目的とするのではなく、“相手と対面すること”や“人前に姿を現すこと”を表現します。「参上」が“行くこと”に主眼があるのに対し、「見参」は“会うこと”に焦点がある点が大きな違いです。
「推参」と「見参」の違い
続いて、「推参」の意味も見てみましょう。
すい‐さん【推参】
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
[名・形動](スル)
1 自分のほうから出かけて行くこと。また、招かれていないのに人を訪問することを、詫びる気持ちをこめていう。
「夜中に―して奉行衆に逢いたいと云うのは宜しくない」〈鴎外・堺事件〉
2 出すぎていること。差し出がましいこと。無礼なこと。また、そのさま。
「是は―な奴だ、人の運動の妨(さまたげ)をする」〈漱石・吾輩は猫である〉
「推参」は、特に“招かれていないのに行くこと”を表し、「勝手に押しかけてしまってすみません」といった含みを持つ表現です。時に自嘲気味に使われることもあるでしょう。
「見参」との違いは、「見参」が貴人など目上の人物との対面を前提とするのに対し、「推参」は相手の立場にかかわらず、自分の意志で訪問することを表す点にあります。
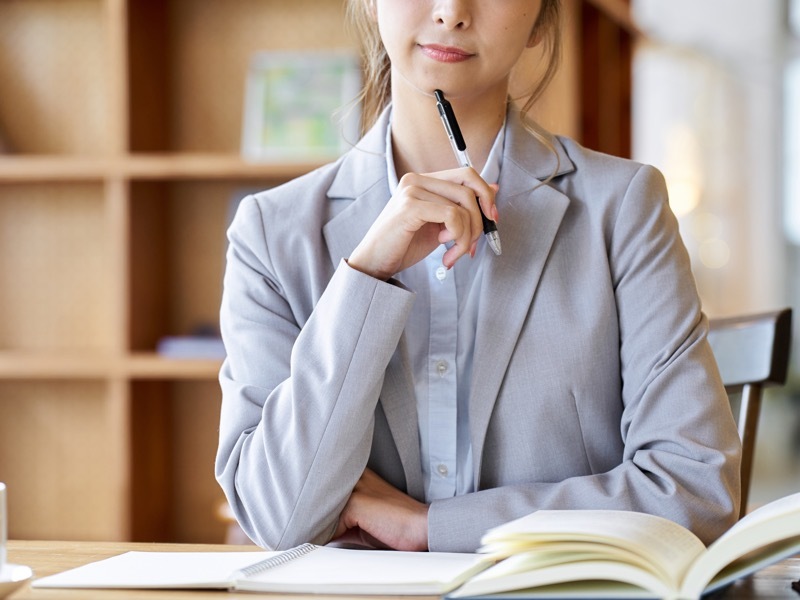
『龍が如く 見参!』とは?
『龍が如く 見参!』は、セガが2008年3月に発売したプレイステーション3用のアクションアドベンチャーゲームです。
舞台は、激動の江戸時代。人が人を斬ることで己を極めようとした時代に、剣にすべてを懸けた男たちの生き様が描かれています。歴史を背景にした壮大な人間ドラマが展開されるのが特徴です。
松田翔太さん、寺島進さん、加藤雅也さん、塚本高史さん、竹中直人さん、そして松方弘樹さんが、声優としてだけでなく、実際のビジュアルモデルとしても登場しています。リアルな人物描写とドラマ性が融合した、魅力が詰まった一作です。
参考:『デジタル大辞泉プラス』(小学館)
最後に
「見参」など、古くからある言葉を知ることで、言葉の奥にある人と人との距離の取り方や敬意のあり方にも、自然と目が向くようになりますね。
TOP画像/(c) Adobe Stock























