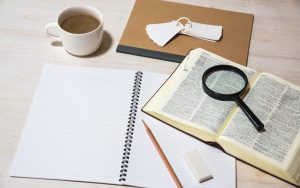衣紋(えもん)とは? 関連する言葉も
衣紋(えもん)とは、衣服を形よく、着崩れしないように着ることです。また、和服の後ろの襟を指すことや、単に衣服や身なりを指すこともあります。
衣紋は、次のような複合語としても使われます。
・抜き衣紋(ぬきえもん)
・衣紋抜き(えもんぬき)
・衣紋掛け(えもんかけ)
・衣紋道(えもんどう)
それぞれの言葉の意味を見ていきましょう。
抜き衣紋とは?
抜き衣紋とは、着物を着るときに襟部分を後ろにずらして項(うなじ)が見えるようにすることです。「抜き襟(ぬきえり)」と呼ぶこともあります。
抜き衣紋をすることで襟足や項が美しく見え、着姿も美しくなります。一般的にこぶし1個分を抜くとよいとされていますが、あまり抜きすぎると下品に見えるため注意が必要。礼装を着用するときは縦向きのこぶし1個分、小紋や紬などのカジュアルな着物は横向きのこぶし1個分程度に調整しましょう。
また、年齢によっても抜き加減を変えると、それぞれの年齢らしい着姿に見えます。10〜20代は横向きのこぶしで控えめに、30〜40代は縦向きのこぶし1個分に、50代以降は横向きこぶし一個分を目安として押さえておくとよいでしょう。

衣紋抜きとは?
衣紋抜きとは、抜き衣紋をした状態を崩さないために用いるアイテムです。男性と子どもは原則として抜き衣紋をしないため、衣紋抜きも使用しません。
衣紋抜きは着物を着るときの必須アイテムではありません。しかし、時間が経過しても衣紋が詰まりにくくなり、着付けしたばかりの美しさを保つ効果があるため、長時間着用するときには使用するとよいでしょう。
衣紋掛けとは?
衣紋掛けとは、着物用のハンガーのことです。着物は畳んで片付けますが、長時間放置するとしわが寄ってしまうことも。また、しっかりと乾燥させてから片付けることで、黄ばみや虫などを避けやすくなります。衣紋掛けを使って、着用前後は鴨居などにかけておくようにしましょう。
衣紋掛けは、数十cm~1mほどの棒の中央に紐がついた構造です。紐にS字フックがついている場合はそのまま鴨居や家具に引っかけ、フックがない場合は鴨居に釘を打ち付けて引っかけます。
着物の形は、襟以外が直線断ち・直線縫いで、生地の重みもあるため、長時間洋服のハンガーに掛けておくと肩の部分にハンガー跡がついてしまったり、胸や袖の部分に余計なしわがついてしまったりすることがありますが、衣紋掛け(着物ハンガー)を使用することでそれらを防ぐことができます。
引っかける場所がないときは、屏風やハンガーラックタイプの衣桁(いこう)が便利です。着物の柄がよく見えるため、花嫁衣裳を展示するときや部屋の飾りとしても使われます。
衣紋道とは?
衣紋道とは、日本の装束を美しく整えて着装する技術や作法のことです。後三条天皇の孫の源有仁が創始し、鎌倉時代に確立された作法といわれ、即位の礼などの儀式や皇室行事などでも活用されています。
代表的な衣紋道の流派としては、山科家が受け継ぐ「山科流」と高倉家が受け継ぐ「高倉流」が挙げられるでしょう。一般的に「山科流」は見た目の美しさを追求した流派、「高倉流」は簡素かつ実働的な流派とされています。
衣紋を完成させる5つのコツ
着物を着るなら、時間が経っても美しい状態をキープしたいもの。次のコツを押さえておくと、着崩れしにくい「衣紋」を完成しやすくなるでしょう。
1. 半襟と襟芯を準備する
2. 背中心に合わせて長襦袢を着る
3. 抜き加減を調整する
4. 長襦袢に合わせて着物を羽織る
5. 補助アイテムを活用する
各コツを見ていきます。

1. 半襟と襟芯を準備する
長襦袢の襟元に「半襟(はんえり。半衿とも表記)」を付けましょう。半襟付けが緩いと着用時に襟元や衣紋部分が波々になり、美しく仕上がりません。襟全体にしわや弛みが生じないように細かく縫い付けてください。
次に「襟芯(えりしん。衿芯とも表記)」を選びましょう。襟芯が固すぎると首が痛くなりますが、柔らかすぎると襟元が崩れやすくなります。襟芯の種類は様々あるため、首の当たり具合やカーブの有無、襟幅を調べてから購入するとよいでしょう。
2. 背中心に合わせて長襦袢を着る
背中心(背骨)に合わせて、長襦袢を着ましょう。まずは長襦袢の背中心の縫い目が背骨の真上に来るように羽織り、両袖を通します。襟元を合わせてから、背中心を後方に引っ張って、首の後ろの付け根周りに空間を作りましょう。
鏡で後姿をチェックします。その際、左右対称になっていることと、首の後ろにこぶし1個分の空間があるか確認してください。問題なければ腰紐を胸の下で結び、襟元を固定させます。
3. 抜き加減を調整する
通常は襟元の後ろをこぶし1個分程度に抜きますが、季節やTPO、年齢によっても適切とされる抜き加減が異なるため注意が必要です。抜き過ぎたと思えるときは、指三本分程度に縮め、下品にならないように調整しましょう。
夏に浴衣や単衣を着るときは、やや深めに抜くと涼しげに見えます。反対に冬に袷(あわせ)を着用するときは、通常より狭くすると防寒効果も期待できるでしょう。
また、留袖や訪問着などをフォーマルな場で着用するときの抜き加減は深め、小紋や紬をおしゃれ着として楽しむときは浅めに抜いて粋に着こなしましょう。
一般的に若い方は深め、年配の方は狭めにすると年齢ごとのよさを引き立てるといわれています。体型によっても異なるため、ベストバランスを見付けてください。
4. 長襦袢に合わせて着物を羽織る
長襦袢で適切な抜き加減を決めた後で、いよいよ着物を羽織ります。整った衣紋を崩さないように、背中心から長襦袢に重ねるように着物を羽織りましょう。
襟元を合わせてから、長襦袢の襟後ろ部分に沿わせるように後方に引くと、衣紋が美しく整います。着物と長襦袢の襟部分が一体となるように、しわや弛みを作らないようにしてください。
5. 補助アイテムを活用する
衣紋抜きなどの補助アイテムを活用すると、美しい状態を長持ちさせられます。市販の衣紋抜きには長襦袢に後付けで縫い付けるタイプもありますが、強度や取り付け位置に不安のある場合は長襦袢を仕立てる際にあらかじめ衣紋抜きと紐付けを依頼するとよいでしょう。
また、襟元をキープするアイテムとしては、コーリンベルトもよく用いられます。襟元をクリップで留めて背中を抑えるため、お腹の前部分を締め付けることなく衣紋の着崩れを防ぎやすくなります。
美しく快適な着付けで和装を楽しもう
着物は成人式や卒業式だけに着用するものではありません。衣類の一つとして、普段の食事やお出かけの際に着用するのもよいでしょう。
抜き衣紋のコツがわかると、美しく快適な着付けができるようになります。着物を着こなして、おしゃれの幅を広げましょう。
監修:西村兄妹キモノ店/西村美寿穂
西村兄妹キモノ店 Webサイト https://www.kimonoten.jp
Instagram https://www.instagram.com/nishimura_kyoudai_kimonoten
メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock