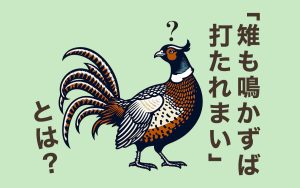目次Contents
普段は健康そのものという人が、めずらしく風邪をひいたとき。「鬼の霍乱だね」と言われることがあります。しかし、意味が把握できていなければ相槌すら打てませんよね…。
そこで本記事では、「鬼の霍乱」という言葉の意味や使い方、類語や英語表現まで紹介していきます。
「鬼の霍乱」とは? 意味をわかりやすく解説
まずは、「鬼の霍乱」の読み方と意味から確認していきましょう。
「鬼の霍乱」の読み方と意味は?
「鬼の霍乱」は、「おにのかくらん」と読みます。意味を辞書で確認しましょう。
鬼(おに)の霍乱(かくらん)
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
《「霍乱」は日射病のこと》ふだんきわめて健康な人が珍しく病気になることのたとえ。
「鬼の霍乱」とは、ふだんはとても丈夫で健康な人が、体調をくずすことを指します。

「鬼の霍乱」の「霍乱」とは?
「霍乱(かくらん)」とは、もともと日射病や暑気あたりのような、急に起こる体調不良を意味する言葉です。「鬼の霍乱」は、そんな「霍乱」によって鬼のように元気な人が体調を崩すという、少しユーモラスな表現だといえますね。
なお、同じ「かくらん」という読みでも、「撹乱」と書くのは誤りですので注意が必要です。「撹乱」は「かき乱すこと」や「混乱させること」を意味し、「鬼の霍乱」とはまったく異なる意味になります。漢字の違いに気をつけたいところです。
「鬼の霍乱」の使い方を具体的な例文とともに紹介
「鬼の霍乱」の意味を確認したところで、例文とともに具体的な使い方を確認していきましょう。
「いつも元気な彼女が風邪で寝込むなんて、まさに鬼の霍乱だね」
普段体調を崩さない人が、珍しく寝込んでしまった場面で使われています。

「部長が風邪で会議を欠席すると聞いて、同僚が“鬼の霍乱だな”とつぶやいた」
上司の体調不良に対し、驚きを込めて使われている例です。
「“鬼の霍乱ってやつかな”と言って、薬を手にした彼の姿が印象的だった」
自身の体調不良を「鬼の霍乱」と表している例です。
「鬼の霍乱」の類語や対義語を知る
似たような意味を持つ言葉や、反対の印象を与える言葉を知っておくと、表現の選び方に幅が出てきます。場面に応じた言い換えや対比ができると、言葉に対する理解もより深まりますよ。
類語・青菜に塩(あおなにしお)
青菜に塩をふりかけるとしおれてしまうことから、元気をなくしてぐったりしている様子を表すたとえです。見た目にも明らかに力が抜けている様子を描くときに使われます。
「鬼の霍乱」と同じく、いつもと違う弱々しい状態を表す表現として使われることがありますよ。

対義語・病上手に死に下手(やまいじょうずにしにべた)
「鬼の霍乱」のはっきりとした対義語ではありませんが、対照的な印象を持つ言葉として紹介しましょう。よく病気にかかる人は、かえって容易には死なないという意味を持っています。
「鬼の霍乱」は英語でどう表現する?
「鬼の霍乱」を英語で表現するなら、“an illness which suddenly affects a normally healthy person”がいいでしょう。「普段健康な人が突然体調を崩す」ことを意味する、慣用表現です。
参考:『プログレッシブ和英中辞典』(小学館)
最後に
「鬼の霍乱」という言葉は、健康でたくましい人がふいに弱さを見せたときに使われる表現です。意味を知っていれば、日常のちょっとした会話にも自然に取り入れられそうですね。
TOP画像/(c) Adobe Stock