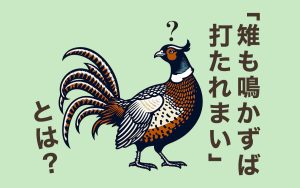「艱難、汝を玉にす」ということわざをご存じでしょうか? 現代ではあまり使われることはありませんが、意味や背景を知ると深い教訓が込められていることが分かります。
そこで、この記事では、この表現の意味や語源、さらには関連する言葉との違いについて詳しく解説していきましょう。
「艱難、汝を玉にす」とは? 意味と由来を解説
「艱難、汝を玉にす」ということわざは、何を意味するのでしょうか? 読み方と意味から確認していきましょう。
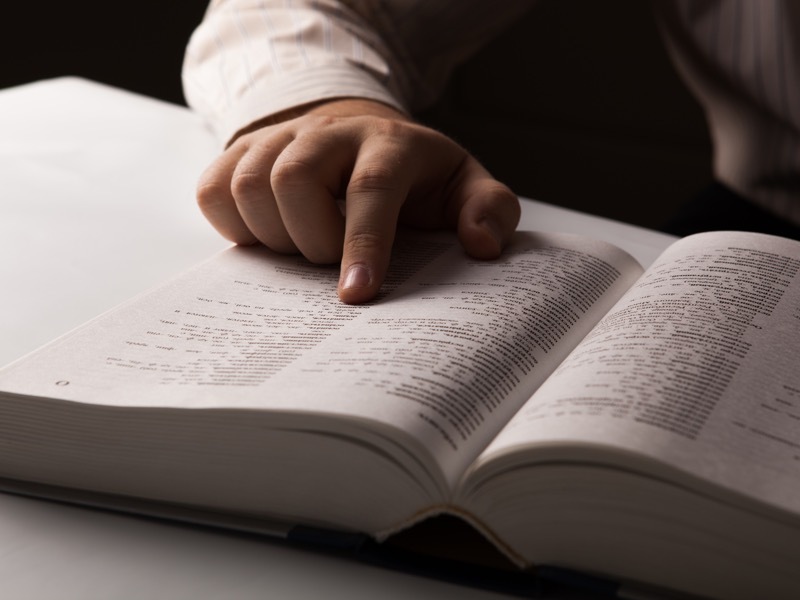
「艱難、汝を玉にす」の読み方と意味
「艱難、汝を玉にす」は、「かんなん、なんじをたまにす」と読みます。辞書で意味を確認しましょう。
艱難(かんなん)汝(なんじ)を玉(たま)にす
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
人間は苦労・困難を乗り越えることによってりっぱな人物になる。
「艱難、汝を玉にす」は、試練や苦労を重ねることで自分自身を磨き上げることを示唆しています。多くの人が経験する挫折や失敗も、見方を変えれば成長の機会と捉えられるでしょう。例えば、仕事での失敗を糧にスキルを高めるといった状況に適した言葉です。
現代では特に、人生の座右の銘として好まれるところがありますよ。
「艱難、汝を玉にす」の由来は?
「艱難、汝を玉にす」という表現は、漢文のように見えますが、実際には漢籍にその出典は確認されていません。むしろ、英語のことわざ“Adversity makes a man wise.”(逆境は人を賢くする)または、それと同じ意味を持つフランス語のことわざを翻訳したものと考えられています。
この言葉が日本で広まったのは、修身教科書による影響が大きいようです。特に、二宮金次郎や渡辺崋山の少年期のエピソードとともに紹介されることが多く、「人は、多くの困難を乗り越えて初めて人格を高めることができる」という教訓として広く理解されるようになりました。
また、「艱難、汝を玉にす」は国定教科書の第一期から第四期まで繰り返し取り上げられており、それによって日本社会に深く浸透したと考えられますよ。『辞苑』の初版にも「人は多くの艱難を経て、初めて人格を向上することができる」と説明されており、日本独自の捉え方が根付いたことがわかります。
参考:『故事俗信ことわざ大辞典』(小学館)

「艱難辛苦、汝を玉にす」とは?
よく検索される「艱難辛苦、汝を玉にす」という表現ですが、一般的な辞書には掲載されていません。「艱難、汝を玉にす」という表現を覚えておきたいですね。
「艱難、汝を玉にす」の類義語と関連表現
「艱難、汝を玉にす」ということわざは、人が困難や苦難を乗り越えることで成長し、立派な人物になることを意味します。この考え方に通じる類義語や関連表現を見ていきましょう。
玉磨かざれば光なし
「玉磨かざれば光なし」は、「どんなに美しい宝石でも磨かなければ輝かない」という意味です。この表現は、人間も素質だけでは不十分であり、努力や経験によって初めて本当の価値が引き出されるという教えを含んでいます。
特に、自分を磨き続けることの重要性を強調する場面で用いられることが多いでしょう。
若い時の苦労は買ってもせよ
「若い時の苦労は買ってもせよ」という言葉は、若い時期に積極的に苦労を引き受けることが将来の成功や成長につながるという考えを表しています。経験を積むことが大切であると教える言葉であり、特に自己成長を目指す若者に向けたアドバイスとして使われることが多いでしょう。

「艱難、汝を玉にす」の英語表現
「艱難、汝を玉にす」を英語で表現する場合は、先述した由来でもある“Adversity makes a man wise.”(逆境は人を賢くする)と表現するといいでしょう。
「艱難、汝を玉にす」とドラえもんとの関係
「艱難、汝を玉にす」という表現は、アニメ『ドラえもん』のエピソード「くろうみそ」に登場しました。この回で、のび太のパパはのび太に対し、「苦しみ、悩んでこそ、立派な人間になれる」という意味だと説明します。
『ドラえもん』では、子供たちにも理解しやすい形で深い教訓が伝えられていますよ。
最後に
「艱難、汝を玉にす」という言葉は、日常生活の中で試練を乗り越えることの重要性を教えてくれるものです。特に、困難を経験しながらも前向きに成長しようとする人にとっては、励ましの言葉となるでしょう。この表現を理解することで、自分自身を奮い立たせるきっかけにしてみてください。
TOP画像/(c) Adobe Stock