皆さんは、「虎の巻」という言葉を聞いたことはありませんか? 学生時代、受験の際などに使われるイメージがあるかと思いますが、実はビジネスの場面でも登場することがあるのです。本記事では、「虎の巻」の意味や使い方、よく似た「参考書」などの類語を解説します。
「虎の巻」の意味
「虎の巻(とらのまき)」とは、一体どんな意味なのか辞書でみてみましょう。
《中国、周時代の兵法書「六韜(りくとう)」の虎韜(ことう)の巻による語》
『デジタル大辞泉』(小学館)より引用
1 兵法の秘伝書。
2 芸道などの秘事・秘伝を記した書。
3 講義などの種本。また、教科書にある、問題の解答などが書いてある参考書。あんちょこ。とらかん。
このように、「虎の巻」には兵法の秘伝書や芸道の秘事など複数の意味があります。現代では、3番目の教科書の内容を解説した参考書、という意味として使われることがほとんどですね。略して「虎巻(とらかん)」と呼ぶこともあるようです。
語源
「虎の巻」の語源は、中国周時代の兵法書『六韜(りくとう)』にあるとされています。周の時代の政治家である、太公望(たいこうぼう)が著者とされ、『六韜』には文韜・武韜・竜韜・虎韜・豹韜・犬韜の6巻60編があります。その中で、戦場での戦術などの兵法が記されている「虎韜巻(ことうかん)」が略されて、「虎の巻」と呼ばれるようになった、という説が有力です。
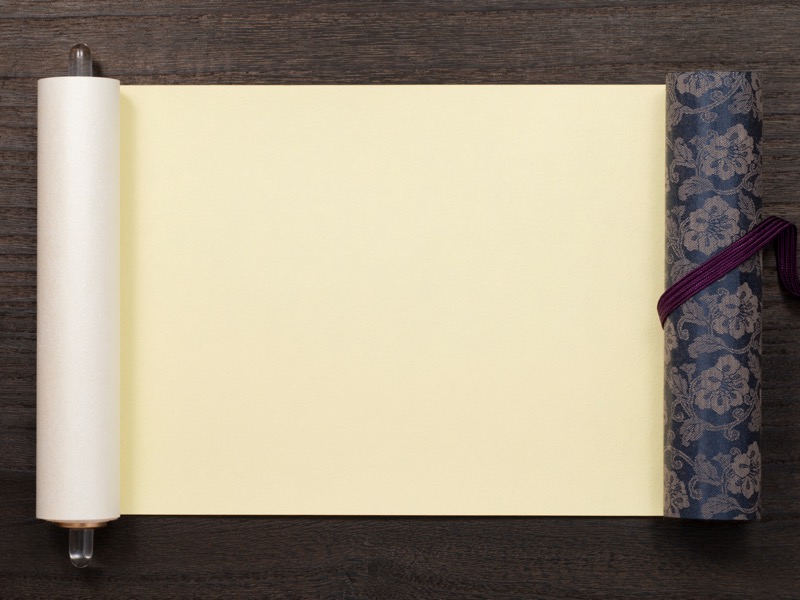
使い方を例文でチェック!
「虎の巻」がどんなシーンで使われるのか、一緒にチェックしていきましょう。
1:受験勉強をするために、数学の虎の巻を購入した。
「虎の巻」は、高校入試の参考書などに使われます。受験に出てくる傾向のある内容を網羅しており、「この一冊があれば安心!」というニュアンスで、用いられることも多いですね。宣伝文として「受験勉強の虎の巻!」などと言われることも。
2:先輩が、デキるビジネスマンになるための虎の巻を教えてくれた。
会社の先輩から、ビジネスにおける必要なマナーやスキルを記した本を教えてもらったということですね。特に入社したての頃は、目上の人への言葉遣いや取引先とのメールのやり取りなどわからないことも多いもの。そんな時に役に立つ本があると助かりますよね。
3:語学の堪能な友人から、英会話の虎の巻を教えてもらったおかげで上達しました。
英語で挨拶をする時のコツや、英語でコミュニケーションをとる際の秘訣などが書かれたものも、「虎の巻」と言えるでしょう。ある分野で成功するための秘訣が書かれた本や、入門書を読むことで、効率的に学習することができそうです。

類語や言い換え表現は?
「虎の巻」とよく似た意味を持つ言葉としては、「参考書」や「教本」、「あんちょこ」などが挙げられます。それぞれどのような内容が書かれた書物なのか、一緒に見ていきましょう。
1:参考書
学生時代から当たり前のように使っている「参考書」ですが、どんな書物だと言えるのか辞書で確認してみましょう。
調査・研究・教授・学習などの際に参考とする書物。「受験―」
『デジタル大辞泉』(小学館)より引用
ある物事を調べる際に、参考として用いる書物のことを「参考書」と呼びます。受験対策に使われる参考書や大学での研究内容が記載されている本はこれに当たりますね。学習内容をわかりやすく解説した本なので、専門的な知識を学びたい時に最適と言えそうです。
(例文)
・先輩から高校受験の参考書をもらった。
・参考書をいくつか調べてみたけど、載っていなかったよ。
2:教本
「教本(きょうほん)」の意味は以下の通りです。
1 宗教・道徳などの教えの根本。
『デジタル大辞泉』(小学館)より引用
2 教則本。教科書。「ギター―」
「教本」は、宗教の教えのおおもとを指す言葉である他に、文字通り「教えを記した教科書」という意味もあります。学校の教科書の他にも、ピアノの弾き方を解説した本や英会話のテクニックを記した本なども「教本」と言えますね。
(例文)
・先生はフランス語の教本をわたしにくれました。
・ビジネスマナーに関する教本を、入社前に何度も読みました。
3:あんちょこ
「あんちょこ」とは、いったいどんなものなのかチェックしてみると、
《「あんちょく(安直)」の音変化》教科書を予習するのに、いちいち調べたり考えたりせずにすむように作られた、手軽な参考書。虎(とら)の巻。
『デジタル大辞泉』(小学館)より引用
となります。教科書にある問題の解答や、英文の訳が書かれた解説書が「あんちょこ」と呼べますね。調べ物をする手間を省くための、簡単な参考書のことです。
中学生や高校生などが、友達同士のくだけた会話の中で使う傾向がありますが、現代ではあまり馴染みのない言葉になっていますね。
(例文)
・兄は苦手な数学のあんちょこを用意していた。
・彼はいちいちあんちょこを確認して、落ち着きがない。
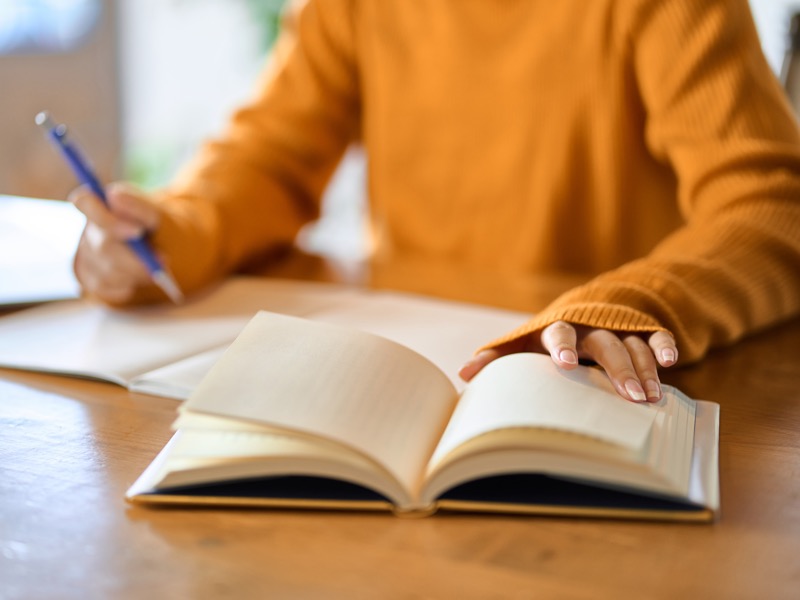
「虎」を使ったことわざ
「虎の巻」以外にも、動物の虎の文字が使われることわざがいろいろあります。例えば、「虎に翼」は、「元から強い力を持つ者に、さらに強い力が加わること」。「虎の子」は、大切にして手放せないもの」を指し、虎が子供を非常に可愛がる習性があることから生まれた言葉なのだとか。
また、「張子の虎(はりこのとら)」は、虎の形をした首の動く張子のおもちゃを指し、転じて虚勢を張る人をあざけっていう言葉となります。ポジティブな意味からネガティブな意味まで幅広く、ことわざの中で「虎」が使われているようですね。
最後に
「虎の巻」は中国の書物が由来となっていることから、兵法の秘伝書という意味から芸事の秘伝書、現代における勉強の参考書まで幅広く使われます。ビジネスシーンでは、働く上で必要なスキルが書かれた本などを示すこともありますので、会話の中でうまく活用できるといいですね。
TOP画像/(c) Adobe Stock























