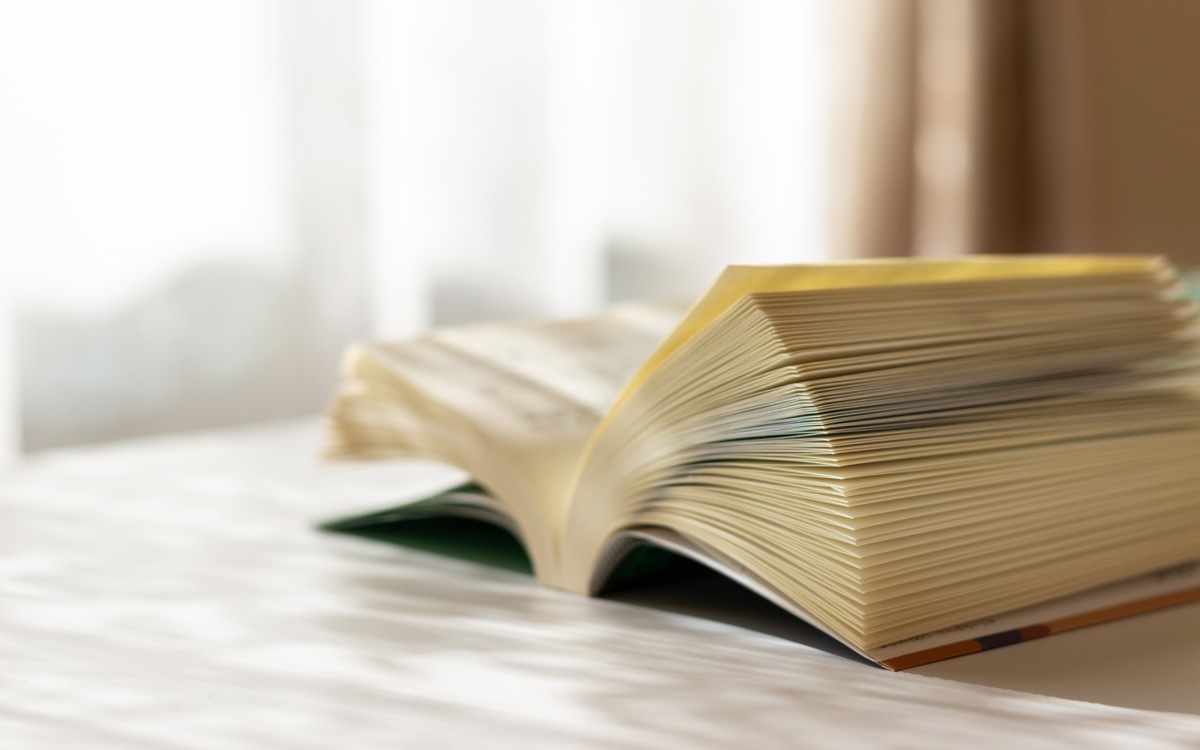目次Contents
この記事のサマリー
・「〜していただく」は、相手の行為を受ける自分をへりくだって表す謙譲語です。
・補助動詞として使う場合は「いただく」をひらがなで書くのが原則です。
・自分主体の行動に使うなどの誤用は避け、主体と恩恵の関係を意識しましょう。
「〜していただく」という表現は使う機会の多い言葉ですが、自分の立ち位置を正しく理解していないと、誤用しやすい言葉です。自分はしてもらう側なのか、してあげる側なのか、それとも「〜してくださる」という表現が適切なのか… 。まずは立ち位置の整理から始めましょう。
この記事では、「〜していただく」の意味や敬語としての位置づけ、似た表現との違いを整理しながら、迷わず使えるコツを紹介します。
確認しよう!「〜していただく」の正解|意味・敬語体系・表記
「〜していただく」という言葉を使うときには、自分の立場を理解することが必要です。まずは、自分の立ち位置を見極めながら、敬語としての位置づけや、似た表現との違いを整理していきましょう。
【謙譲語】「〜していただく」の意味と位置づけ
「〜していただく」は、自分が相手の行為から恩恵を受ける立場で使う謙譲語です。主語は自分側であり、相手を立てながら事実を述べる形になります。
具体的にいうと、「資料を送っていただく」は、相手がしてくれた行為を、自分の立場からへりくだって表していますよね。
辞書で補助動詞「いただく」について、記載を確認しましょう。
いただ・く【頂く/▽戴く】
引用(抜粋):『デジタル大辞泉』(小学館)
[動カ五(四)]
…
8 (補助動詞)
ア(動詞の連用形に接続助詞「て」を添えた形に付いて)話し手または動作の受け手にとって恩恵となる行為を他者から受ける意を表す。「これが先生にほめて―・いた作品です」「せっかく来て―・いたのですが、主人は今おりません」「一言声をかけて―・いたらよろしかったのに」
イ(接頭語「お」または「御(ご)」に動詞の連用形またはサ変動詞の語幹を添えた形に付いて)8㋐に同じ。「これから先生にお話し―・きます」「お読み―・きたい」「御心配―・きまして」「御審議―・きたい」
ウ(動詞の未然形に使役の助動詞「せる」「させる」の連用形、接続助詞「て」を添えた形に付いて)自己がある動作をするのを、他人に許してもらう意を表す。「させてもらう」の謙譲語。「あとで読ませて―・きます」「本日は休業させて―・きます」
…
辞書では、「話し手や動作の受け手にとって恩恵となる行為を他者から受ける意を表す」とされています。

【尊敬語】「〜してくださる」との違い
「〜していただく」とよく似た表現に「してくださる」があります。
「〜してくださる」は、相手を主語にして敬意を示す尊敬語です。主語は、相手や第三者であり、相手側の動作に敬意を払う形です。
例
「部長が説明してくださいました」
「先生がご指導くださいました」
一方の、「〜していただく」とは、先述したとおり、自分を主語にし、相手からの恩恵を受ける立場で使う謙譲語でしたね。
例
「私は、部長に説明していただきました」
「弊社が、先生にご指導いただきました」
ポイントは、主語の立ち位置が変わっている点です。
尊敬語「〜てくださる」…相手の行為を立てる。
謙譲語「〜ていただく」…相手の行為を受ける自分をへりくだる。
この違いを意識することで、場面に応じて適切な言い換えができますよ。
「〜していただく」の表記に注意
「〜していただく」は、ひらがな表記が原則です。
例:「ご確認いただく」「ご協力いただく」

「〜していただく」の使い方と例文
ここまで見てきたとおり、「〜していただく」は謙譲語です。フォーマルなやり取りで、相手への敬意と感謝を伝えることができるため、依頼・報告・お礼の場面で多く使いますよ。具体的な使い方を、例文とともに確かめましょう。
「〜していただく」の例文
例文
「ご協力いただいた皆さまのおかげで、無事に終了いたしました」
「お時間を割いてご説明いただき、助かりました」
「本日の会議にご参加いただき、誠にありがとうございます」
感謝の言葉を添えると、より温かいコミュニケーションになりますよ。
「〜していただく」のよくある誤用と注意点
「〜していただく」と「〜させていただく」は、主体が誰か、で使い分けます。この主体を取り違えると、文章全体がちぐはぐな印象になります。特に多いのは、以下の2パターンです。
自分が主体なのに「〜していただく」を使ってしまう
自分が行為の主体なのに、「〜していただく」を使うと、意味がねじれてしまいます。自分が行動する場合は「〜させていただく」が適切です。
誤:「私が発表していただきます」
(相手が発表してくれるような意味になってしまう)
正:「私が発表させていただきます」
(自分が発表する。ただし、相手の許可や配慮を受けて行うという意味になる)
相手が主体なのに「〜させていただく」を使ってしまう
相手が行動する場面で「〜させていただく」を使うと、自分が行為をするように聞こえてしまいます。相手主体の場合は「〜していただく」が正しい形です。
誤:「講師に資料をご説明させていただきます」
(説明するのは講師なのに、自分が説明するかのように聞こえる)
正:「講師に資料をご説明いただきます」
(講師が説明してくれる、その恩恵を受けるという意味になる)
「〜していただく」のポイントまとめ
・自分が動くとき → 「〜させていただく」
・相手が動くとき → 「〜していただく」
・補助動詞として使うときはひらがな表記
主体の立場を見誤ると、相手に違和感が生まれます。迷ったときは、「誰が動作をするのか」を確認しましょう。

「〜していただく」に関するFAQ
ここでは、「〜していただく」に関するよくある疑問と回答をまとめました。参考にしてください。
Q1. 「〜していただく」は敬語として正しいの?
A. はい。
相手が行った行為の恩恵を自分が受けることをへりくだって表す、正しい謙譲語です。
Q2. 「〜してくださる」との違いは何?
A. 「〜してくださる」は尊敬語で、「〜していただく」は謙譲語です。
主語の立ち位置が逆になります。
Q3. ビジネスメールでは漢字とひらがなのどちらを使う?
A. 補助動詞なので、ひらがなで書くのが原則です。
最後に
「〜していただく」は、相手への敬意と感謝を込めて、自分が恩恵を受けることを表す謙譲語です。「〜していただく」を正しく使うには、自分が「してもらう立場」か、「して差し上げる」立場かを見極めることが大切です。立場を理解して言葉を選べば、敬語の正確さだけでなく、相手に与える信頼感も大きく変わります。
特にビジネスシーンでは、正しい敬語の使い分けが信頼感につながりますよ。日頃から「主体は誰で、恩恵を受けているのは誰なのか」を意識して選び、誤解のない表現を身につけていきましょう。
TOP画像/(c)Adobe Stock