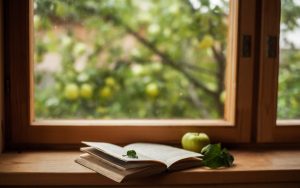目次Contents
お祝いの場やハレの日の着物で、「綸子」という名前を耳にしたことがあるかもしれません。着物が日常から離れている今でも、綸子はハレの日を彩る着物として愛されています。結婚式や成人式など、特別な日の装いにふさわしい光沢と、柔らかな手触りを持つ生地について、その特徴や歴史を見ていきましょう。
この記事では、「綸子」の読み方や意味を始め、生地の特徴、他の生地との違いなどを紹介します。
綸子とはどんな生地?
「綸子」という言葉について意味を理解するために、生地の特徴や背景を確認します。

綸子の読み方と意味
「綸子」は「りんず」と読みます。辞書でその意味を確認しましょう。
りん‐ず【×綸子/×綾子】
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
《「りん(綾)」「ず(子)」は唐音》滑らかで光沢がある絹織物。後練りの繻子(しゅす)織りの一種で、紋織りと無地とがある。染め生地として使用。
「綸子」は、絹を使った織物のひとつです。表面に光沢があり、なめらかな風合いが特徴とされています。
「りんず」という読み方は、「唐音(とうおん)」と呼ばれる中国伝来の読み方に由来しています。このことから、「綸子」が中国の織物文化の影響を受けて日本で作られるようになったことがわかります。
「綸子」はどんな織物?
綸子は、なめらかな光沢を持つ絹織物で、模様が織り込まれたものと無地のものがあります。染め加工を施す前の白生地として用いることが多く、着物の素材として重宝されています。
江戸初期に中国製の綸子を将軍家への献上品として用いた記録もあるほど、高級な織物とされていました。
参考:『世界大百科事典』(小学館)
繻子(しゅす)織りとの関係
綸子には、繻子織りという技法が使われています。これは、経糸や緯糸を一部だけ表面に浮かせて交差させることで、光沢を生む織り方です。なめらかで輝くような質感が特徴になっています。
ちなみに、「サテン」と呼ばれる洋服生地も、繻子織りを用いたものです。素材や工程は異なりますが、光を反射する艶やかな質感という点では共通しています。「サテンのような着物生地」と捉えると、綸子の質感が想像しやすくなりますね。
参考:『デジタル大辞泉』(小学館)、『世界大百科事典』(小学館)

綸子はどんな着物に使う?
ハレの日に身にまとう着物には、生地にも意味があります。綸子をどんな着物に使うのか紹介します。
綸子の着物はフォーマル向き
綸子は礼装用和服や帯地に用います。特に白無地の綸子は、白無垢として用い、婚礼衣装の素材として位置づけられています。
参考:『日本大百科全書』(小学館)
振袖に綸子は使える?
綸子は、その光沢のある質感から格式を求められる場面の着物にも用います。振袖に用いることも多く、成人式や婚礼など、特別な日に選ばれることが多い特徴があります。
参考:『日本大百科全書』(小学館)、『国史大辞典』(小学館)

綸子生地の特徴
艶やかな生地である綸子が持つ質感や、他の素材との違いを見ていきます。どんな特徴があるのか、知っておくと着物を選ぶ際に楽しみが増えるかもしれませんよ。
綸子の光沢と格式
綸子は、経糸・緯糸ともに撚りのない生糸を使用し、なめらかでやわらかく、光沢に富んだ風合いを特徴とします。その綸子の独自の美しさは、礼装に用いてきた背景から、格式の高い素材として位置づけられてきました
綸子の歴史
綸子は、慶長年間(1596-1615)に京都・西陣で中国の織技に倣って織り始めたと伝わっています。
慶長裂(けいちょうぎれ)や慶長小袖と呼ばれる衣装には綸子地のものが多く見られ、江戸初期には高級織物の代表格でした。1666年(寛文6)の衣服禁令では、一般の武士階級による綸子の着用が禁じられた記録もあり、その格式の高さがうかがえます。
当初は京都が主産地でしたが、江戸中期には群馬県桐生市でも製織されるようになりました。現在では、石川県小松市で生産される「小松綸子」が特に知られる他、京都府京丹後市や新潟県五泉市でも綸子の製織が続いています。
参考:『世界大百科事典』(平凡社)、『国史大辞典』(吉川弘文館)
繻子、緞子(どんす)との違い
緞子とは、繻子地を基本とした紋織物です。裏組織で文様を織り出す点に特徴があり、織る前に糸を染める「先染め」の技法で作ります。経糸と緯糸に異なる色糸を用いることで文様が明瞭に表れます。
綸子も同様に繻子織りの技法を用いますが、後染めが基本で、織り上げた白生地に後から染色を施す点が異なります。
さらに、綸子では「昼夜組織(ちゅうやそしき)」と呼ばれる織り方を用います。これは、布の表面には「表朱子(おもてしゅす)」、裏面には「裏朱子」という異なる織り方を組み合わせて、模様を浮き上がらせる技法です。これにより、綸子独特のやわらかく、光を受けて揺れるような文様が生まれます。
参考:『日本大百科事典』(小学館)、『世界大百科事典』(平凡社)
最後に
綸子は、光沢となめらかさを備えた絹織物で、礼装の場などにふさわしい素材です。繻子織りによる独特の風合いや、昼夜組織によって生み出される繊細な文様も綸子の魅力のひとつです。伝統的な織り方や歴史的背景をたどることで、見た目の美しさだけではない、着物文化の奥行きを感じ取ることができますね。
TOP画像/(c) Adobe Stock