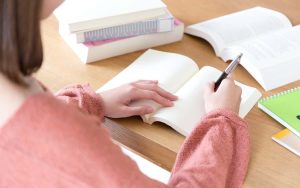目次Contents
この記事のサマリー
・「いたします」と「致します」は同じ意味ですが、基本はひらがな表記。
・丁寧すぎる敬語は、不自然に感じることもあるため注意が必要。
・「いたす」は「する」の謙譲語。
ビジネスの場面では、誠実さが求められる一方で、敬語を過剰に使いすぎる場面も増えていたりします。特に、「いたします」は定型表現として頻繁に使うからこそ、正しい使い方を知っておきたい語句の一つです。
この記事では、「いたします」と「致します」の意味の違いや、公用文での表記ルールを整理しつつ、「丁寧すぎて不自然ではないか?」といった現代的なモヤモヤにも触れていきます。形式にとらわれすぎず、伝わる敬語を一緒に確認していきましょう。
「いたす」の意味を確認
まずは「いたします」と「致します」の意味を確認したうえで、2つの表記の違いを整理しましょう。
「いたす」の意味を整理
「いたす」は「する」の謙譲語・丁寧語で、主に自分や自分側の行為をへりくだって述べるときに使います。例えば「ご報告いたします」や「確認いたします」などの形で使うのが一般的です。
辞書では以下のように定義されています。
いた・す【致す】
…
4
(ア)「する」の謙譲語。自己側の動作を低めて言ったり、改まった気持ちで言ったりすることで聞き手に対する敬意を表す。多く「いたします」の形で用いる。「努力を―・す所存です」「御指示どおりに―・します」「私から話を―・します」
(イ)「する」の丁寧語。多く「いたします」の形で用いる。「いい香りが―・します」「あと数分―・しますと重大発表が行われます」
…
6 (補助動詞)動詞の連用形やこれに「お」を付けた形、または、漢語サ変動詞の語幹やこれに「御(ご)」を付けた形などに付く。(ア)補助動詞「する」の謙譲語・丁寧語。多く「いたします」の形で用いる。「お静かにお願い―・します」「御一緒―・しましょう」
(イ)補助動詞「する」の尊大な言い方。「即刻、返答―・せ」
[補説]平安時代は、主として漢文訓読に用いられた。
…
一部引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
辞書に書かれた意味のうち、現代の敬語としてよく使うのは「する」の謙譲語・丁寧語にあたる用法と補助動詞です。「いたす」は主に敬語として使い、「いたします」の形で使います。
「いたします」と「致します」の使い分け方
「いたします」「致します」の意味は同じで、違うのは「表記」のみです。
漢字の「致します」は間違いなのか? という疑問について、結論からいえば、誤用ではありません。ただし、公用文や社内規程文などの正式文書、補助動詞では、ひらがな表記の「いたします」が推奨されているという点に注意が必要です。
これは、ひらがな表記が読みやすく親しみやすいためで、どちらを使うか迷った場合は、「いたします」を使えば無難です。一方の「致します」は、改まった印象を与える表現であり、文章全体をフォーマルに整えたい場面で使います。
例:
「ご報告いたします」
「来る◯月◯日、記念式典を開催致します」

「いたします」は丁寧? それとも堅すぎ?
ビジネスの場では丁寧な言葉遣いを意識するあまり、不必要な敬語を用いたり、形式的な表現ばかりになってしまったりすることがあります。ここでは、「いたします」の使い方を見直すヒントとして、「させていただきます」について注目してみましょう。
「いたします」と「させていただきます」はどう違う?
ここまで見てきたように、「いたします」は、自分側の行動を伝えるための正しい敬語です。
一方、「させていただきます」は、「許可や恩恵を受けてその行為を行う」意味を含んだ表現です。例えば、「発表させていただきます」は、「発表の機会をいただきました」という意味を含み、へりくだった気持ちを強く表します。
ただし、「させていただきます」を使うと、くどさを感じさせてしまうこともあります。相手に敬意を示しつつ、違和感を与えずに伝えたいときは、「発表いたします」を選ぶほうが、すっきりと伝わりますよ。

「いたします」の使用例|安心して使える文例をチェック
「いたします」は、ビジネスの場面で幅広く使える謙譲語・丁寧語です。ここでは、使用シーン別に文例を見ていきましょう。言い換え表現にも注目しながら、自分らしい敬語を見つけてみてください。
「ご依頼の件について、担当者よりご連絡いたします」
基本的な業務連絡でよく使う表現です。以下のような文も適切な使い方といえます。
例文:
「新しい資料を共有いたしますので、ご確認ください」
「会議の日程を再調整いたします。あらためてご連絡差し上げます」
「ご協力に心より感謝いたします」
これは、お礼を伝える場合の表現です。
「いたします」と「申し上げます」を場面に応じて使い分けるといいですね。以下は、お詫びの例です。
例文:
「不手際がありましたことをお詫びいたします」
「ご返信が遅くなりましたこと、ならびにご不便をおかけしましたことをお詫び申し上げます」
「ご不明点などございましたら、お問い合わせいただければ幸いです。対応いたします」
これは、ビジネスメールの結びや挨拶に多く使われる表現です。状況に応じて「いたします」と「申し上げます」を使い分けることで、丁寧さの度合いを調整できます。
例文:
「今後とも何卒よろしくお願いいたします」
「引き続き、よろしくお願い申し上げます」

「いたします」に関するFAQ
ここでは、「いたします」に関するよくある疑問と回答をまとめました。参考にしてください。
Q1. 「いたします」と「致します」、どちらを使えばいいですか?
A. 「いたします」とひらがなで書くのが一般的です。
どちらも意味は同じですが、ビジネス文書やメールでは、読みやすさ・親しみやすさを重視して、ひらがな表記が推奨されています。
Q2. 「いたします」と「させていただきます」はどう違いますか?
A. 「いたします」のほうが、より簡潔です。
「させていただきます」は、相手の許可や恩恵を受けて自分が行うことをへりくだって述べる表現です。
最後に
「いたします」は、ビジネスのさまざまな場面で使える敬語表現です。意味としては「致します」と同じで、ひらがな表記が基本とされています。
丁寧であることも大切ですが、相手にとって心地いい言葉を選ぶ意識を持ち、伝わる敬語を身につけていきたいですね。続けていくことで、信頼される大人のコミュニケーションへとつながることでしょう。
TOP画像/(c)Shutterstock.com