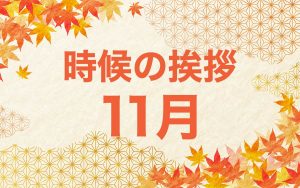目次Contents
「十三夜(じゅうさんや)」の意味や由来
みなさん、「十三夜」をご存じでしょうか? 広く知られているのは「十五夜」といえるでしょう。「中秋の名月」とも呼ばれ、おいしい月見団子を食べながら、秋の満月を鑑賞する「お月見」の風習があります。
実は「十五夜」の他にも「十三夜」と呼ばれる、日本独特の風習があるんです。ということで今回は「十三夜」について紹介します。秋の夜長に日本古来の素敵なお月見をしてみませんか?
まずは、「十三夜」の意味や由来についてみていきましょう。
「十三夜」の意味

十三夜とは、旧暦の9月13日の夜ことを指します。十五夜が中国伝来の風習とされるのに対し、十三夜は日本で始まった風習です。昔は、月の満ち欠けなどを用いて暦を計算する旧暦を用いていたため、人々の生活と月は密接につながっていました。
旧暦は、毎月新月から数え始めます。新月から数えておおよそ14日目~17日目が満月になりえます。十五夜は新月から数えて15日目なので満月、もしくは満月に近い月。十三夜は新月から数えて13日目なので、満月には少し欠ける月です。十三夜は、十五夜の次に美しいともされています。
じゅうさん‐や〔ジフサン‐〕【十三夜】
出典:小学館 デジタル大辞泉
1 陰暦13日の夜。
2 陰暦9月13日の夜。8月15日夜の十五夜に次いで月が美しいとされ、「後のちの月」という。十五夜の月を芋いも名月というのに対し、豆名月・栗名月ともいう。《季 秋》「泊る気でひとり来ませり―/蕪村」
▼あわせて読みたい
「十三夜」の由来は?
十三夜のお月見の起源については諸説あります。中でも、平安時代に醍醐天皇が月見の宴を催し、詩歌を楽しんだのが始まりではないかという説が代表的でしょう。また、平安時代後期の書物に「明月の宴」が催されたことが記され、宇多天皇が「今夜の名月は並ぶものがないほど優れている」という意味の詩を詠んだとの記述もあり、風習として親しまれていたことがうかがえます。
十五夜も十三夜も月見を楽しむことを大切にしており、八月十五夜の月見だけして九月十三夜の月を見ないことを「片月見(かたつきみ)」または「片見月(かたみつき)」と呼びます。片月見は縁起が悪く、災いが来ると忌み嫌われていました。ちなみに、陰暦八月十五夜の月と九月十三夜の月を合わせて「二夜の月(ふたよのつき)」と呼びます。

また、9月と10月の間に「閏9月」がある年には、十五夜と十三夜が2回訪れ、2回目は「後の十五夜」「後の十三夜」と呼ばれます。閏月(うるうづき・じゅんげつ)とは、月の満ち欠けによって決まる太陰暦の1年と太陽暦の1年との〝ずれ〟を補うために入れられる月のこと。ですから閏9月が入れられた年には、十五夜と十三夜を2回ずつ楽しむことができます。美しい月を愛でられる機会が多いのはうれしいですね。
さらに東日本を中心とした地域には、旧暦10月10日に十日夜(とおかんや)と呼ばれる行事がありますが、こちらはお月見というよりも収穫祭の意味合いが強いといえます。十日夜に見る月が、その年の収穫の終わりを告げるとされていました。十五夜と十三夜、十日夜がすべて晴天に恵まれると、縁起がいいともいわれているようです。
▼あわせて読みたい
2025年の「十三夜」は11月2日(日)
では、今年はいつ、お月見をしたらいいのでしょうか?
十三夜は、旧暦の日付で定められているため、毎年同じ日にやってくるとは限りません。2025年の十五夜は10月17日(火)、十三夜は11月2日(日)です。片月見とならないよう、両日ともお月見を楽しみたいですね。ちなみに十日夜は11月29日(土)です。
「十三夜」の別名は「豆名月・栗名月・後の月」
十三夜には、別の呼び方がありますので紹介します。この時期は、栗や豆が収穫できる時期であり、旬のものをお供えしてお月見をしたことから「豆名月(まめめいげつ)」「栗名月(くりめいげつ)」とも呼ばれます。十五夜の芋名月が、芋を収穫しお供えしたことから名づけられたのと同じですね。
また、十五夜に次いで美しく、十五夜の後に巡ってくるので、「後(のち)の月」とも呼ばれます。
「十三夜」もお団子を飾る? 並べ方や後の月見についても知ろう

十五夜の月見に対して、十三夜の月見を「後の月見」といいます。お月見では、秋の収穫に感謝するため、収穫物をお月様にお供えします。お供えしたものは、必ずおいしくいただきましょう。神様との結びつきが強くなると考えられています。
では「後の月見」には、具体的に何を準備すればよいのでしょうか? まずは、月見団子です。十三夜の場合は、13個のお団子を用意し、1段目に9個、2段目に4個並べます。月見団子は、お月様から見えるところか、もしくは床の間にお供えしましょう。合わせて収穫された旬の果物や野菜をお供えし、秋の実りに感謝します。たとえば、旬を迎える栗やブドウといった果物がおすすめです。「豆名月」の由来にもなっている枝豆、大豆をお供えするのもよいでしょう。
そして、収穫物とともにススキを飾ります。「ススキの鋭い切り口は、魔除けになる。茎の内部が空洞のため、神様の宿り場になる」と信じられていたそうで、古くから神様の依り代(よりしろ)と考えられていたとか。悪霊や災いなどから収穫物を守り、翌年の豊作を願う意味を込めて飾っていたようです。
▼あわせて読みたい
心地よい秋風とともに、お月見を楽しもう

今回は「十三夜」について解説しました。いかがでしたか? 古くから日本では、四季折々の自然を感じながら暮らしてきた文化や慣習があります。秋の澄んだ空気の中、きれいな月を見上げて、秋の実りに感謝するお月見。日々の忙しさに追われる現代ですが、時間を作ってゆっくりと月を見上げてみる。今年は、そんな心休まるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。
メイン・アイキャッチ画像/(c)Adobe Stock