目次Contents
お盆の期間はいつからいつまで? 地域によって違う?
お盆といえば、日本の夏にある大きな催事のひとつです。ご先祖さまや亡くなった家族がこの世へ戻ってくることのできる期間のことを指し、今でも変わらない慣習が全国各地にあります。

◆お盆の期間
日本の夏にある大きなイベント、「盂蘭盆会(うらぼんえ)」。つまり「お盆」のことですね。お盆といえば大型連休、というイメージの方も少なくないのではないでしょうか。
お盆とは、ご先祖さまや亡くなった家族をお迎えする期間のこと。お盆には家族やご先祖様の精霊(しょうりょう)をお迎えし、供養をする行事が行われます。
もともとお盆は太陽暦では7月15日を中心に行われていました。明治時代に旧暦から太陽暦に改暦されたことにより、日本の行事はおおよそひと月遅れになったようです。
◆新盆、月遅れ盆、旧盆
現在では、7月13日から7月15日にかけて行うことを「新盆」、8月13日から8月15日にかけて行うことを「月遅れ盆」、旧暦7月15日を中心に行うことを「旧盆」と分けて呼ぶ傾向も見られます。
「新盆」が適用されている地域は「東京都の一部」「南関東」「静岡旧市街地」「函館」など。「月遅れ盆」が適用されている地域は「南関東の一部」「西日本全般」「関東以北」、「旧盆」が適応されている地域は「沖縄地方」などです。
なぜこのような差があるのでしょうか? 改暦が行われた当時、日本国民の80%は農業をしていました。新暦の7月15日はちょうど農作業が多忙な時期であり、お盆の行事を執り行う余裕はあまりありません。そのため、1ヶ月遅れた8月15日にお盆の行事が執り行われるようになっていった、というわけ。これが「月遅れ盆」です。
都市部の多い新盆の地域では、農作業に合わせる必要がありません。そのため、旧暦の日付がそのまま新暦に反映された7月15日がお盆となるなど、明治時代の太陽暦への改暦による混乱と、実際の人々との生活とがさまざまな折り合いをつける形で、現在のようになったようです。
最近では、8月13日から8月16日の期間を「旧盆」と表現するケースも見られます。
◆お盆の由来
お盆の正式名称は「盂蘭盆会」です。この「盂蘭盆会」とは「盂蘭盆経」というお経が由来であるとされています。
この「盂蘭盆」の由来だとされているものは2つあります。1つは古代インドで使われていたサンスクリット語の「ウラバンナ」。意味は「逆さ吊りの苦しみ」。もう1つはペルシャ語で「霊魂」を意味する「ウラヴァン」が由来だとされています。何故これらの言葉が由来とされているのか。それは「盂蘭盆経」の元となるエピソードから来ているようです。
釈迦の弟子である目連は神通力により、亡き母が地獄で逆さ吊りの刑を受けていることを知ります。そんな母を救済できないかと考え、釈迦に教えを乞いました。すると釈迦は、「7月15日に多くの高僧を心から供養すれば、苦しみから救えるでしょう」と伝えます。目連がその教えを実行したところ、母は無事往生することができました。
これが盂蘭盆経の元となるとされているエピソードです。このお経が日本に伝わり、先祖の恩に感謝して墓参りや迎え火を行うようになりました。
お盆・2025年はいつからいつまで休み?

お盆休みは、新暦や旧暦により日にちが異なります。7月にお盆の行事が行われる新盆では、2025年は7月13日(日)から16日(水)がお盆期間です。また、月遅れ盆の期間は2025年8月13日(水)から16日(日) となります。
一般的にお盆休みは8月のお盆期間に重なる休暇ですが、2025年は祝日の「山の日」が8月11日月曜日で祝日のため、8月13日(水)~8月17日(日)のお盆休みに12日(火)を加えて、9連休を取得するというのも可能でしょう。
▼あわせて読みたい
お盆にすること…迎え火・送り火・精霊棚の設置など
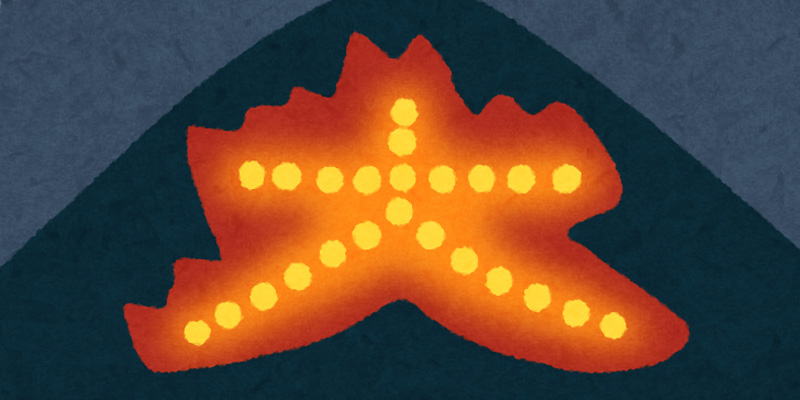
◆お盆にすること
先述したように、お盆の期間は亡くなった家族やご先祖様の精霊をお迎えし、供養することが一般的。そのため、お盆の期間には初日と最終日で行うことが異なります。
はじめに行うのが「精霊迎え」。この「精霊迎え」は、ご先祖様の霊魂が迷わずに帰ってくることができるように、お盆初日の夕方頃に玄関先で迎え火を焚く行為です。この火を目印に、精霊馬に乗ったご先祖様が返ってくると考えられています。
お盆最終日には、夕方頃にお盆の間一緒に過ごしたご先祖様の霊魂をお送りします。このことを「精霊送り」と呼び、「精霊迎え」と同様に火を焚いて見送ります。この「精霊送り」は各地で様々な行事が行われており「精霊流し」や京都の「五山の送り火」もその1つです。
また、宗教によっては迎え火や送り火を行わないところも。その場合は提灯が代わりの役目を果たすようです。賃貸など、火を焚くことが難しい住宅もこちらの方法で代用できるでしょう。
迎え火や送り火の他にも、お盆の時期には精霊棚を作り、お位牌を安置するという慣習もあります。通常の仏具に加え、精霊馬や精霊牛、季節の果物をお供えしましょう。
◆新盆(初盆)にすること
故人が亡くなられてから初めて迎えるお盆のことを、新盆や初盆と呼びます。この新盆の際は、普段のお盆と行うことがいくつか異なるため注意が必要です。
新盆では親族や友人などを招き、住職に読経をあげてもらい供養します。そのため、遅くとも1か月程前から準備を行う必要があるでしょう。
また、初盆では盆提灯を用意しますが、通常のお盆に使われる盆提灯は使いません。初盆の際は、白提灯を飾ります。飾り方も2つ1組で飾るのが一般的である盆提灯と異なり、白提灯は玄関先や軒先、仏壇の前などに1つだけ飾るのが通例です。
初盆が終わった後、この白提灯を供養する必要があります。この供養の方法としては、「燃やして処分をする」「菩提寺に供養してもらう」のいずれかが一般的です。読経の依頼をする際に、白提灯の処分方法を聞いておくとスムーズに行えますよ。
以上が、初盆と通常のお盆の大きな違いです。家庭や地域、宗教や宗派によって違いもあるため、そのやり方に従いましょう。
▼あわせて読みたい
お盆期間中のマナーとは? 海や植物など

お盆の期間は海に入ったら足を引っ張られてあの世に連れていかれる、などという考えから「お盆の期間には海に入ってはいけない」といわれています。お盆の期間は地獄に通じる釜の蓋が開き、帰る場所のない亡霊たちが海にさまよっているから、お盆の時期はクラゲが発生しやすいから、などさまざまな意見があるようです。
また、お盆の期間は「殺生禁止」とされています。釣りや虫捕りも避けた方がよいでしょう。その理由は、盂蘭盆経のエピソードから、飢餓で苦しんでいる方を救った日に殺生をしてはいけないという説が1つ。もう1つはご先祖様が虫の背中に乗って地上に帰ってくるため、虫を殺すとご先祖様が激怒する、という説です。
このようにお盆期間には、いくつかの言い伝えやマナーが存在します。ご先祖様を供養するためにも、こういった言い伝えは守るようにしたいですね。
▼あわせて読みたい
最後に

お盆について理解は深まりましたか? お盆期間は、亡くなった家族やご先祖様をお迎えする大切な期間。お盆期間には迎え入れる用意をして、亡くなった家族の話をするのもよいでしょう。思い出してもらえることが何よりの供養になるはずです。
TOP画/(c)Shutterstock.com


























