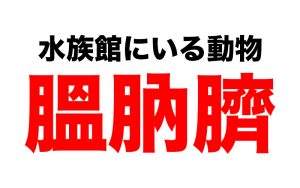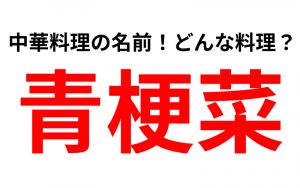「蟀谷」とは、顔のある部分を指す言葉ですが、すぐに読むことができるでしょうか? 意外と身近で、頻繁に見聞きする言葉ですが、漢字表記を見て戸惑う人は少なくないかもしれませんね。この記事では、ちょっと難しそうな「蟀谷」の意味や読み方を紹介していきます。
顔のどこの部分?「蟀谷」の読み方と意味を知る
まずは「蟀谷」の、基本となる読み方と意味を押さえておきましょう。

「蟀谷」の読み方と意味
「蟀谷」は「こめかみ」と読みます。辞書で、意味を確認してみましょう。
こめ‐かみ【顳=顬/蟀=谷】
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
《米噛(か)みの意》耳の上、目のわきの、物をかむと動く所。しょうじゅ。
「蟀谷」は、耳の上で目の横にあたる部分のことです。物を噛んだときに動く場所でもありますね。
辞書では「耳の上、目のわきの、物をかむと動く所」と説明されています。
「蟀谷」は「顳顬(しょうじゅ)」と呼ばれることもあります。日常的には「こめかみ」の方がよく知られていますね。
「蟀谷」という漢字の由来
「こめかみ」に「蟀谷」という漢字をあてるのは、あまり見慣れないかもしれません。ここでは、「蟀谷」という漢字の由来について見ていきます。
「蟀谷」は「米噛み」が語源
「蟀谷」という言葉の語源は、米を噛むと動くところから「米噛み」と呼ばれ、それが「こめかみ」という言い方につながったと考えられています。
参考:『日本国語大辞典』(小学館)

「蟀」という漢字の意味は?
「蟀」は、本来「こおろぎ」を表す漢字なんです。こおろぎは、別名「蟋蟀(しっしゅつ)」とも書きます。
参考:『新選漢和辞典Web版』(小学館)
「蟀谷」を使った例文と類語、英語表現を知る
身体の一部としての「こめかみ」は、日常会話の中でも登場しますね。ここでは、「蟀谷」を使った例文と類語、英語表現を紹介します。
例文:「蟀谷を押さえる」
頭痛を感じたとき、「蟀谷がズキズキする」と感じた経験がある人もいるかもしれませんね。「蟀谷」は、普段はあまり意識しない場所ですが、顔、頭に近いので、体調の変化が表れやすい部分でもあるようです。
また、実際に口を開けたり、食べ物を噛んだりすると、「蟀谷」が動くのを感じる人も多いでしょう。

例文:「怒ると、蟀谷に青筋が立つ」
この例文にある「青筋」とは、皮膚の下に見える青い血管のことです。「蟀谷」は皮膚が薄く、怒って血圧が上がると血管が浮き出やすい部分でもあります。
また、「怒ると、蟀谷に青筋が立つ」は、漫画やアニメでもよく描かれる表現です。怒りの感情が目に見える形でデフォルメされ、視覚的に伝わりやすくしているのです。現実の生理現象を元にした、感情表現のひとつといえるでしょう。
「蟀谷」の言い換え表現は「側頭」
「側頭(そくとう)」とは、頭の両側にあたる範囲を広い部分を指します。「蟀谷」は「側頭部」の一部にあたるといえるでしょう。
「蟀谷」の英語表現は“temple”
「蟀谷」は英語で“temple”と表現します。頭痛や脈打つような痛みを説明する際に使われることも多く、医療現場や日常会話の中でも使われますよ。
最後に
「蟀谷」は、漢字で表記すると難しく見えるかもしれませんが、意味はとても身近なものです。食事のときに動く部分として、また頭痛のときなどに意識される場所ですね。
辞書をひもといて言葉を見つめ直すと、見慣れた言葉にもあらたな理解が生まれてきます。これを機に、普段の会話や文章の中でも、ちょっと気に留めてみると、新たな発見があるかもしれません。
TOP画像/(c) Adobe Stock