間髪を容れずの「間髪」とは?
「間髪を容れずに〇〇をした」といった表現を目にしたことがある方は多いかもしれません。なんとなく「すぐに」「間をおかず」といったニュアンスであることはご存じでしょう。しかし、この「間髪」が何か知っていますか。
この章では「間髪を容れず」という表言葉の意味や「間髪」が何なのかを解説します。
「間髪を容れず」の意味
「間髪を容れず」とは、少しのゆとりもないことを表す言葉です。この「間髪」とは、文字通り「間(あいだ)の髪」のことです。つまり、間髪を容れずとは「間に髪の毛も入らない」という意味であり、これが転じて「少しのゆとり(余裕)もない」という意味で用いられています。また、そのような状態を指すこともあります。
間髪を容れず
出典:小学館 デジタル大辞泉
《「説苑ぜいえん」正諫から。あいだに髪の毛1本も入れる余地がない意》少しの時間も置かないさま。「質問に間髪を容れず答えた」
正しくは「間髪」で一語ではない?
「間髪をいれず」はもともと、間に髪の毛のひとすじを入れる余裕がないことから「即座に、とっさに」という意味を持つと解説しました。つまり正確な意味を考えると、「かん、はつをいれず」と間と髪の間を明確に区切って読むのが適切といえます。
しかしこれが次第に区切られずに読むようになり、「間髪」が一つの単語と誤解されるようになりました。この誤解から半濁音が加わり、「かんぱつ」という誤った読み方が一般的になったとされています。

「間髪」の語源・由来
「間髪を容れず」は、中国の古典文学に由来しているようです。そこには「間に髪をいれず」という表現が見られ、現代の「間髪をいれず」の語源となっています。
「間髪をいれず」は「間髪を入れず」とも表記されますが、由来を考えると「間髪を容れず」が正しいと考えられるでしょう。「いれず」とはすなわち「受け入れない、許さない」という意味で用いられており、何かが進行する際に隙間を与えないという意味を持ちます。
間髪を容れずの使い方
「間髪を容れず」を使う場合は、以下の例文を参考にしてください。
・彼は問題点を指摘するとすぐに次の提案に移り「間髪を容れず」議題を進めていった
・プレゼンテーションでは、彼女は一つの事例を説明し終えると、「間髪を容れず」に次のデータに移った
・議論中、彼らは意見を交わすと「間髪を容れず」に次のトピックに移り、スピーディーに議論を進めていった
間髪を容れずの類語・言い換え表現
間を置かず、すぐにという意味で用いられる言葉は、「間髪を容れず」の他にも複数の語句があります。ここでは「間髪を容れず」の類語として「すかさず」「間一髪」「咄嗟に」といった語句について解説。
「間髪を容れず」とあわせて類語や言い換え表現を覚えておくことで、効率的にボキャブラリー向上に臨めるでしょう。
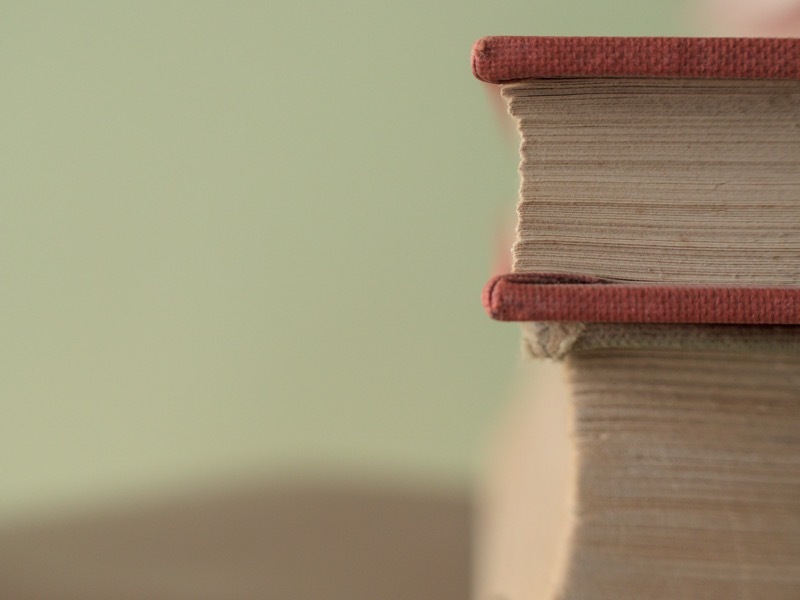
すかさず
「すかさず」は、漢字で表記すると「透かさず」です。この言葉は、すぐに、ためらうことなく行動することを意味します。「間をおかず直ちに」というニュアンスを持ち「間髪を容れず」と同じ意味で使われます。
間一髪
「間一髪」とは、物事の隙間や短い時間を示し、事態が切迫した状況を表現します。たとえば「事故を起こして炎上している車の中から、間一髪で脱した」というように使われる言葉です。この場合、飛行機が不時着し、燃料が引火する寸前に、わずかな時間の隙間を利用して脱出できたという緊迫した状況が伝わってきます。
咄嗟に
「咄嗟に」という言葉は「とっさに」という読み方をし、非常に短い時間を指します。たとえば「散歩中に突然飛んできたボールを咄嗟に避けた」というように使いますが、その短い時間の意味に加えて、反射的に行動するというニュアンスも含まれているといえるでしょう。
「髪」に関連する故事・ことわざ
「間髪を容れず」の他にも「髪」を使った故事やことわざは複数あります。本章では「髪結いの亭主」「一髪、二化粧、三衣装」「女の髪の毛には大象も繋がる」などを紹介。
昔から、髪=美の象徴のような意味をもつことが多いといえるでしょう。故事やことわざにおいて「髪」がどのような意味で用いられるものなのか確認しながらチェックしてみましょう。

髪結いの亭主
「髪結いの亭主」とは、妻の収入に頼って生活している夫を指します。このような夫は「甲斐性なし」「情夫」と揶揄されることがありますが、「髪結いの亭主」は比較的控えめな表現です。
「髪結い」とは髪を結う職業であり、その店を「髪結床(かみいどこ)」と呼びます。髪結いは比較的良い収入を得られるものであり、「髪結いの亭主」という表現が生まれたようです。
▼あわせて読みたい
一髪、二化粧、三衣装
「一髪、二化粧、三衣装」ということわざは、女性の美しさを高めるためのポイントを示した言葉です。最初に大切なのは髪の美しさ、次に化粧、そして最後に衣装とされている言葉といえます。これは古くから髪が美意識の象徴とされていたことを示しています。
女の髪の毛には大象も繋がる
「女の髪の毛には大象もつながる」ということわざは、女性の魅力が非常に強力であることを示しています。本来、髪の毛は非常に細くて脆弱なもの。しかし、ことわざでは大きな象をもつなぎ止めるほどの力を持っているとされています。象という大きな生物を用いて、女性の魅力が非常に強力であることを印象付けています。
「間髪」の由来を理解して、言葉を使いこなそう
「間髪」はそれ単体で用いられる言葉ではありません。基本的には「間髪を容れず」といった使い方をされます。そして、間髪を容れずとは少しの余裕もない様を表す言葉です。
この記事では「間髪を容れず」の意味だけでなく、類語や「髪」に関連する故事やことわざについても解説しました。まとめて覚えておき、一気に語彙力を向上させましょう。
メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock
























