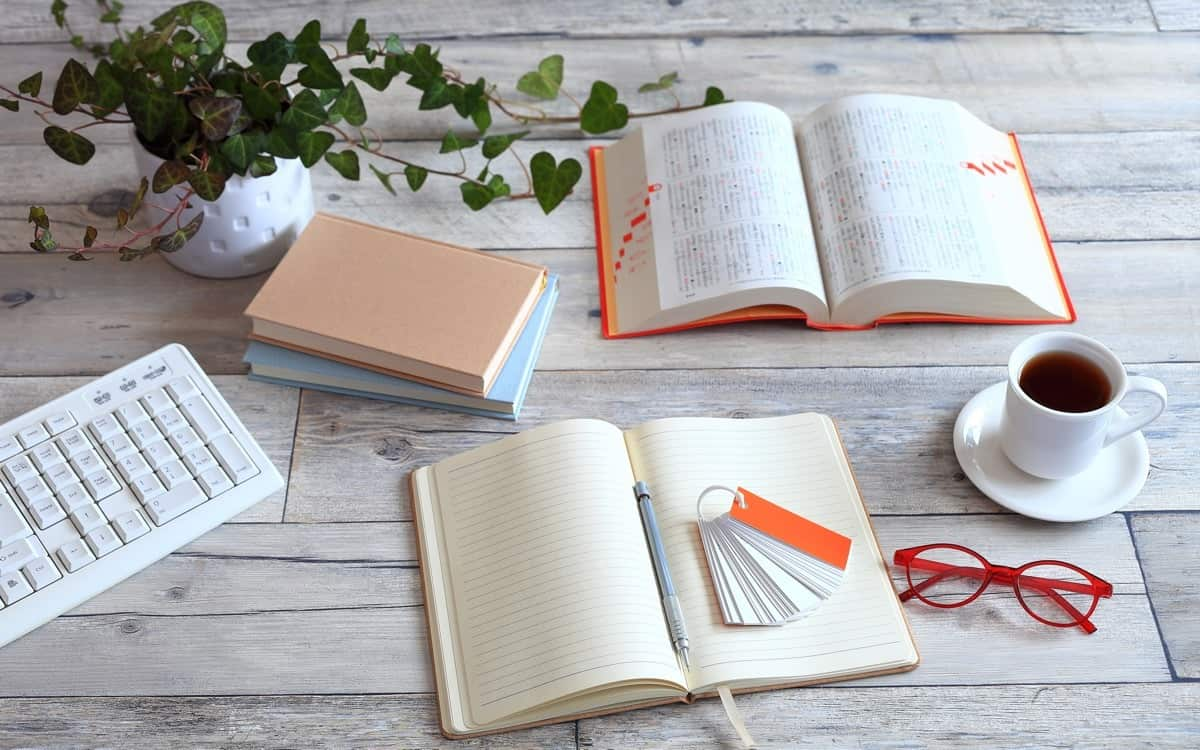「挙句の果て」とは? 基礎知識をまとめて解説
挙句の果てとは、「最後の最後には」などの意味がある言葉です。「あげくのはて」には、「挙句の果て」のほかに「挙げ句の果て」「揚げ句の果て」「揚句の果て」「あげくの果て」という複数の表記があります。
それでは、挙句の果てという言葉の詳しい意味や語源、「挙句」「果て」という単語のみの場合の意味を確認していきましょう。
挙句の果てとは「挙句」を強めた言い方
挙句の果ての意味は、「最後の最後には」「とどのつまり」「結局のところ」などです。「挙句」を強めた言い方で、「さまざまな手を尽くした末に、最終的にどうなったか」という結果を示す際に用いられます。
挙句の果ては、その結果があまり好ましくないものになった場合に多用される傾向にある表現です。また、悪い結果になるだろうと予想できる場合にも使用されます。
挙げ句の果て
出典:小学館 デジタル大辞泉
「挙げ句2」を強めた言い方。最後の最後には。とどのつまり。「口論が続き、挙—殴り合いのけんかになった」
挙句の果ての語源
挙句の果ての由来は、長連歌や短歌合作、俳諧(はいかい)などの連歌(れんが)から来ているとされています。
連歌とは、短歌の上の句(五・七・五)と下の句(七・七)を組み合わせて詠む、日本の伝統的な詩歌の形態のひとつです。一人または複数人が交互に句を詠み連ねるのが特徴です。
連歌では、最後の七・七の句のことを「挙句」と呼びます。歌の最後にあたる部分を指すことから転じて、「物事の最後」や「最終的な結果」を表すようになりました。その挙句という言葉に「果て」という言葉を加えて、さらに意味を強調したといわれています。

挙句という言葉の意味
あわせて、挙句自体の意味も確認しましょう。
挙句は、さまざまな意味があります。たとえば、連歌の場合は「最後の七・七音の句」を意味する表現です。また、「終わり」「結果」「末(すえ)」を表す場合もあります。
挙句を副詞のように用いる際は、「その結果として」「結局のところ」という意味です。いまでは、挙句の前に連体修飾語を置く使い方でよく使われています。
あげ‐く【挙(げ)句/揚(げ)句】
出典:小学館 デジタル大辞泉
1 連歌・連句の最後の七・七の句。→発句 (ほっく)
2 終わり。結果。末 (すえ) 。「苦労した—が失敗とは情けない」
3 (副詞的に用いて)結局のところ。その結果として。現在では、連体修飾語を上に付けて用いることが多い。「さんざん迷った—買ってしまった」
▼あわせて読みたい
「果て」という言葉の意味
果てという言葉にも、さまざまな意味があります。「果てること」「終わること」「物事の終わり」を指すこともあれば、「年月が経過したあとの状態」を表すケースも。
場所を表す場合には、「広い地域の極まるところ」や「もっとも端のところ」という意味です。さらに、「喪の終わり」を意味する際にも用いられ、「四十九日の終わる日」や「一周忌」を果てと表現することがあります。
なお、挙句の果てという表現の場合、果ては「結末」や「終わり」という意味です。
はて【果て】
出典:小学館 デジタル大辞泉
1 果てること。終わること。また、物事の終わり。しまい。限り。すえ。「—もない議論」「旅路の—」
2 年月を経過したあとの状態。「なれの—」「栄華の—」
3 広い地域の極まるところ。いちばん端の所。「地の—」「海の—」
4 喪の終わり。四十九日の終わる日。また、一周忌。
「御—も、やうやう近うなり侍りにけり」〈源・幻〉
挙句の果ての使い方・例文
挙句の果ての使い方を、実際に簡単な例文で確認しましょう。
・今日は用事があるため早く帰ろうと頑張っていたのに、新しい仕事を頼まれてしまった。挙句の果てに同僚がミスして、いつもよりも帰りが遅くなってしまいそうだ
・彼女のミスをいろいろとかばってあげたのに、まったく反省しない。挙句の果てには、私のことを嫌味な人だと陰口を言われていた
また、挙句の使い方は以下のとおりです。
・どの服を買うかさんざん迷った挙句、やっぱり今度また買いものに来ることにした
・リクエストに沿うものを作ろうと苦労した挙句、契約に至らなくてがっかりしてしまった

挙句の果てに関連する表現もチェック
あわせて、挙句の果てに関連する以下の表現も確認しておきましょう。
【挙句の果ての類語・言い換え表現】
とどのつまり・挙げ句・差し詰め・終(つい)に・つまるところ
【果ての類語・言い換え表現】
果(は)てし・限(かぎ)り・きり
【挙句の語源に関連する表現】
発句
それでは、これらの言葉の意味を解説します。
挙句の果ての類語・言い換え表現
「とどのつまり」
いきつくところ。結局。
「差し詰め」
直接かかわること。行き詰まってしまうこと。つまるところ。さしあたり。
「終(つい)に」
長い時間ののち、最終的にある結果に達するさま。ある状態が最後まで続くさま。とうとう。
「詰(つ)まるところ」
要するに。結局。
これらのうち、「とどのつまり」は挙句の果てと同じく、思わしくない結果になる場合に用いることが多いです。

果ての類語・言い換え表現
「果(は)てし」
際限。きり。終わり。
「限(かぎ)り」
時間・空間・数量・程度などの境や限界。ある範囲・制限の内にあること。〜である以上は。命が絶える時。葬式。だけ。さだめ。
「きり」
だけ。かぎり。ずっと〜している。〜を最後として。だけしか。
「果(は)てし」の「し」は強調する意味の副助詞です。基本的に、打ち消しの言葉とともに「果てしない」などの形で用います。
「限(かぎ)り」にはとくに多くの意味があります。果てという言葉の意味に含まれないものもあるため、言い換える際は注意しましょう。
挙句の語源に関連する表現
先述したとおり、挙句の語源は五・七・五・七・七を組み合わせて詠む連歌のうちの、最後の七・七音の句です。
一方、長連歌の始まりの五・七・五の17音からなる句のことは「発句(ほっく)」と呼ばれます。発句は、短歌の始めの5音や第1・2句、または五・七・五の17音が単独の短詩形として詠まれた俳句を指すこともあります。
また、連歌の最初の部分を指すことから、競り市で最初に提示される値の「初値」を意味することもあるようです。
挙句の果てを正しく使おう!
挙句の果ては「挙句」を強めた言い方で、「結局のところ」などを意味します。基本的に、あまり好ましくない結果となるようなニュアンスで用いられるケースが多いです。
類語・言い換え表現は、「とどのつまり」「挙げ句」「差し詰め」「終(つい)に」「つまるところ」などが挙げられます。
ぜひこの機会に言葉の意味・語源・使い方・言い換えできる表現などを確認して、正しく使えるようになりましょう。
メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock