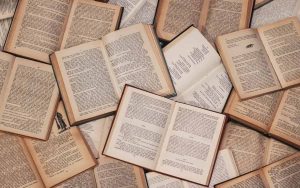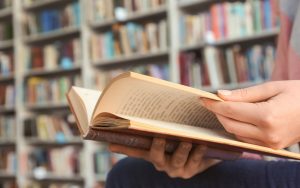目次Contents
「濫觴」という言葉は、あまり日常では見かけない表現かもしれません。ただ、歴史や文化を語る場面では、意外と使われる言葉です。言葉に込められた意味をたどりながら、「濫觴」がどのように使われているかを見ていきましょう。
「濫觴」とは? 読み方と意味をわかりやすく紹介
まずは「濫觴」の読み方と、意味を確認していきましょう。

「濫觴」の読み方と意味
「濫觴」は「らんしょう」と読みます。辞書で意味を確認しましょう。
らん‐しょう〔‐シヤウ〕【濫×觴】
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
《揚子江のような大河も源は觴(さかずき)を濫(うか)べるほどの細流にすぎないという「荀子」子道にみえる孔子の言葉から》物事の起こり。始まり。起源。「私(わたくし)小説の―と目される作品」
「濫觴」は、「流れの源」を指します。そこから転じて、「物事の起こり」や「起源」を表すようになりました。
「濫觴」はどんな場面で使われる?
「濫觴」は、歴史や制度、文化の流れなどを語るときに使われることが多い表現です。何かの活動や思想の起源に言及するとき、「濫觴」という語が選ばれることがあります。抽象的な場面にもなじみやすく、文章に落ち着いた印象を与える語です。
「濫觴」の語源は?
この言葉の由来は、中国の古典『荀子(じゅんし)‐子道』や『孔子家語(こうしけご)‐三恕』に見られます。孔子が弟子の子路(しろ)を戒めた言葉「昔者江出於岷山、其始出也、其源可以濫觴」が語源です。
「濫」は“浮かべる”という意味を持ち、「觴」は“さかずき”を指します。つまり、「さかずきを浮かべられるほどの小さな流れ」が物事の始まりとしてたとえられた表現です。そこから転じて、今では「起源」や「発端」を表す言葉として用いられています。
参考:『故事俗信ことわざ大辞典』(小学館)
「濫觴」の使い方を具体的な例文で確認
「濫觴」という言葉は、文脈によって印象が少しずつ変わります。実際の使い方を見ることで、その表現が持つ雰囲気や距離感がつかみやすくなりますよ。ここでは代表的な例を紹介していきます。
「この取り組みは、わが社におけるSDGsの濫觴となった」
企業が新たな価値観や方向性を意識し始めた、その起源を表す表現です。語調に落ち着きがあり、社内報やビジネス文書でも使いやすい言い回しです。

「その文学運動の濫觴は、明治末期にまでさかのぼる」
文学の流れや時代背景を語るとき、その始まりを静かに示す言葉として使われます。論文や解説文などで、出来事の位置づけを丁寧に伝えたい場面などに向いています。
「文明の濫觴は、メソポタミアにあるともいわれる」
壮大なテーマを扱うときでも、「濫觴」という言葉には適度な抽象性があります。歴史や文化の起源について、視野を広げながら言及したいときに自然に馴染む表現です。
「濫觴」の類語・言い換え表現を紹介
「濫觴」という言葉は少し硬さを感じる表現でもあるため、文脈に応じて言い換えることで、伝わりやすさや印象が変わることもあります。ここでは、似た意味を持つ言葉を紹介していきましょう。
嚆矢(こうし)
「物事の始まり」や「最初の出来事」を表す言葉です。「濫觴」と同じく、由緒ある表現として文語的な文章に使われることがあります。歴史や制度の変化に触れる場面でも見かけますよ。
起源(きげん)
物事がどこから始まったかを示す、一般的でなじみやすい言い回しです。「濫觴」よりもやわらかく、説明的な文脈にも向いています。
始まり
「起源」より、さらに日常的な言葉です。「物事の起こり」を伝えるのに、一番平易な言葉だといえるでしょう。
『濫觴生命』とは? 曲をきっかけに広がった言葉の関心
『濫觴生命』は、Orangestarさんが制作し、VOCALOIDのIAが歌唱する楽曲です。この曲のタイトルにより、「濫觴」という言葉への関心が高まりました。
楽曲『濫觴生命』の歌詞には、新たな感情の始まりや、個人の物語の出発点を連想させるような文脈が出てきていますよ。

英語で「濫觴」はどう表す?
「濫觴」は、文学的な響きを持つ日本語表現のため、ぴったり一致する英訳を見つけるのはやや難しいかもしれません。ただし、意味に近い言葉を文脈に応じて使い分けることで、ニュアンスを伝えることは可能です。
the origin
「起源」「発端」といった意味を持つ表現で、「濫觴」の基本的な意味を最もシンプルにカバーします。制度や歴史の話題、研究の背景を説明するときによく使われる単語です。
the beginning
より日常的な響きのある言葉で、「始まり」「出発点」を意味します。抽象的な話題や感情の流れ、物語の導入などにもなじみやすいでしょう。
最後に
「濫觴」という言葉は、使い慣れないからこそ、丁寧に選んで使いたい表現かもしれません。始まりというテーマを少し距離をもって見つめたいとき、落ち着いた語調で伝えたいときに、この言葉はそっと寄り添ってくれるように感じます。言葉の奥にある感覚に触れてみると、自分の表現の世界も少し広がるかもしれませんね。
TOP画像/(c) Adobe Stock