「口伝」という言葉は、古風な響きを持ちながらも、今なお使われている表現です。歴史的な文脈で見かけることが多く、知っているようでいて、曖昧なままになっている人も多いかもしれません。
この記事では、「口伝」の読み方や意味、使い方や言い換え表現を丁寧に紐解いていきます。
「口伝」とは? 意味と読み方を整理
まずは、「口伝」の読み方と意味を確認していきましょう。
口伝の読み方は「くでん」と「くちづて」
「口伝」と書いて「くでん」と読む場合と、「くちづて」と読む場合があります。「くちづて」と読む場合は、人から人へと言い伝えることを意味しますよ。

口伝(くでん)の意味|言葉や知識を口頭で伝えること
「口伝(くでん)」という言葉には、いくつかの意味があります。辞書では次のように説明されています。
く‐でん【口伝】
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
1 言葉で伝えること。くちづたえ。
2 師が、学問や技芸の奥義などを弟子に口で伝えて教え授けること。また、その教え。口授(くじゅ)。口訣(くけつ)。
3 奥義を伝えた文書や書物。秘伝書。
つまり「口伝」とは、文字にせず、言葉だけで物事を伝える行為を意味します。日常的な会話や情報のやりとりにとどまらず、師から弟子へと受け継がれるような技術や知恵、時には秘伝書のような文書を含むこともあります。
形式に残らない伝え方だからこそ、その場にいた人だけが受け取る重みがありますね。
「口伝」の使い方を具体的な例文とともに確認
「口伝」という言葉には少し古風な印象がありますが、意味を理解し、場面に合わせて使えるようになると表現の幅が広がります。ここでは、代表的な使い方を例文とともに紹介していきましょう。
「この舞の細かな動きは、口伝でしか伝わってこなかったそうです」
伝統芸能の世界では、細かな所作や間の取り方などが文字では記録されず、師匠から弟子へと語り継がれることがあります。そうした状況を表していますよ。
「この土地に伝わる昔話は、長年口伝で広まってきたものです」
この例文では、この地域に残る昔話が記録されることなく、話し言葉で代々受け継がれてきたことを表しています。
「口伝の情報だけでは曖昧な部分が多く、記録との照合が必要でした」
言葉だけで伝えられてきた知識には、細部がはっきりしないこともあるでしょう。この例文では、書き記された情報と照らし合わせて確認する必要が出てきた場面を説明しています。
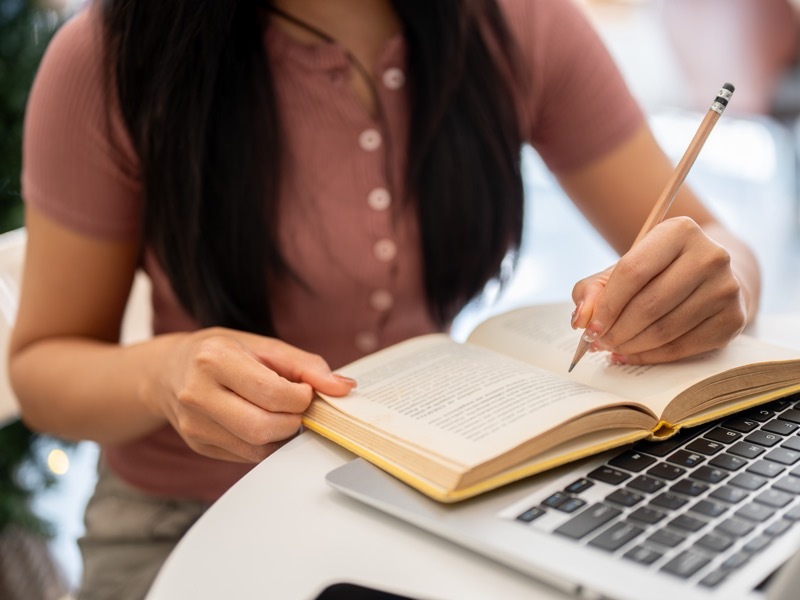
「口伝」の類語や言い換え表現を紹介
「口伝」という言葉は、場合によってはややかたく聞こえることもあります。より一般的な言い回しに言い換えると、伝えたいニュアンスが自然に届くでしょう。ここでは、「口伝」の類語を4つ紹介します。
口伝え(くちづたえ)
口頭で人から人へ情報を伝えることを意味します。日常的なやりとりでも使いやすく、比較的カジュアルな印象があります。
口承(こうしょう)
物語や教えなどを、文字ではなく口頭で語り伝えていくことを指します。伝統文化や民話の世界で使われることが多い言葉です。
語り継ぐ
人から人へ、そして世代から世代へ、次々と語って伝えていくことを意味します。主に歴史や物語、体験などを、世代を越えて伝える際に用いられますよ。
口頭伝承(こうとうでんしょう)
書き記されることなく、語りのかたちで継承されていく文化や知識の伝え方です。民間伝承や神話などがその一例です。言葉によって受け渡されるという特性から、表現や内容が変化することもあります。学術的には、文字のない社会に限らず、文化や記憶の伝達手段として研究対象になることもあります。

「口伝」の英語表現は?
「口伝」という言葉を英語に置き換える場合は、伝えたい内容によって表現を使い分けるのがよさそうです。伝統的な語りなのか、技術や知識の伝授なのかで、適した英単語が変わってきます。
oral traditions
“oral traditions”は、昔から人の口によって語り継がれてきた伝承や物語を表す表現です。民話や神話、歴史的な言い伝えなどを指す際に使われます。
oral instruction
“oral instruction”は、口頭で教えを与えることを意味します。技術や知識を直接言葉で伝えるような場面に適しています。教育や訓練の現場などでも使われることがありますよ。
最後に
「口伝」という言葉には、ただ情報を伝える以上のぬくもりがあるように感じられます。文字になっていないからこそ、そこには人の思いや声の調子、そのときの空気までもが含まれているのかもしれません。なぜ言葉で伝えるのか。その理由に思いを巡らせてみると、言葉の奥にある人と人とのつながりが見えてくるかもしれませんね。
TOP画像/(c) Adobe Stock























