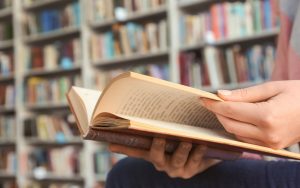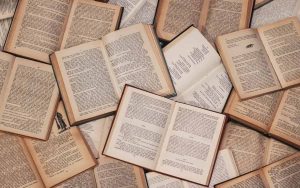目次Contents
「尽未来際(じんみらいさい)」という言葉には、どこか壮大で静かな響きがありますね。聞いたことはあっても、その意味や背景まで知っている人は少ないかもしれません。この表現は仏教に由来しており、「時間」という普遍的な概念に関連する言葉です。
少しだけ足を止めて、その深い世界をのぞいてみませんか?
仏教の教えで使われる「尽未来際」とは?
仏教語としての「尽未来際」には、時間の果てをイメージするような意味が込められています。読み方と意味を見ていきましょう。

読み方と意味
「尽未来際」は「じんみらいさい」と読みます。辞書で意味を確認してみましょう。
じんみらい‐さい【尽未来際】
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
《「じんみらいざい」とも》仏語。未来の果てに至るまで。未来永劫(えいごう)。永遠。
辞書には「未来の果てに至るまで 」といった意味が記されています。つまり、「未来永劫」、「永遠」を指す言葉です。
気になる使い方と例文
「尽未来際」という言葉は、日常会話ではあまり耳にしないかもしれませんね。でも、どのような場面で使われるのかを知っておくと、「尽未来際」の持つ意味がすっと頭に入ってくるかもしれませんよ。

「この誓いは、尽未来際にわたって守られるべきものです」
このような使い方は、儀式や式辞、仏教に関する文章などでよく見られます。「尽未来際」は、「永遠に」や「終わりなく続く時間」を表す言葉として使われており、信仰や祈りが、一瞬の行為や短期的な願いにとどまらないことを示しています。
言葉に重みがあるため、普段づかいにはやや堅く感じられるかもしれません。大切な誓いや変わらぬ思いを表したいときには、心の奥に残る言葉として使える場面があるかもしれませんね。
「恩師への感謝の念は、尽未来際にわたって忘れることはないだろう」
この例文は、恩師に対する深い感謝の気持ちが、どれほど時間が経っても決して消えることはないという強い想いを表現しています。「一生忘れない」と言うよりも、大きなスケールを感じさせますね。
この表現は、人生に大きな影響を与えた人物などに対する敬意や感謝を、荘厳で厳かな語調で伝えたいときに適しています。

「弟子某甲(でしむこう) 尽未来際」
仏教の儀式や文書の中で見かける表現に、「弟子某甲 尽未来際」があります。
これは、仏法に帰依する誓いを立てる場面などで使われる言い回しです。修行者が仏に対して、永遠に変わらぬ意思を持って信仰を貫くことを誓うときに用いられます。
ここでの「弟子」とは、仏弟子を意味します。釈尊の死後、その教えを受け継ぐ者たち、またそれを名乗る者をも含むようになりました。
続く「某甲(むこう)」という言葉は、「だれそれ」「なにがし」といった意味で、特定の個人名を挙げずに記述するときに使われます。あえて特定の名前を伏せることで、形式や象徴性を重んじる儀礼的な文脈にふさわしい表現となっています。
定型的な表現に見えるかもしれませんが、その中には「時間の流れによって揺らがない覚悟」や、「尽きることのない祈りの気持ち」が込められています。
参考:『日本国語大辞典』(小学館)、『例文仏教語大辞典』(小学館)
最後に
「尽未来際」という表現には、仏教がとらえる「永遠」の感覚が息づいています。時間は、人それぞれの経験や心の状態によって、長くも短くも感じられるものですよね。だからこそ、「尽未来際」という言葉は、限りなく続く未来を思い描くための手がかりになるかもしれません。
果ての見えない時間を思うとき、この言葉が気持ちを静かに整えてくれることもあるのではないでしょうか。
TOP画像/(c) Adobe Stock