目次Contents
時間がたっても、どちらも折れずに言い分をぶつけあうような出来事は、誰しもどこかで見たことがあるでしょう。そんなとき、「喧嘩両成敗」という言葉を思い出す人もいるかもしれません。
この記事では、「喧嘩両成敗」の意味や起源、今の社会に与える印象などをたどってみましょう。
喧嘩両成敗とは? 読み方と意味をひもとく
まずは「喧嘩両成敗」の読み方と意味から確認していきましょう。
喧嘩両成敗の読み方と意味
「喧嘩両成敗」は、「けんかりょうせいばい」と読みます。辞書で意味を確認しましょう。
けんか‐りょうせいばい〔ケンクワリヤウセイバイ〕【×喧×嘩両成敗】
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
けんかや争いをした者を、理非を問わないで双方とも処罰すること。戦国時代の分国法にみられ、江戸時代にも慣習法として残っていた。
「喧嘩両成敗」とは、喧嘩の当事者がどちらか一方に責任があるとは限らないとして、両方を同じように処罰する、という立場を表す言葉です。必ずしも道徳的な是非を問うものではなく、争いそのものを問題視するという点に特徴があります。

「喧嘩両成敗」の歴史的背景とは?
「喧嘩両成敗」の考え方を、実際に制度として運用した時代がありました。争いが絶えなかった戦国の世において、治安を保つための手段だったとも考えられます。ここでは、歴史の中での「喧嘩両成敗」について触れていきましょう。
「喧嘩両成敗」の始まり
「喧嘩両成敗」という考え方は、中世から近世にかけて広まった法の一節に由来するといわれています。最も古い例のひとつとして、文安2年(1445)に出された藤原伊勢守の高札に「喧嘩口論堅被停止訖、有違背族者、不謂理非、双方可為斬罪」という記述が見られます。
当時の「喧嘩」は、主に武力による争いを意味しており、一方が攻撃しない場合には「喧嘩」として扱われないのが一般的だったようです。その後、この概念は時代とともに広がりを見せ、単なる武力闘争だけでなく、対立や口論など広範な争いごとに適用されるようになりました。
現在では、子ども同士のけんかや日常的な言い争いに対しても、「喧嘩両成敗」という言葉が用いられることがありますね。もともとの背景をたどることで、この表現が持つ重みや、時代による解釈の変化に気づくきっかけになるかもしれません。
参考:『故事俗信ことわざ大辞典』(小学館)
『甲州法度之次第』と「喧嘩両成敗」の関係
「喧嘩両成敗」という考え方が明文化された例のひとつに、『甲州法度之次第(こうしゅうはっとのしだい)』があります。これは、戦国時代の甲斐国(現在の山梨県)で武田信玄が制定した法典で、武士の統治や秩序維持を目的として定められたものです。
この中には、「喧嘩両成敗法」があり、まさに「喧嘩両成敗」の原型ともいえる内容が記されています。
参考:『世界大百科事典』(平凡社)
武田信玄が採用した背景とは
武田信玄が「喧嘩両成敗」の方針を取り入れた背景には、武士たちの私的な争いを抑え、領内の統治を安定させたいという意図があったと考えられています。武力や報復によって個々の正当性を主張することよりも、全体の秩序を優先することが重要とされていた時代です。
一見すると公平性に欠けるようにも見えるかもしれませんが、「誰が正しいか」を超えて、「争いを起こすこと自体が望ましくない」という価値観を浸透させるための方策であったとも受け取れます。信玄の支配下では、こうしたルールが武士社会の安定に一定の効果をもたらしたと考えられますよ。
「喧嘩両成敗」が「理不尽」と言われるのはなぜ? 現代人が感じる違和感
「喧嘩両成敗」はどちらにも責任があるという前提がありますが、現代の価値観ではその考え方に違和感を覚えることもあるようです。ここでは、そのギャップについて見ていきましょう。
「喧嘩両成敗」は理不尽?
今の社会では、それぞれの立場や状況に耳を傾ける姿勢が大切にされています。一方的に「両方に責任がある」と結論づけられると、事情を無視されたように感じる人もいるかもしれません。そのため、「喧嘩両成敗」という考え方に対し、理不尽さを覚える声があるのも自然なことです。

現代に、この考え方は合っているのか
背景や経緯に目を向ける風潮が広がるなかで、一律に処分を下すという考え方は、やや古風に映る場面もあります。
「喧嘩をした」という事実だけを見て判断するより、そこに至るまでの経緯や感情をくみ取ることが求められる時代ともいえるでしょう。「喧嘩両成敗」に対する印象も、時代の流れとともに変わりつつあるのかもしれません。
今に残る「喧嘩両成敗」的な考え方
「喧嘩両成敗」という考え方は、すでに法制度としては姿を消しています。ただし、現代のさまざまな場面で、それに似た対応が見られることがあります。表面的な公平さを重視した処理の仕方に、その名残が感じられるのかもしれません。
企業のクレーム対応と「両成敗」的な処理
例えば、接客トラブルなどで顧客と従業員の間に摩擦が生じた際、双方の主張に深く踏み込まず、「どちらにも至らぬ点があった」として等しく注意を促すケースがあります。
その背景には、対立を長引かせず、場を収めたいという配慮があるのかもしれません。けれども当事者にとっては、不完全燃焼のまま終わる対応と映ることもあるようです。
SNSトラブルに見る“どちらも悪い”という反応
ネット上の議論が白熱すると、第三者のコメントで「どっちもどっち」といった言葉が見られることがあります。これもまた、「喧嘩両成敗」的な発想に通じるものといえそうです。
深く背景を知るわけでもなく、争っている両者に対して同じように距離を取るような態度が、今の時代にも残っているのかもしれません。
英語ではどう表現される?
「喧嘩両成敗」にぴったり当てはまる英語表現は少ないかもしれませんが、似たようなニュアンスを持つ言い回しはいくつか存在します。ここでは、そのうちの2つをご紹介します。
“In a quarrel, both parties are to blame.”
「喧嘩においては、両者ともに責任がある」という意味です。特定の誰かを一方的に責めるのではなく、状況の中で互いに非があると見る姿勢が込められています。
道徳的あるいは社会的な教訓として使われることが多いでしょう。
“A plague both on your houses”
この表現は、シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』に登場する有名な台詞です。直訳すると「両家に災いあれ」となり、深い恨みや絶望を表すフレーズですが、現代では「どっちもどっちだ」「どちらにもうんざり」といった軽い皮肉として使われることもあります。
言い換え・類語として使える言葉
「喧嘩両成敗」は歴史的な響きを持つ言葉ですが、今の暮らしや会話の中では、より親しみやすい表現が使われることもあります。ここでは、似た意味を持つ言い回しをいくつか紹介しましょう。
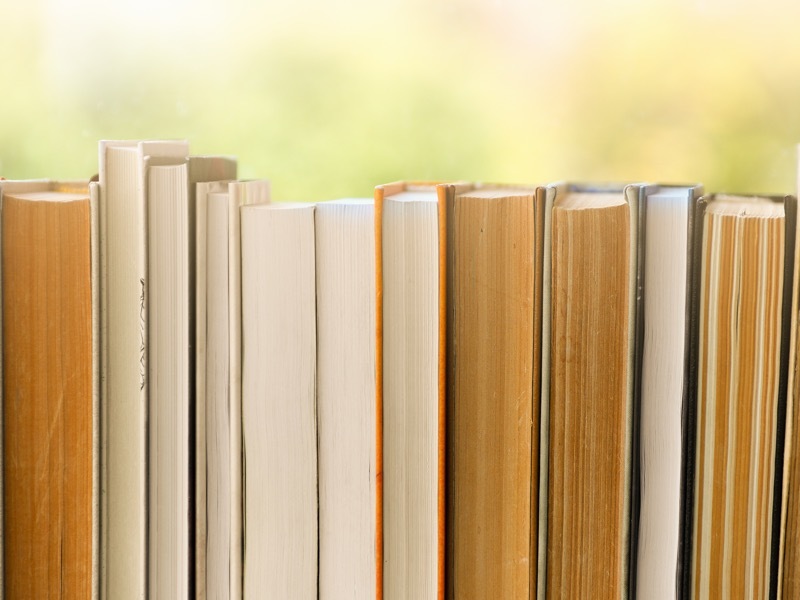
どっちもどっち
「どちらにも非がある」という意味合いで、日常の会話でよく使われます。例えばSNSで意見がぶつかったときなど、双方の言い分に問題があるような状況に対して、「どっちもどっちだね」と言うことで、少し距離を置いて状況を眺めるようなニュアンスが出せます。
痛み分け
「痛み分け」は、勝敗をつけずに互いに引き分けとなるような状態を指します。例えば、議論や争いでどちらも一歩も引かず、結果として両方にダメージが残ったような場面に使われますよ。穏便に事を収めたいときに、便利な表現ともいえるでしょう。
おあいこ
子どもの喧嘩や、ちょっとした言い争いの場面でよく耳にする言葉です。「お互いさまだから、もう水に流そう」という気持ちを込めて使われることが多く、柔らかくその場をおさめるニュアンスがあります。対立を和らげたいときにぴったりの表現です。
最後に
「喧嘩両成敗」という言葉は、時代の流れとともに、意味や受け止め方が少しずつ変化してきたようです。争いをおさめるための手段として生まれたこの考え方も、現代では別の形で語られることが多くなりました。
それでも、対立をどう扱うかという問いかけは、今も昔も変わらず私たちのそばにあるように思われます。日常の中でふと浮かぶこの言葉が、少し違った視点をもたらすきっかけになることもあるかもしれませんね。
TOP画像/(c) Adobe Stock























