追剥とは? 読み方や意味を紹介
追剥は「おいはぎ」と読みます。送り仮名を付けて、「追い剥ぎ」や「追剥ぎ」と表記することもあります。
追剥とは、通行人を襲い、衣類や持ち物などを奪うことや、奪い取る盗賊のことを指す言葉です。たとえば次のように使います。
- あの峠は追剥が出るらしいので、一人では行かないように
- 驚くようなことがあったのか、彼はまるで追剥に遭ったように呆然としていた
追剥という言葉は、江戸時代以前から使われていたようです。江戸幕府に基本法典である『公事方御定書(くじがたおさだめがき)』では、通行人を捕まえて金品を強奪し、衣類を剥ぐことを「追剥」と定義し、獄門(ごくもん)の刑に処しました。獄門は罪人の首を切り、獄屋の門にさらす刑罰で、死罪よりも一等重い罪に対して適用されたとされています。
おい‐はぎ〔おひ‐〕【追(い)剝ぎ】
通行人を襲い、衣服・持ち物などを奪い取ること。また、その盗賊。ひきはぎ。「—にあう」
追剥が登場する昔話
物が溢れ、安価に衣類が手に入る現代と比べ、かつては着物の価値が高かったと考えるのは自然なことでしょう。金品を奪うだけでなく着ている服までも奪う追剥の被害に遭ったり、被害に遭ったという話を聞いたりすることは、決して珍しくはなかったのかもしれません。
昔話の中にも、多くの追剥が登場します。有名な昔話をいくつか見ていきましょう。
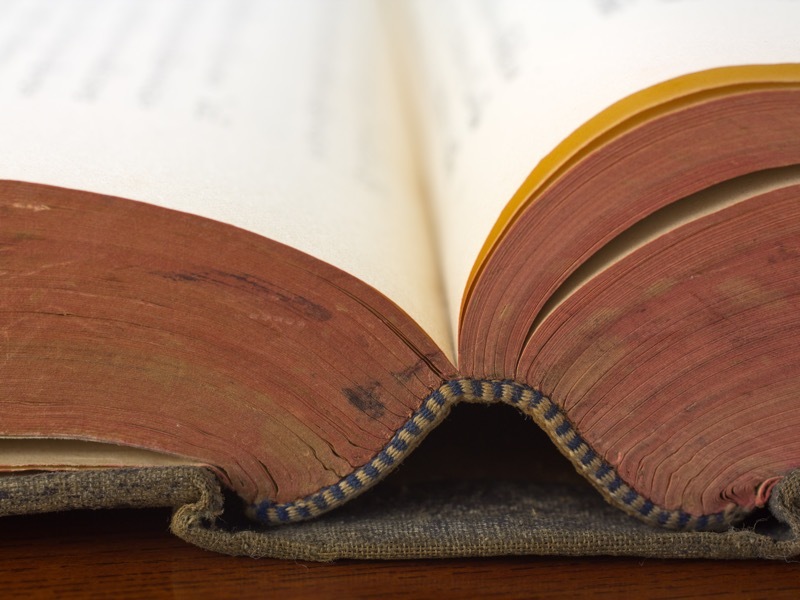
二ツ道のおいはぎ
栃木県那須烏山市に伝わる昔話です。山奥に「平野」と呼ばれる村がありました。自然が豊かで人々も穏やか、動物たちも安心して暮らせる場所でしたが、村の近くの街道に追剥が住み着くようになり状況は一変します。追剥は人々を襲っては金品や着物を奪うため、村人たちは街道を通れなくなってしまいました。
村人たちが困っていることを知ったキツネの親子は、追剥を懲らしめることを決意します。キツネは美しく光る大きな石を担いだ若者に化け、追剥のいる街道に向かいました。
予想通り、追剥が襲い掛かってきたところ、若者に化けたキツネは追剥をさんざんに痛めつけ、街道から追い出します。キツネの親子の働きにより平野には平和が戻り、安心して街道を通れるようになりました。
改心したおいはぎ
千葉県東金市に伝わる昔話です。東金で三代続いた問屋の宗兵は、商売上手として江戸でも知られた存在。いつものように江戸で上総木綿を売り、大儲けをして帰って来る途中、刀を持った追剥に遭いました。
追剥は刀を突きつけて「有り金を置いていけ」と脅しましたが、胆力のある宗兵には通じません。宗兵は落ち着き払い、追剥の様子を観察します。よく見ると追剥は大変若く、人を襲うのが初めてなのか刀の先が震えていました。
そこで宗兵は「仕入れの帰りで持ち合わせが一両ほどしかありません。東金まで一緒に来てくれたら、もう少し差し上げられるのですが……」と追剥に言いました。追剥は話を信じて宗兵の荷車を後押しし、一緒に東金に行くことに。
問屋に着いて、追剥はあまりの人の多さに驚きます。「これでは刀を振り回しても意味がない」と悟り、隙を見て逃げようと考えます。しかし、宗兵に捕まり、奥さんに「手伝ってくれた人だ」と紹介されました。
さらに宗兵は追剥を奥の部屋に招き、約束のお金と荷車を押したお礼を渡し、「ここで働いてみないか」と誘います。追剥は宗兵の人柄に感動し、心を入れ替えて働き、自分の店を持つほどに出世をしたということです。

嘉兵衛塚のとげ抜き地蔵さん
茨城県稲敷郡阿見町に伝わる昔話です。嘉兵衛という一人暮らしの老人がいました。嘉兵衛は小さな畑を耕し、空いた時間にはわらじや草履を作り、ただ一つの楽しみであるお酒を飲んで暮らしていました。
ある日も草履を売って稼いだお金でお酒を飲み、いい気分になった嘉兵衛。家路を急いでいると、森にさしかかったところで大きなオオカミに出会いました。怖くなって座り込んでしまいましたが、一向にオオカミは襲ってくる気配がありません。
嘉兵衛が目を凝らすと、オオカミの口元にかんざしが刺さっています。可哀想に思った嘉兵衛は勇気を振り絞ってかんざしを引き抜くと、オオカミは涙を流して森に消えていきました。
その翌日も、嘉兵衛は草履を売って家路を急いでいると、今度は2人の追剥に遭遇。追剥は「金を出せ」と迫ります。嘉兵衛が有り金を渡そうとしたときに現れたのが昨日のオオカミ。2人の追剥は驚き、腰を抜かして座り込んでしまいます。嘉兵衛はその隙に逃げて、事なきを得ました。
嘉兵衛が年を取って死ぬと、村人たちは墓を建て、嘉兵衛塚と呼びました。嘉兵衛塚にお参りすると自然ととげが抜けることから、とげ抜き地蔵と呼び、お堂を建てて祀ったそうです。
追剥と類似する言葉
追剥と類似した意味で使われる言葉を紹介します。いずれも似てはいますが、ニュアンスが異なります。正しく意味を理解して、使い分けるようにしましょう。

盗賊
盗賊(とうぞく)とは、盗人、泥棒のことです。人の物を盗りますが、追剥のように着ているものまで盗むかどうかまでは明確にされていません。
強盗
強盗(ごうとう)とは、暴力や脅迫などの手段で他人の金品を奪うことや、奪う者のことです。盗賊は知らない間に物を盗る可能性がありますが、強盗は脅して盗るため、相手に気付かれてしまうでしょう。
切り取り
切り取り(きりとり)とは、人を切って金品を奪うことや、奪う者のことです。追剥や盗賊、強盗は相手の体を傷つけるとは限りませんが、切り取りは傷つけることも意味に含みます。
夜盗
夜盗(やとう)とは、夜、盗みに入ることや、その者のことです。追剥や盗賊、強盗は盗みの時間が限定されていませんが、夜盗は夜限定です。
類似する言葉を使い分けよう
盗みや盗む人を指す言葉は多くあります。言葉によっては盗む時間や相手を身体的に傷つけるかどうかといった意味も含まれるため、使用する際は正確に使い分けたいもの。
また、各地に泥棒や追剥を題材とした昔話が残っています。地域の昔話を調べてみるのも面白いかもしれません。
メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock























