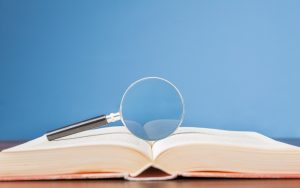「外様(とざま)」という言葉には、歴史的な背景があり、現代でも使われる場面があります。この記事では、歴史的な意味とともに、ビジネスシーンでの活用方法について考えていきます。
「外様」とは? 基本的な意味と歴史的背景
「外様」という言葉は、特に江戸時代の大名の分類の一つとして知られていますが、それだけではありません。現代では、組織や人間関係の文脈でも使われることがあります。意味や背景を理解することで、適切な使い方が見えてきますよ。

「外様」の読み方と意味とは?
「外様」は、「とざま」と読みます。辞書で意味を確認しましょう。
と‐ざま【▽外様/▽外▽方】
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
1 鎌倉幕府以後、将軍の一門または譜代の家臣でないこと。また、そのような武家・大名。→親藩 →譜代
2 組織の中などで、主流でなく、傍流の立場にあること。また、その人。「―では出世は難しい」
「外様」とは、もともと「組織の中で生え抜きではない立場」を指します。江戸時代では、関ヶ原の戦い以前から徳川家に仕えていた「譜代大名」とは異なり、戦後に従った大名が「外様大名」とされました。
「外様」の歴史的背景
「外様」という言葉は、中世から武家社会において使われてきました。当初は、主に家臣団の内部で譜代関係にない者を指し、特に鎌倉時代には幕府の中で「御内人(みうちびと)」と「外様御家人」という区分がありました。
室町時代以降、「外様」は家格を示す呼称として用いられ、幕府と深い関係を持たない大名を「外様衆」と呼ぶようになります。そして、江戸時代に入ると「外様大名」という形で明確に区別されるようになりました。
関ヶ原の戦い(1600年)以前から徳川家に仕えた「譜代大名」に対し、戦後に従属した大名は「外様大名」とされ、幕府の警戒の対象となりました。特に、外様大名は江戸に近い要所を任されることはなく、主に西国や北陸、東北などの遠方に配置される傾向がありました。
このように、「外様」という概念は単なる家臣の区別にとどまらず、時代とともに支配体制や権力関係を示す言葉として変化していきました。
参考:『世界大百科事典』(平凡社)
現代のビジネスシーンで使われる「外様」とは?
「外様」という言葉は歴史的な背景を持ちながら、現代の組織や企業文化においても使われることがあります。特に、転職者や外部からの新規参入者を指す場面で用いられ、組織内での立場を示すことがあるでしょう。
ここでは、ビジネスにおける「外様」の意味や影響について考えます。
「外様社員」とは? 会社における「新参者」の立場
企業において「外様」とされるのは、主に 転職者や外部からのプロフェッショナルでしょう。新卒から同じ企業で働き続ける「生え抜き社員」とは異なり、既存の組織文化や人間関係に馴染むまでに時間がかかることがあります。
また、業界経験が豊富であっても、企業ごとの慣習や価値観が異なるため、新しい環境での適応力が求められますね。特に、日本企業では今もなお 「終身雇用」や「年功序列」の文化が根強い職場もあり、転職者がすぐに受け入れられるとは限りません。
そのため、「外様」としての立場を理解し、適切な振る舞いをすることが大切になることもあります。

ビジネスにおける「外様」のメリットと課題
ここでは外様のメリットと課題について考えていきましょう。
《外様のメリット》
・新しい視点をもたらす
組織の中で長く働いていると、業務や考え方が固定化しがち。しかし、「外様社員」は外部の視点を持ち込むことで、業務の改善や新たなアイデアを提供できるでしょう。
・業界経験を活かせる
他の企業で培ったスキルやノウハウを活用することで、即戦力としての貢献が期待されます。
《外様の課題》
・社内文化との摩擦が生じることがある
企業によって価値観や業務の進め方が異なるため、新しい考え方が受け入れられにくい場面もあるでしょう。
・人間関係の構築に時間がかかる
長年働いてきた「生え抜き社員」と比べ、信頼関係を築くのに時間がかかることもあるでしょう。
「外様」を使った具体的な例文と言い換え表現
ここでは、「外様」を使った具体的な例文を紹介しながら、使い方を解説します。さらに、似た意味を持つ言葉も見ていきましょう。
「彼は外様だからこそ、新しい視点で物事を見ている」
この例文では、「外様」が「組織の中で生え抜きではない立場」にあることを示しています。新しく組織に加わった人は、これまでのしきたりに縛られず、異なる視点で物事を捉えることができることを強調していますよ。
例えば、転職者がこれまでの経験を生かし、新しいアイデアを提案する場面で使われることがあるでしょう。

「外様としての立場を考えながら、慎重に動いた」
ここでの「外様大名」は、江戸時代の大名の身分制度に基づいた表現です。外様大名は幕府と距離があり、直接の信頼を得にくい立場だったため、下手な行動をすると警戒されることもありました。
この例文は、組織の中で外部からの立場で関わる人が、慎重に振る舞う様子を表しています。例えば、新しく就任した経営者や、合併後に加わった幹部が、既存の文化に配慮しながら行動する場合に使えます。
「外様」の類語と言い換え表現
言葉の意味をより深く理解するために、「外様」と似た意味を持つ表現を見ていきましょう。
新参者(しんざんもの)
組織に入ったばかりの人を指します。
例文:「彼はまだ新参者だから、会社のルールを学んでいる最中だ」
異分子(いぶんし)
価値観や考え方が異なるため、周囲と調和しにくい人や存在を指します。
例文:「彼の発想はチーム内では異分子だが、新しい方向性を示してくれることもある」
傍流(ぼうりゅう)
主流ではなく、異なる系統に属している立場を指します。企業の派閥や家系の分流などの文脈で使われることが多いでしょう。
例文:「彼の出身は傍流の部門だったが、その経験が今の改革に役立っている」
最後に
「外様」という言葉は、歴史的な背景を持ちつつ、現代でも企業文化や人間関係の中で使われることがあります。その背景を理解することで、より適切な使い方が見えてくるのではないでしょうか。
TOP画像/(c) Adobe Stock