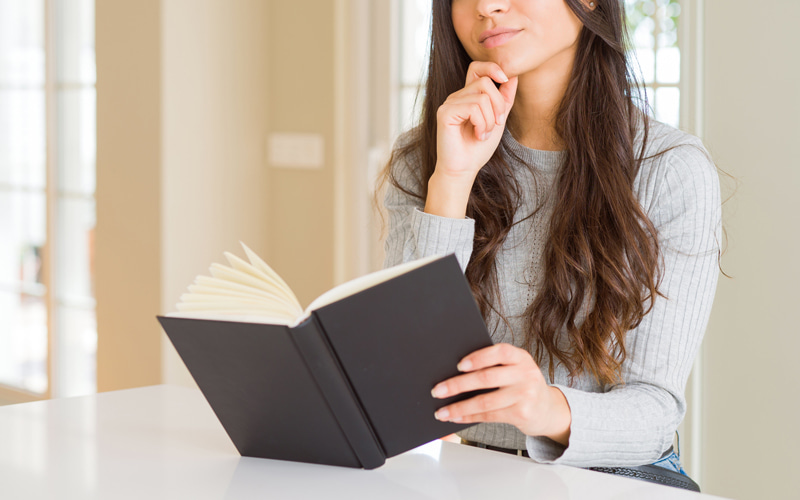目次Contents
「沙羅双樹」の意味や読み方とは?
「沙羅双樹」は「さらそうじゅ」と読み、お釈迦様が亡くなった際、寝床の四方に2本ずつあったとされる木のことです。お釈迦様が亡くなったことを知ると双樹の1本ずつが枯れ、鶴のように白くなり寝床を覆ったと伝えられています。
また、「沙羅双樹」は「無憂樹(むゆうじゅ)」「印度菩提樹(いんどぼだいじゅ)」と並んでお釈迦様と関係の深い木とされています。
「仏教三大聖樹」のひとつといわれています。仏教三大聖樹とは、お釈迦様と関係の深い木のことです。「無憂樹」はお釈迦様がこの木の下で生まれたとされる木、「印度菩提樹」はお釈迦様がこの木の下で悟りを開いたとされる木のようです。
「沙羅」は「しゃら」とも読み、サンスクリット語のシャーラまたはサーラ(sala)に由来しています。
さら‐そうじゅ
出典:小学館 デジタル大辞泉
1 フタバガキ科の常緑高木。高さ約30メートルに及び、葉は光沢のある大きな卵形。花は淡黄色で小さい。材は堅く、建築・器具用。樹脂は瀝青 (れきせい) (チャン)の代用となり、種子から油をとる。インドの原産。さらのき。さらじゅ。しゃらそうじゅ。
2 釈迦がインドのクシナガラ城外のバッダイ河畔で涅槃 (ねはん) に入った時、四方にあったという同根の2本ずつの娑羅樹。入滅の際には、一双につき1本ずつ枯れたという。しゃらそうじゅ。
3 ナツツバキの俗称。
平家物語に記された「沙羅双樹の花の色」
「沙羅双樹」という言葉は、平家物語の冒頭に「沙羅双樹の花の色」として登場します。平家物語は、鎌倉中期に語り継がれたといわれる軍記物語です。
物語の中で「沙羅双樹の花の色」が意味するものは何なのでしょうか。「平家物語」の特徴と共に、内容について簡単に紹介します。

平家物語とは
「平家物語」は、物語を聞かせることを生業としていた盲目の僧「琵琶法師」(びわほうし)によって語り継がれた物語です。おもに鎌倉時代、琵琶にあわせて語られたといわれています。
吉田兼好が記した「徒然草」(つれづれぐさ)によると、「平家物語」の作者は信濃前司行長(しなののぜんじゆきなが)とされています。しかし、作者に関しては諸説あり、実際は明らかではありません。
物語は、平家と源氏の激しい合戦で失われた武士たちの鎮魂を目的に、琵琶法師たちによって全国で語り継がれていきます。「づんど跳り越え」、「むずと組んでどうど落ち」など、擬態語を使ったわかりやすい文体が特徴です。
生き生きと語られた物語は現代でも比較的読みやすく、学校の教材としても扱われています。
平家物語の冒頭部分の意味
「平家物語」の冒頭には、以下のようなかたちで「沙羅双樹」が登場します。
祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。奢れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者も遂にはほろびぬ、ひとへに風の前の塵におなじ。
「平家物語」第一巻「祇園精舎」より
冒頭の「諸行無常」(しょぎょうむじょう)とは、この世は常に変化していくという仏教の根本的な考えのことです。続く「盛者必衰」(じょうしゃひっすい)は、勢いが盛んなものも衰え滅びることを表します。
「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす」は、この世のすべては常に変化し、どんなに勢いがあるものもいずれ滅びることを、消えゆく鐘の音や移ろう花の色に見出した表現です。
「平家物語」ではこの冒頭を皮切りに、天下をとっていた平家が源氏との戦いで滅びるまでの物語が語られます。
▼あわせて読みたい
「沙羅双樹」は「サラノキ」のこと
「平家物語」で表現されている「沙羅双樹」とは、「沙羅の木」(サラノキ)のことです。おもにインド亜大陸に原生する常緑の高木で、大きな葉を付けます。
開花は3〜7月で、淡い黄色の花を咲かせることが特徴です。日本で自然に生息することはなく、樹高は30mほどになるといわれています。

日本では「ナツツバキ」を「沙羅双樹」と呼ぶ傾向に
サラノキが生息しない日本では、「ナツツバキ」が「沙羅双樹」にたとえられる傾向にあります。ナツツバキは初夏に花を咲かせ、秋には紅葉を楽しめる落葉樹です。
花は白色で、朝に咲き夕方には散ってしまいます。「平家物語」の「沙羅双樹の花の色」はナツツバキという説もあり、はかなく散るその姿に諸行無常の姿を重ねたのかもしれません。
ナツツバキは木の幹の皮がはがれ、スベスベとした木肌が現れることから「サルスベリ」と呼ばれることもあります。
タイやカンボジアで「沙羅双樹」とされるのは「ホウガンノキ」
タイやカンボジアなどの寺院では、「沙羅双樹」の代わりに「ホウガンノキ」が植えられているとか。ホウガンノキは、サラノキのような常緑高木です。20〜30mにまで成長し、3〜5月にピンク色の花を咲かせます。
大きな特徴は、花が咲いた後に砲丸のような丸い実を付けることです。実の大きさは直径10〜20cmほどになり、名前の由来にもなっています。
南アフリカを原産地とするホウガンノキは寒さに弱く、日本国内では植物園などで栽培されています。
「沙羅双樹」の花言葉は?
「沙羅双樹」とされるサラノキは寒さに弱く、日本ではあまり見かけない植物です。生息するのは一部の植物園のみで、花言葉は設定されていないようです。
一方で、代わりとされるナツツバキには、以下のような花言葉があります。
- 愛らしい人
- 愛らしさ
- はかない美しさ
- 哀愁
「愛らしい人」や「愛らしさ」といった花言葉は、ナツツバキの白く可憐な姿に由来すると考えられます。「はかない美しさ」、「哀愁」などは1日で花が落ちてしまうことや、「平家物語」の一節が関係しているといえるでしょう。
「哀愁」と似た花言葉には、真紅のカーネーションの「心の悲しみ」や、ヒガンバナの「悲しき思い出」などが挙げられます。
また、ナツツバキは6月16日と7月15日の誕生花とされています。
「沙羅双樹」は仏教と関係の深い植物
「沙羅双樹」は、お釈迦様が亡くなる際にそばにあったといわれる植物で、仏教と関係の深い樹木といえます。
日本の古い書物「平家物語」の冒頭では、その姿に盛者必衰の意味を重ねています。また、日本で「沙羅双樹」とたとえられるナツツバキは1日で散ってしまい、「はかない美しさ」や「哀愁」などの花言葉をもつことが特徴です。
普段何気なく目にしている木々も、日本文化とのかかわりを知ることでまた違った趣が感じられるかもしれません。
初夏にナツツバキの白い花を見つけたら「沙羅双樹」の言葉とともに、「平家物語」の一節や木々の特徴などを思い出してみてください。
メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock