輪廻転生とは? 意味と読み方
輪廻転生とは、生ある者が迷妄に満ちた生死を絶え間なく繰り返すことで、仏教由来の言葉です。三界・六道に生まれ変わり、死に変わりすることを指し、インドで発達した考えといわれています。単に「輪廻(りんね)」や「流転(るてん)」と表現することもあります。
りん‐ね〔‐ヱ〕【輪×廻】
出典:小学館 デジタル大辞泉
[名](スル)《「りんえ」の連声》
1 《(梵)saṃsāraの訳。流れる意》仏語。生ある者が迷妄に満ちた生死を絶え間なく繰り返すこと。三界・六道に生まれ変わり、死に変わりすること。インドにおいて業 (ごう) の思想と一体となって発達した考え。流転。転生。輪転。「六道に—する」
〈中略〉
三界・六道とは?
仏教では、三界・六道において生まれ変わり死に変わりを繰り返すとされています。三界(さんがい)とは、欲界・色界・無色界の3つの世界のことです。欲界とは食欲や淫欲、睡眠欲といった本能的な欲望が盛んな世界です。
一方、色界とは欲界の上にある世界で、欲界のように煩悩や欲はないものの、物質や肉体の束縛からは脱却していない世界を指します。また、無色界とは色界の上にある世界です。物質や肉体から離脱し、心の働きである受・想・行・識だけからなります。
六道(ろくどう)とは、衆生(生命のあるものすべて、特に人間)が業(ごう、カルマ)によって赴く6つの世界のことです。欲界と同一で、天上界・人間界・修羅界・畜生界・餓鬼界・地獄界を指します。
さん‐がい【三界】
出典:小学館 デジタル大辞泉
<1>[名]仏語。
1 一切衆生 (しゅじょう) が、生まれ、また死んで往来する世界。欲界・色界・無色界の三つの世界。
2 「三千大千世界」の略。
3 過去・現在・未来の三世。
〈中略〉
ろく‐どう〔‐ダウ〕【六道】
出典:小学館 デジタル大辞泉
仏語。衆生がその業 (ごう) によっておもむく六種の世界。生死を繰り返す迷いの世界。地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人間道・天道。六趣 (ろくしゅ) 。六界 (ろっかい) 。
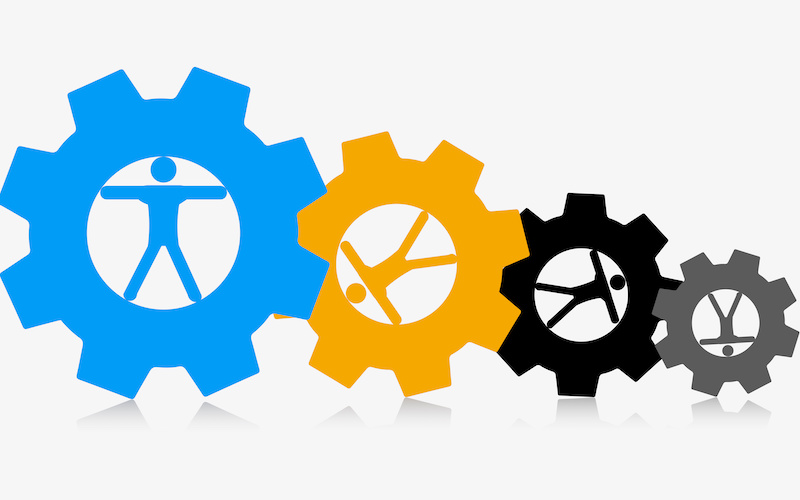
輪廻転生の行く先を決めるとされる引業とは?
生ある者は三界・六道の中で生まれ変わりを繰り返すという考えの「輪廻転生」。来世の生まれ合わせを決定するのは「引業(いんごう)」だと考えられているようです。生きている間の業のうち、もっとも重い業で次の世界が決まるとされています。
なお、引業により来世の世界が決まることに対し、「満業(まんごう)」によって性別や身分、富裕かどうかなどが決まるとも考えられています。
いん‐ごう〔‐ゴフ〕【引業】
出典:小学館 デジタル大辞泉
仏語。来世の生まれ合わせを決定する業。
まん‐ごう‥ゴフ【満業】
出典:小学館 精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 仏語。来世に人間界など共通の界に生まれ合わせることを決定する引業に対し、等しく生まれ合わせたもののなかで、男女・貧富・貴賤など個別の差を決定させる業。
業(カルマ)とは?
業(カルマ)とは、インド哲学や仏教などにおいて、来世に影響を与える個人の行為や意識を指す言葉として使われます。「行為」を意味する、サンスクリット語が語源となっているようです。
仏教ではカルマが蓄積されることで、終わりのない輪廻転生が続くと考えられました。悟りを開いてカルマを断ち切ると、輪廻転生からの解脱が可能になり、悟りの境地である涅槃(ねはん)に至るとされています。
ごう〔ゴフ〕【業】
出典:小学館 デジタル大辞泉
《(梵)karmanの訳》
1 仏語。人間の身・口・意によって行われる善悪の行為。
2 前世の善悪の行為によって現世で受ける報い。「—が深い」「—をさらす」「—を滅する」
3 理性によって制御できない心の働き。
輪廻転生と類似する概念|実例はある?
生まれ変わり・死に変わりするという考え方は、仏教固有のものとはいえないでしょう。さまざまな宗教や地域の風習などには、生まれ変わり・死に変わりの概念がベースとなったものが見られます。いくつかの例を簡単に紹介します。
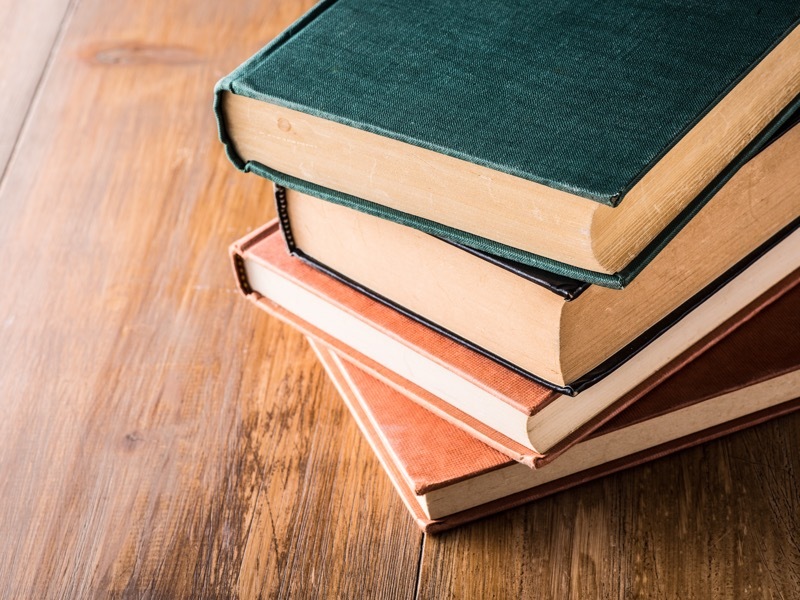
復活(キリスト教)
復活(ふっかつ)とは死んだ人やものが生き返ること。キリスト教では、十字架にかけられて亡くなったイエス・キリストが生き返ったことを指し、重要な教理の一つです。
ふっ‐かつ〔フククワツ〕【復活】
出典:小学館 デジタル大辞泉
[名](スル)
1 死んだものが生き返ること。よみがえること。蘇生 (そせい) 。
2 いったん廃止したものなどを再びもとの状態に戻すこと。また、消失したものが、再びもとの状態に戻ること。「旧制度が—する」
3 キリスト教で、十字架上で死んだイエス=キリストがよみがえったことをいい、キリスト教の最も中心的な信仰内容。イエスの復活は罪と死に対する勝利であり、神の愛による人類の救いの完成という意味をもつ。
転生(チベット仏教)
チベット仏教では、転生によって高僧の地位が継承されると考えられていたようです。その中でもよく知られているのがダライ・ラマやジェブツンダンバの転生です。
ダライ・ラマはチベットでは宗教だけでなく政治的指導者ともされ、一方、ジェブツンダンバはモンゴルにおけるチベット仏教の指導者としてもっとも高い権威を持ちます。
ダライ・ラマは観音菩薩の化身で、先代が亡くなってから次の生まれ変わりを探すことでその地位をつないできました。新しいダライ・ラマは、先代の遺言や聖なる湖の観察、また、先代の遺品を認識できるかなどによって判別されているようです。
偶然によって転生したのではなく、本人の意思により、人々を救うために生まれ変わってきたと考えられています。
てん‐しょう〔‐シヤウ〕【転生】 の解説
出典:小学館 デジタル大辞泉
[名](スル)生まれ変わること。転じて、環境や生活を一変させること。てんせい。「輪廻 (りんね) —」

生まれ変わり(出羽三山)
日本でも、輪廻転生のように生まれ変わりが信仰となって根付いている地域があります。たとえば月山(がっさん)と湯殿山(ゆどのさん)、羽黒山(はぐろさん)の出羽三山は、日本古来の山岳信仰が息づく場所として、また「生まれかわりの旅」を体験できる場所として多くの参詣者を迎える山です。
出羽三山にはそれぞれ役割があり、羽黒山は現世利益を叶える現在の山、月山は死後の安楽と往生を祈る過去の山、湯殿山は新しい命の誕生を表す未来の山と考えられています。三山を巡ることで死と再生を辿り、心身ともにうるおう体験として広まりました。
死後の国(古代エジプト)
2,000~5,000年ほど昔のエジプトでは、死後の世界が信じられていたようです。ナイル川の上流にあるルクソールの西岸は太陽が沈むことから死者の町と考えられました。王家の墓や葬祭場が多数作られ、近年でもミイラや遺物などが発見されています。
死後の世界へ行くには肉体が必要です。死後の世界では生前と同じような生活を送ると信じられていたため、肉体が腐らないようにミイラとして保存してから埋葬する習慣が生まれたといわれています。
また、来世で食べたり話したりするためには、口が必要です。埋葬前に「開口の儀式」を行い、来世でも口を使えるようにしたと考えられています。
世界中に見られる輪廻転生思想
世界中の至るところで、輪廻転生の考え方が見られます。死に対する恐怖や現実世界における不満なども、輪廻転生の考え方が生まれた理由の一つといえるかもしれません。
紹介した思想以外にも、生まれ変わりの考え方は多数あります。それぞれの考え方から、地域・時代の価値観を探ってみるのもよいかもしれません。
メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock























