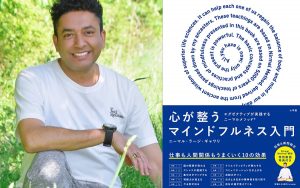目次Contents
この記事のサマリー
・「人のせいにする人」の心理背景には、「劣等感」や「自己防衛」などが関係していると考えられます。
・「人のせいにする人」が職場や家庭にいる場合の具体的な対処法として、「即答を避ける」「記録を残す」ことなどが効果的です。
職場や家庭、友人関係の中で、「あの人、いつも人のせいにしてくる…」と感じた経験はありませんか? 自分に非がないようにふるまい、トラブルが起きるたびに誰かのせいにしてしまう人。そんな相手とどう向き合えばいいのか、そもそもなぜそのような行動を取るのか…。
この記事では、「人のせいにする人」の特徴と背景を探りながら、関係に悩むあなたが少しでも心を軽くできるヒントをお届けします。
人のせいにする人の心理と特徴を知る
「なぜあの人は人のせいにするの?」。まずは、そんな疑問を解消するために、「人のせいにする人」の心理と特徴を探っていきましょう。
人のせいにする人の深層心理と防衛メカニズム
人のせいにするという行動の裏には、「自分の非を直視するのが怖い」「自分を守るための無意識のクセ」といった深層心理が潜んでいると考えられます。
また、「自分は無能だと思われたくない」という劣等感から、自分を守るために他者を責めるケースも少なくありません。
私たちは誰しも少しずつ、こうした心の「逃げ場」を持っていますが、それが過剰になると周囲に悪影響を及ぼすことがあるのです。
育ち・家庭環境との関係はある?
例えば、子ども時代に「失敗を厳しく責められる環境」で育った人は、「失敗=人格否定」と感じやすくなり、責任を取ることに強い不安を抱えることがあります。すると、大人になってからも「自分が悪い」と認めることを極端に避ける傾向が出てくるようです。
また、親が過保護すぎたり、代わりに問題を処理してしまう家庭では、「自分が責任を取らなくてもなんとかなる」という学習が無意識に根づくことがあります。家庭内コミュニケーションの在り方が、人格形成に大きな影響を与えることがわかりますね。

「病気なのかも?」と思うときの判断ポイント
「この人、あまりに極端に人のせいにしてばかり。もしかして病気なのでは?」と思ったことがある人もいるかもしれません。実際、極端な責任転嫁が見られる場合、いくつかの精神的特性や障害の可能性が指摘されることがあります。
ただし重要なのは、これらは診断名であり、安易に「〇〇っぽい」と決めつけてはいけないという点です。あくまで専門家(精神科医や臨床心理士など)による診断が必要であり、素人判断でレッテルを貼ることは信頼関係を壊すだけでなく、誤解や偏見を助長するおそれもあります。
それでも、「もしかして…」と思った時点で、自分自身がその人との関係に負担を感じている証拠ともいえます。無理に理解しようとせず、自分を守る視点を持つことも大切です。
関わり方に悩んだときの実践的ヒント
「人のせいにする人」と関わらざるを得ない状況は、職場でも家庭でもしばしば起こります。真っ向から否定すれば反発を招き、黙っていれば自分の心がすり減る… そんな板挟みのような状態に、疲弊している方も多いのではないでしょうか?
ここでは、感情に振り回されないための実践的な距離感の保ち方、具体的な会話の工夫、そして自分自身を守る視点を紹介します。
職場にいる「人のせいにする人」との接し方
「え、これ私の責任なんですか?」と内心戸惑いながらも、表面上は波風を立てないようにやり過ごす… そんな経験が、職場では特に起きやすいものです。人のせいにする同僚や上司がいると、空気が悪くなるだけでなく、自分の評価や業務にも影響が出ることがあります。
そんなとき、まずはその人と「感情的に対決しない」ことが鉄則です。対処法としては、
・記録を残す(メールやチャットなどで確認事項を文書化)
・第三者を介して対応する
・「今は確認してから回答しますね」と、即答を避ける
など、冷静かつ論理的に距離を取る方法をおすすめします。相手を変えようとするのではなく、自分の「巻き込まれない力」を育てることが、精神的安定に繋がります。

パートナーや家族が「人のせい」タイプだったら…
仕事関係以上に難しいのが、身近な存在が人のせいにしてくる場合です。特に夫や親など「家族ゆえに距離が取りづらい関係」では、自己否定感を抱いたり、自責に陥ったりしやすくなります。
「なんであのとき、ちゃんと話を聞かなかったんだ」「あなたがああ言ったから、うまくいかなかった」… こうしたセリフを繰り返す相手に、あなたが振り回されていると感じるなら、それは立派な「心理的支配」にあたるかもしれません。
そんなときは、以下のような対応が有効です。
・話をすぐに受け止めず、「少し考えさせて」と間を置く
・一方的に責められたら、「それは私だけの責任ではないと思う」と穏やかに返す
・同じ話が繰り返される場合は、「その話はもう終わったことにしない?」と提案する
自分が「反応しすぎない」ように距離を整えること。それが自尊心を守る第一歩です。
反応しない強さを持つための「自己防衛フレーズ」
「また人のせいにされた」「何か言い返したいけど、角が立ちそう」…。そんなときに役立つのが、「自己防衛フレーズ」です。感情的に反発するのではなく、冷静に、そして相手を責めずに距離を置く言葉選びが鍵になります。
例えばこんな言い方があります。
・「それについては、ちょっと考えが違うかも」
・「責任の分担については、また整理して話そう」
・「今はそれについて議論したくないな」
こうした言い回しは、相手の主張をすぐには受け入れず、かといって攻撃的にもならない絶妙なラインを保ってくれます。
実際、筆者もあるプロジェクトでミスをなすりつけられそうになった際、「まずは事実を確認してから話しましょう」と伝えたことで、それ以上の追及を防ぐことができました。
SNSや日常会話でも使える、少し知的で穏やかな返し。こうしたフレーズを「自分の辞書」として持っておくことで、心の余裕が生まれます。
人のせいにする人の「末路」とは?
「人のせいにする」行動が続いたとき、目に見える変化がすぐに現れるわけではありません。ただし、その人が周囲からどう見られ、どんな立場に追い込まれていくかという「社会的な末路」には、一定の傾向があります。
例えば職場では、「一緒に仕事をしたくない人」として避けられるようになったり、評価が下がって責任ある仕事から外されることもあるでしょう。また、友人関係や家族内でも、徐々に人が離れていき、孤立感を深めることがあります。
つまり、「人のせいにする人」は、自分では気づかぬうちに信頼資産をすり減らし続けているのです。
もちろん、こうした末路を迎えるすべての人が反省するとは限りません。しかし、信頼を築くことの大切さに気づいたとき、初めて自分のふるまいを見直すきっかけになるかもしれません。
そのためにも、周囲の私たちは「責任を押し返す言葉」だけでなく、「距離を置くという選択肢」も持ち合わせていたいものです。

「人のせいにする人」に関するFAQ
ここでは、「人のせいにする人」に関するよくある疑問と回答をまとめました。参考にしてください。
Q1.「人のせいにする人」とは性格の問題なのでしょうか?
A. 一概に性格だけの問題とはいえません。
環境や育ってきた過程、トラウマ、ストレス状況など、さまざまな要因によって表出することがあります。
Q2.距離をとった方がいい相手の特徴はありますか?
A. 一般的に、以下のような傾向が強い場合は注意が必要です。
・ミスや失敗を一切認めない
・周囲に悪影響を与えても気にしない
・責任を押しつけるだけで解決策を考えない
・謝罪を求めると逆ギレする
こうした場合、改善を望むよりも「巻き込まれない距離感」を優先することが、自分を守るうえで有効です。
Q3.逆に、自分が「人のせい」にしていないか不安です…。
A. その気づきがあるだけで、あなたはすでに自己省察力のある方です。
もし「イライラするとつい誰かのせいにしてしまう」と感じたら、少し時間をおいて感情を整理したうえで、「自分は何をコントロールできたか?」を振り返る習慣を持つことをおすすめします。小さな責任を受け止める力が、信頼される人への一歩になります。
最後に
「人のせいにする人」と関わるとき、私たちは怒りや苛立ちだけでなく、悲しさや無力感も感じてしまうことがあります。ですが、相手を理解することと、振り回されずに自分を守ることは、両立できます。
このテーマを深掘りしていくと、実は「自分の言葉」や「選択」に丁寧であることの大切さにも気づかされます。誰かを責める言葉ではなく、自分の人生を引き受ける言葉を選べるように…。そんな視点でこの記事が、日々の対話や人間関係を少しでも軽やかにするヒントになれば幸いです。
TOP画像/(c)AdobeStock