「大晦日」の意味や由来とは?
1年が過ぎていくのは本当に早いものですね。世界情勢の混迷や円安、インボイス制度などさまざまな制度の変更のあった2023年は、例年より過ぎるのがより早く感じたという人もいるのでは? そんな1年の締めくくりのとなる12月31日、「大晦日」について、少し深掘りしてみたいと思います。

そもそも12月31日が「大晦日」と言われる由来や意味について、即答できたりしますか? なかなかそうはいかないですよね。この部分はしっかり押さえて、話題にのぼった時に差し込めるようにしましょう♪
◆大晦日の意味と由来
「大晦日」を解説する前に、まずは「晦日(みそか)」について。「晦日」は「晦(つごもり)」ともいわれ、毎月の最終日のことを指します。この「つごもり」とは、月が隠れることを意味する「月隠り(つきごもり)」が転じたもので、月が見えなくなる時期のことを表しています。
今の暦は太陽暦ですが、日本では1872(明治5)年まで、太陰太陽暦が用いられていました。一般的には旧暦と呼ばれます。この旧暦は、月の満ち欠けに合わせて暦が決められていました。新月を1日とし、月が隠れる「晦日」はおおよそ毎月30日。このことから30日は「晦日」と呼ばれるようになりました。
その後、新暦になり、ひと月が30日になったり、31日になったりするようになりましたが、今ではその月の最終日のことを「晦日」、「つごもり」と呼ぶようになったのです。そこに加え、1年の終わりであり、新年との節目である12月の晦日は特別な日。なので頭に「大」をつけて「大晦日」と呼ぶようになりました。
「大晦日」の行事ごとは?

大晦日を特別な日として扱う歴史はかなり古く、平安時代にはそのような風習があったと言われています。大晦日は歳神様(としがみさま)を迎える準備をする日。歳神様とは、稲の豊作をもたらす神で、人々は厚く信仰してきました。この歳神様は、新年に各家庭を訪れるとされており、大晦日はその準備をするのです。
◆除夜の鐘
大晦日の夜から元日にかけて、寺院が撞く鐘のことを「除夜の鐘」と言います。その回数は108回。人の煩悩の数の鐘をついて、煩悩を払い、清らかな心で新年を迎えることができるようにと願うもの。一般的には107回目までが年内に撞かれ、最後の1回は新年に入ってから撞かれます。
◆年越しの祓(はらえ)
いわゆる厄落としです。神社では6月と12月、半年ごとに穢れを落とす行事をします。6月30日は「夏越しの祓」、12月31日は「年越しの祓」。白紙で作った人形を川へ流したり、篝火を焚いたり。それまでにたまった穢れを払って、それ以降を健康に過ごせるように願います。
「大晦日」の過ごし方
大晦日、あなたはどのように過ごしますか? これまでの風習を見てみましょう。
◆年の湯
大晦日の夜のお風呂のことを「年の湯」と言います。この1年で最後のお風呂で身も心もきれいにし、気持ちよく新年を迎えるのです。今ではお風呂は毎日入るものと思われていますが、昔はそうではありません。大晦日にしっかりとお風呂に入るのは、禊的な気分もあって、きっと特別なことだったのでしょうね。
◆年籠り
歳神様は、初日の出とともにやってくるという説があります。ですから、日の出の時間に寝てしまっていては失礼ですね。というわけで、寝ないで日の出を待つという風習がありました。ちなみに、うっかり寝てしまったりすると「シワや白髪が増える」というちょっと怖い言い伝えもあったようです…。
大晦日に何を食べる?「年越し蕎麦」には色々な呼び方が

大晦日に食べるものの代表格といえば「年越し蕎麦」。この風習は意外に新しいもので、江戸時代に始まったものだそう。蕎麦は切れやすいことから、「一年の災厄を断ち切る」という意味があると言われています。
年越し蕎麦に関しては、ちょっとおもしろい逸話があります。江戸時代、金箔職人は飛び散った金箔を集めるのに蕎麦粉を使っていました。そのことから、年越し蕎麦を残すと、新年は金運に恵まれない年になるというもの。こんな話を聞くと、残さず食べようと思いますね。
ちなみに、年越し蕎麦のことを「晦日蕎麦」と呼ぶことがあります。このことからもわかるように、月末に蕎麦を食べる風習があり、そのうち大晦日に食べる習わしだけが残ったようです。
◆年越し蕎麦のいろいろな呼び方
年越し蕎麦には、さまざまな呼び方があります。
◯寿命蕎麦:蕎麦のように、長生きできるようにと願う蕎麦です。
◯福蕎麦:さきほど述べたように、金箔職人や金銀細工の職人が散らばった金箔を集めるのに蕎麦粉を使ったことから、蕎麦を金を集める縁起物と考えた呼び方です。
◯縁切り蕎麦:蕎麦がよく切れるのと同様に、1年の苦労と縁を切って新年を迎えるというものです。
最近では「年明けうどん」なる新しい風習も出てきて、31日に蕎麦、1日にうどんと炭水化物が続く…なんてことも。
近年の大晦日の過ごし方

かつては一家が集まって年越しをする風習がありましたが、近年では少し様子が変わっています。
◆イベントに参加する
年越しライブやテーマパークの年越しイベント、カウントダウンイベントなど、新年を祝うさまざまなイベントが行われます。とはいえ、これらのイベントには大勢の人が集まりますね。アフターコロナになって初の年越しということもあって、年越しイベントに参加するのが何年振り!と、友達と出かけるのを心待ちにしている人も多いのでは?
◆旅行にいく
新年をいつもと違う場所で、という気持ちからでしょうか、旅行に行く人も多いですね。毎年年越しはあそこで、と場所やお宿を決めているという家族も多いはず。
◆お墓参りに行く
家の掃除をするように、お墓の掃除をしに、年末にお墓参りに行く人も多いようです。お墓をきれいにして、ご先祖さまに一年の報告と新年のあいさつ。歳神様はご先祖様だという説もありますから、お墓参りをするのはいいですね。
◆初詣に行く
大晦日の夜から初詣に出かけて、年越しを境内ですることを二年詣りといい、とても縁起がいいと言われます。とはいえ、京都の有名な神社など、大きな神社では人が多い… という心配も。家の近くの神社で、静かに新年を迎えるのもいいですね。
◆テレビを見る
NHKの「紅白歌合戦」とはじめ、人気の年越し番組がありますね。あたたかい部屋でテレビを見ながらのんびり過ごす… という人も多いのではないでしょうか? 今年は忙しくって大変だったという人は、家族と一緒にのんびり過ごすのも良さそうです。もちろん「気になっていたけれどなかなか観られていなかったドラマ」をVODなどで一気見する、という人も多そう。
最後に
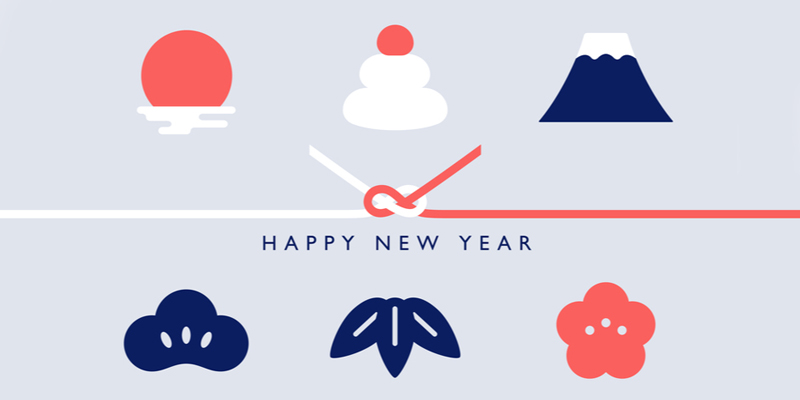
掃除や門松の準備などのお正月支度は「事はじめ」の日、つまり12月13日がいいと言われています。また、神様を迎える準備ですから、大晦日にバタバタとやるのではなく早めに済ませ、落ち着いて大晦日を過ごしたいものですね。
TOP 画像/(c)Shutterstock.com





















