目次Contents
「建国記念の日」は日本ができた日ではない

「建国記念の日?」「建国記念日?」 なんとなく、建国をお祝いする日であるという認識で、正しい意味をご存知ない方もいるのではないでしょうか? 本記事では、2月11日の「建国記念の日」の本当の意味・制定された経緯について解説します。
「建国記念の日」とは?
毎年2月11日は「建国記念の日」と定められています。年によって日付が移動することはなく、毎年同じ2月11日が「建国記念の日」にあたり、1948年に施行された「国民の祝日に関する法律」で国民の祝日と定められています。
この法律の中で「建国記念の日」は、「建国をしのび、国を愛する心を養う」と記述されています。日付については「政令で定める日」と記され、「建国記念の日となる日を定める政令」にて、1966年に「建国記念の日は、二月十一日とする」と制定されました。
「建国記念の日」を英語で表すと?
「建国記念の日」を英語にすると、「National Foundation Day」となります。あわせて頭の片隅にでも、覚えておきたいですね。
「建国記念の日」ができた経緯とは?

明治時代までは「紀元節」と呼ばれる建国を祝う祝日がありました。しかし、第二次世界大戦後の1948年『初代天皇の即位に起源をもつ「紀元節」は、天皇を崇拝する日本人の団結力を高めるのではないか』というGHQの懸念により廃止されました。
その後、国民の間で「紀元節」復活の動きが高まり続け、1966年になってようやく、2月11日を「建国記念の日」として制定されることになりました。ところで、なぜ2月11日になったのでしょうか?
これは、日本の初代天皇である神武天皇が即位した日をもとにしています。『古事記』や『日本書紀』を紐とくと、神武天皇の即位は紀元前660年1月1日とされており、この日付は古代で使われていた旧暦です。今も使われている新暦に換算すると、紀元前660年1月1日は、現在の2月11日にあたる事から、この日を「建国記念の日」にすると定められました。
神武天皇とは、日本に伝わる数々の伝説や神話に登場する人物で、天照大神の直系でありながら、日本を建国したとされる伝承上の人物です。
「建国記念の日」が「建国記念日」ではない理由
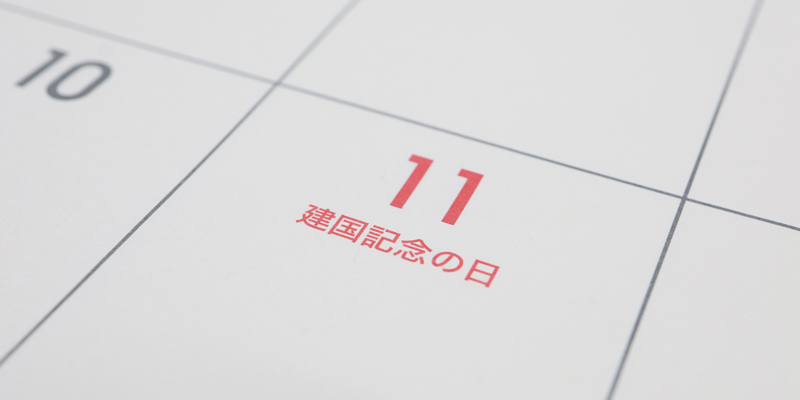
「建国記念の日」と「建国記念日」の、2つを耳にする事がありますよね。どちらが正しいのでしょうか?
日本の建国は『古事記』や『日本書紀』の神話から導いていることは、先述したとおりです。アメリカの独立記念日や、オーストリアの建国記念日のように、はっきりと日付がわかっている国とは異なり、明確な日付がありません。このことから、日本という国ができた記念の日ではなく「日本という国が建国された事実をお祝いする日」という考えのもと「記念日」ではなく「記念の日」となりました。なんだか理屈っぽいですが、たしかに違いがありますね。
世界の建国記念日
世界に存在する独立国の中で、百十数ヵ国が建国記念日に相当する日を持っています。各国の建国記念日の内容はというと、3分の2以上は旧植民地国の独立記念日です。次に多いのが、共和国創立記念日や革命記念日となります。
日本のように古代の建国説話に基づく建国記念日を持つ国は、他に大韓民国の開天節(10月3日)のみなんですよ。
「建国記念の日」は特別な行事はない?
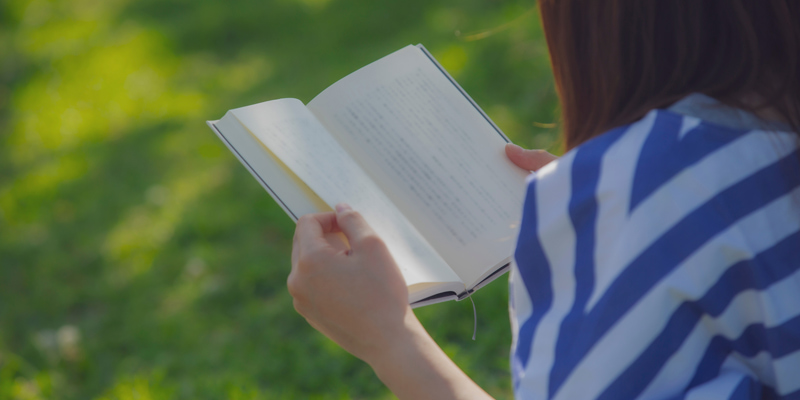
「建国記念の日」に、特別な行事はありません。しかし、せっかくの「建国記念の日」なので、これを機会に、日本の初代天皇である神武天皇について調べてみるのはいかがでしょうか?
日本書記では名前を、神日本磐余彦天皇(かみやまといはあれびこのすめらみこと)と記されています。筑紫の日向で誕生し、数々の苦難を乗り越えながら東征を進め、辛酉元旦に大和の橿原の宮で即位した初代天皇とされています。
このように「日本という国の成り立ちとは?」を辿り続けると、神話の世界に繋がります。改めて日本という国の不思議について想いを馳せるのも、「建国記念の日」ならではの過ごし方になるかもしれません。
最後に
2月11日は、「建国記念日」とは言わず「建国記念“の”日」とすることで、日本の建国をお祝いする日となりました。自分たちが当たり前のように暮らす国なのに、歴史を辿っていくと知らないことがたくさんありますね。「建国記念の日」に「建国をしのび、国を愛する心を養う」ように、過ごしてみてはいかがでしょうか?
TOP画像/(c)Adobe Stock























