雑兵とは? 意味と読み方
雑兵(ぞうひょう)とは、身分の低い兵士のことです。取るに足らない者といった意味でも使われます。
・大将の周りには数十もの雑兵たちが守りを固めていた
・雑兵たち一人ひとりの名前はわからないが、とにかく多くの兵士たちが村を襲来した
・雑兵がするような仕事を任されたと揶揄する声も聞こえたが、出来で勝負したい
雑兵と似た意味で使われる言葉には、足軽(あしがる)や歩卒(ほそつ)があります。各言葉の意味も見ていきましょう。
ぞう‐ひょう〔ザフヒヤウ〕【雑兵】
出典:小学館 デジタル大辞泉
1 身分の低い兵士。歩卒。ざっぴょう。
2 取るに足りない者。下っ端。
「我輩の如き―すら…一身を顧みるに遑いとまなかったです」〈魯庵・社会百面相〉
足軽との違い
足軽(あしがる)とは「足軽くよく走る兵士」の意味で、普段は雑役を務め、戦時になると歩兵として働く者を指します。戦国時代には、弓や槍(やり)、鉄砲などの武器を持って戦う兵士として活躍したようです。
一方、雑兵は足軽や地侍、戦争ごとに動員された農民などをまとめた総称です。おもに家名のない「名もなき人」を指したとされますが、江戸時代では幕府の同心といった身分があまり高くない武家も含めて「雑兵」と呼ぶこともあったようです。
あし‐がる【足軽】
出典:小学館 デジタル大辞泉
《足軽くよく走る兵の意》中世・近世、ふだんは雑役を務め、戦時には歩兵となる者。戦国時代には弓・槍・鉄砲などの部隊の兵士として活躍。江戸時代には諸藩の歩卒(ほそつ)をいい、士分と区別された。
歩卒との違い
歩卒(ほそつ)とは、徒歩で従軍する兵士のことです。歩兵(ほへい)や足軽と同義で使われることもあります。また、身分の低い兵士という点では、雑兵と同じといえるでしょう。
ほ‐そつ【歩卒】
出典:小学館 デジタル大辞泉
徒歩で従軍する兵士。歩兵。足軽。

『雑兵物語』に見る雑兵の生活・心得
『雑兵物語(ぞうひょうものがたり)』とは、足軽などの身分の低い兵士たちに経験や生活を語らせた書物とされています。1683年以前に成立したとされ、作者・編者は明らかではありませんが、老中で川越藩主でもあった松平信綱の五男で、京都所司代などを歴任した信興(のぶおき)が執筆に関わっているのではとも。
江戸時代は戦のない平和な世であったため、本来は兵士として働く武士たちは合戦の心得を忘れてしまうこともあったとか。常に危機意識を持って生活をするためにも『雑兵物語』は多くの写本がつくられ、武士の教科書として使用されたようです。
雑兵の出自
『雑兵物語』では、、戦場・武備・武具などの重要事項が口語で記されています。戦争が起こるたびに強制的に集められた人々のため、主人に対する忠誠心はあまりなかったようです。
雑兵の装い
雑兵は合戦の最前線で戦う兵士です。武士のように鎧や兜などの重装備では駆け回ることができないため、陣笠(じんがさ)や足軽胴(あしがるどう)といった軽量かつ着脱しやすい装備を身に付けていました。
陣笠とは、室町時代以降に誕生した笠で、薄い鉄や革でつくられています。漆を塗って強度を高め、兜の代わりとして足軽や雑兵がかぶったそう。後世には、外縁を反らせて武士の外出時の装いとしても活用されました。
また、足軽胴とは、簡易的な戦装備です。腹掛けのような一枚の薄い金属でできたタイプ(背中部分は覆われていない)や、前面と両脇を守るように三枚の金属をつなげたタイプなどがあります。
陣笠や足軽胴は主家から貸与された装備です。競り合う場面で敵味方を間違えないように、主家の家紋や特徴的な図などが描かれていたようです。
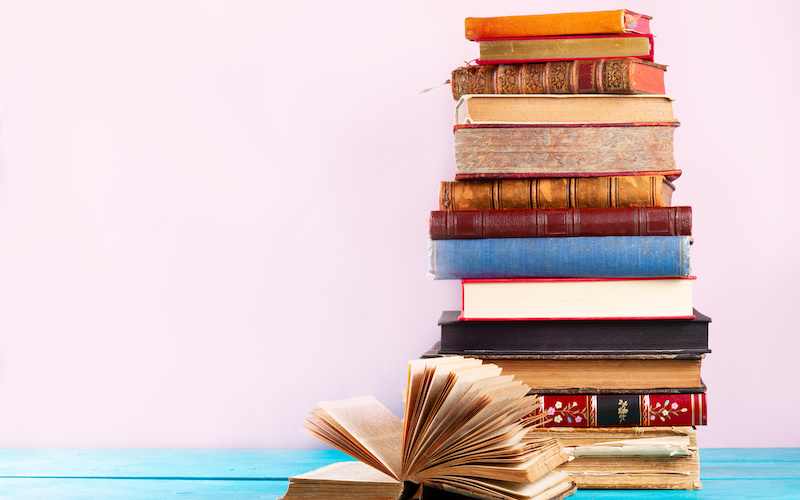
雑兵の心得
雑兵は普段は農作業などに勤しんでいるため、日々、戦の訓練をしているわけではなかったのでしょう。『雑兵物語』には、合戦に向かう臨時兵士たちが心得ておくべき事柄が多く記載されているのが特徴的。また「合戦でこうしたら上手くいった」「このような行動は失敗するから、避けるほうがよい」といった経験に基づいたアドバイスも紹介されているようです。
合戦の心得
槍足軽に対しては、まずは基本の心得として「槍は突くだけの道具ではない」という点が述べられています。敵兵の背中にある旗を叩き落とすつもりで槍足軽たちがタイミングを合わせて一斉に槍で叩く使い方もしていたとか。
また弓足軽には、敵兵が遠くにいるときは腰の矢入れの矢を使わずにその場で渡された矢を射る、敵兵が近くなったときは、合図に従って矢入れの矢を射る、練習よりも倍の時間をかけて十分に的を絞るなど、矢を無駄にしない戦い方を勧めているようです。
戦場での過ごし方の心得
雑兵にとって、戦いは野宿の連続とも。山や平原をサバイバルしていくためにも、先人の知恵が必要です。たとえば、調理や暖を取るために薪(たきぎ)が必要ですが、手に入らないときは乾燥した馬の糞を使うことを勧めているようです。
また、寒いときにはトウガラシをすりつぶして全身に塗るように、ともあるとか。ただし、手に塗ってしまうと、間違って目をこすると大変なことになるため注意が必要だとも記載されています。
食事の心得
荷物を縛る縄には、里芋の茎を干したものを勧めています。味噌で味をつけて湯に入れれば、味噌汁の具材としても活用できるでしょう。
喉が渇いたときは、梅干しを眺めるようにというアドバイスも。実際に舐めると余計に喉が渇くため、単に眺めて口内に唾を満たし、渇きを癒やすようにといった旨が記載されています。
また、戦いの日数分、胡椒の実を携帯することも勧めているよう。1日に胡椒を1粒かじると、寒さや暑さに耐えやすくなると考えられたそうです。
江戸・明治時代の雑兵
江戸時代になると、雑兵のうちの一部は、足軽や同心といった位の低い武士になりました。また、明治時代には警部や大将などの地位の高い役職は武士出身の人が多く占めましたが、巡査や兵員のなかには雑兵出身者もいたようです。
雑兵の暮らしに思いを馳せよう
雑兵は「取るに足らない者」を意味することもありますが、戦時にはその活躍によって歴史を変える存在でもありました。わかりやすく現代語に訳された本も出版されているため、一度『雑兵物語』を読んでみるのも面白いかもしれません。
メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock























