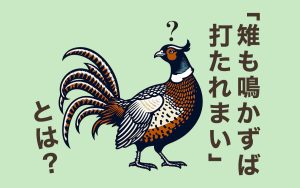目次Contents
この記事のサマリー
・「来るもの拒まず、去るもの追わず」は孟子に由来することわざです。
・ビジネスや恋愛では使い方に注意が必要です。思いやりを示す一言を添えると安心感が伝わります。
・英語では “welcome” “respect” などを使って、表現できます。
人との距離感がわからなくて疲れたり、どう付き合ったらいいのか悩んだり、人間関係で心地いい距離を保つのは、意外と難しいものですよね。
そんなモヤモヤを感じたときにヒントをくれるのが、「来るもの拒まず、去るもの追わず」という言葉です。古くから伝わるこの考え方は、誰に対してもオープンでありながら、自分自身の軸をしっかりと持つという、大人の女性にこそ必要な心の持ち方です。
この記事では、「来るもの拒まず、去るもの追わず」の意味から、日常生活や職場で役立てるためのヒントまで、具体的に紹介します。
「来るもの拒まず、去るもの追わず」の基本
「来るもの拒まず、去るもの追わず」という言葉は、自立した態度として肯定的に捉えられる一方、冷たい人だと誤解されてしまうこともある言葉です。まずは、言葉の基本的な意味や由来を確認しておきましょう。
「来るもの拒まず、去るもの追わず」意味や読み方、ことわざとしての整理
「来るもの拒まず、去るもの追わず」は「きたるものこばまず、さるものおわず」と読む、ことわざです。一般的には「くるものこばまず」と読む場合も多く、これも間違いではありません。
ここでは同じ意味を持つ「往(ゆ)く者は追わず来るものは拒まず」の意味を辞書で確認します。
往(ゆ)く者(もの)は追(お)わず来(く)る者(もの)は拒(こば)まず
《「孟子」尽心下から》立ち去る者はあえて引きとめず、道を求めてくる者は、だれでも受け入れる。去る者は追わず、来(きた)る者は拒まず。
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
「来るもの拒まず」は「どんな人でも受け入れる」、「去る者は追わず」は「自分から離れて行こうとする者は無理に引きとめない」の意味です。

「来るもの拒まず、去るもの追わず」言葉の由来と背景
「来るもの拒まず、去るもの追わず」は、古代中国の思想家である孟子(もうし)の教えが由来です。
孟子が記した『尽心下』には、「夫子設科也、往者不追、来者不拒」と記されています。これは「自分を信じて訪ねてくる者は受け入れるが、離れる者は追わない」という意味で、孟子の弟子を取る態度を表したものです。
つまり、「来るもの拒まず、去るもの追わず」は、人間関係で過剰な執着を持たないこと。そして、オープンな姿勢で人を受け入れることを教えてくれているのです。
参考:『故事俗信ことわざ大辞典』(小学館)
「来るもの拒まず、去るもの追わず」場面別の対応と人間関係の指針
「来るもの拒まず、去るもの追わず」の態度は、実際にどのようなものなのでしょうか? 仕事やプライベートでどういう態度を指すのか、例とともに紹介します。
ビジネスでの応用
退職や異動など節目の場面では、「来るもの拒まず、去るもの追わず」の精神を軸にしながらも、相手の決断を尊重する気持ちを伝えることが大切です。加えて、感謝と敬意を添えることで、誠実さが伝わりますよ。
応用例:「新しい挑戦を応援しています。必要なときはいつでもご連絡ください」
プライベートでの応用
恋愛や友人関係では、自立した姿勢は魅力的ですが、突き放す印象にならないよう配慮しましょう。「来るもの拒まず、去るもの追わず」の距離感を意識しながらも、相手への関心を示す一言を添えることで、穏やかな安心感が生まれます。
応用例:「今はお互いのペースを大事にしよう。気が向いたらまた声をかけてね」
「来るもの拒まず、去るもの追わず」の長所と短所を知っておく
「来るもの拒まず、去るもの追わず」が持つ長所と短所を整理し、職場の人間関係をより豊かにするバランスの取り方を考えてみましょう。
【長所】
人を無理に引き留めないため、関係のもつれや不要なトラブルを避けやすくなります。また、気持ちの切り替えが早くなり、依存しない自立した姿勢は、仕事でもプライベートでも魅力的に映ります。
【短所】
一方で短所としては、熱意が伝わりにくかったり、諦めが早く見えたりする点が挙げられます。特に、関係を深めたい相手に対しては「距離を置かれている」と感じさせてしまう危険もあります。
避けたい使い方とバランスの取り方
顧客対応や家族のケアなど、あなたからの主体的な支援が必要な場面で「来るもの拒まず、去るもの追わず」の態度は不適切です。この場合は「いつも気にかけています」「力になりたいと思っています」と伝える方が相手の安心と信頼につながるでしょう。
「来るもの拒まず、去るもの追わず」の距離感を実際の人間関係に生かすポイントは、相手の行動を尊重する気持ちを持ちながら、あなたからは感謝の気持ちを伝えることです。
また、距離をとった場合でも、温かい関心を示すことも大切。そうすることで、自然体でいながら誠実な人間関係を築けるのではないでしょうか?
「来るもの拒まず、去るもの追わず」の類語・対義語
ここでは「来るもの拒まず、去るもの追わず」に、似た意味を持つ言葉や、反対の姿勢を表す言葉を紹介します。それぞれの言葉が持つ心のありようを理解することで、日々の会話や人間関係の捉え方が深くなるかもしれません。
類語|「清濁(せいだく)併せ(あわせ)呑む(のむ)」
「清濁併せ呑む」とは、良いことも悪いことも、すべてをひっくるめて受け入れる器の大きさがあることを意味します。「度量が大きい」という意味で、「来るもの拒まず、去るもの追わず」と共通した点があるでしょう。
類語|「寛容(かんよう)」
「寛容」は他人の言動を、とがめたり責めたりせずに受け入れる態度のことです。相手の失敗を許したり、自分と違う考えの人にも耳を傾けたりできる心持ちを指します。
類語|「懐(ふところ)が深い(ふかい)」
人としての包容力があり、些細なことでは動じない様子を表すのが「懐が深い」 です。どんなタイプの人も安心して頼れるような、安心感のある人を表現するのにぴったりです。
対義語|「執着(しゅうちゃく)」
「来るもの拒まず、去るもの追わず」と反対に、一つのことに心を奪われ、手放せない状態を表す言葉が「執着」です。過去の恋愛を引きずってしまったり、一度失敗した仕事にいつまでもとらわれてしまったりする心のありようを指します。
この「執着」という言葉は、使い方を間違えると相手を否定しているように聞こえることもあります。不用意に使うのではなく、「このプロジェクトは、もう手放した方がよさそうだね」のように、具体的な行動に置き換えて話すと、相手を不快にさせずに伝えることができますよ。

「来るもの拒まず、去るもの追わず」英語表現と例文
「来るもの拒まず、去るもの追わず」を英語で伝えたい場面もありますよね。ここでは、ビジネスでも日常でも使える自然な表現と、SNSで気軽に使える短文を紹介します。
“welcome”
温かさが伝わる“welcome” を使った表現を見てみましょう。
例えば、次のような表現なら言葉の真意をストレートに伝えたいときにぴったり。知的で潔い印象を与えられます。
例文:“I welcome those who come, and I don’t chase those who leave.”
(私は来る人を受け入れ、去る人を追いかけません。)
“respect”
次に、知的でスマートな印象を与える“respect” を使った表現を見てみましょう。
例文:“Respect in, respect out.”
(来るときも去るときも尊重する。)
シンプルながらも深い意味が込められた、印象的なフレーズです。あなたの価値観をスマートに表現でき、座右の銘のように使うとクールな印象を与えられます。
例文:“I respect your decision and won’t push, but I’m here if you need me.”
(あなたの決断を尊重します。無理強いはしませんが、必要なときにはここにいます。)
この表現も相手の選択を尊重しつつ、温かい気持ちも伝えたいときに使えますよ。仕事で同僚が異動するときや、友人が転職するときなど、相手を思いやる気持ちが伝わります。
“door”
次に‟door”を使って表現する方法を見てください。
例文:“The door is always open. You’re welcome anytime.”
(扉はいつでも開いています。いつでも歓迎します。)
これは、「気が向いたら、また来てね」という気持ちを優しく伝えるフレーズです。相手を温かく迎え入れる、包容力のある人柄を表現できます。
次に、サクッと使えるSNS向けの短文がこちらです。
例文
“Doors open; no pressure.”
(扉は開いているよ。無理はしなくていいからね。)
よりカジュアルで軽やかな雰囲気で伝えたいときにぴったりです。相手にプレッシャーを与えない気遣いが感じることができる、親しみやすい表現です。

「来るもの拒まず、去るもの追わず」に関するFAQ
ここでは、「来るもの拒まず、去るもの追わず」に関するよくある疑問と回答をまとめました。参考にしてください。
Q1. ビジネスメールでそのまま使っても大丈夫ですか?
A. 直接使うと冷たい印象を与えてしまう可能性があります。
「意思を尊重します」「応援しています」といった補足を添えるのがおすすめです。
Q2. 恋愛で使うと「冷めている」と思われませんか?
A. その可能性はあります。
「追わない」という姿勢は潔い一方で、淡泊に見えることも。思いやりを示す一言を添えると安心感が伝わります。
Q3. NGな使い方はありますか?
A. はい。
顧客対応や家族のケアなど、積極的なフォローが必要な場面で使うと「無責任」と受け取られてしまうことがあります。責務が伴う関係では避けるのが無難でしょう。
最後に
「来るもの拒まず、去るもの追わず」は、人との関わりにおいて、頑張りすぎずに自然体でいるための大切なヒントをくれます。誰にでもオープンでありながら、自分自身の軸をしっかり持つことで、心にゆとりが生まれるのです。
ただし、この言葉を実践するうえで大切なのは、相手を尊重する気持ちを忘れないことです。必要なときには温かい一言を添える工夫で、この言葉が持つ魅力を最大限に生かせますよ。無理して付き合う関係ではなく、本当に心地いいと思える人間関係が残っていくよう、言葉の知恵を生活にも生かしてくださいね。
TOP画像/(c)Adobe stock