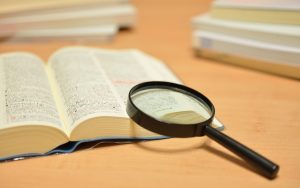日常ではあまり聞き慣れない言葉でも、特定の場面を的確に表す言葉があります。「掣肘(せいちゅう)」もその一つです。目の前の出来事を自由に進められない状況を表すこの言葉は、ビジネスや政治の場面で使われることが多いでしょう。意味や由来を知ることで、場面に応じた使い方が見えてくるかもしれませんよ。
「掣肘」とは? 意味や語源を知ろう
何かをしようとするとき、思うように進められないことがあります。「掣肘」は、そうした場面で使われる言葉です。意味や語源を確認していきましょう。

「掣肘」の読み方と意味
「掣肘」は、「せいちゅう」と読みます。」辞書で意味を確認しましょう。
せい‐ちゅう〔‐チウ〕【×掣▽肘】
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
[名](スル)《「呂氏春秋」審応覧・具備にある、宓子賤が二吏に字を書かせ、その肘(ひじ)を掣(ひ)いて妨げたという故事から》わきから干渉して人の自由な行動を妨げること。「―を加える」
「誰にも―せられることの無い身の上」〈鴎外・雁〉
「掣肘」とは、わきから干渉され、自由に行動できなくなる状況を指します。
「掣肘」の由来は?
「掣肘」は、宓子賤(ふくしせん)が二吏に字を書かせ、その肘(ひじ)を掣(ひ)いて妨げたという、中国の故事『呂氏春秋‐審応覧具備』に由来します。確かに肘をおさえられてしまったら、自由な行動はできなくなってしまいますね。
「掣肘」の使い方|どんな場面で使われる?
「掣肘」は、組織や人間関係の中で、自由に動けない状況を表すときに使われます。具体的な場面を例に挙げていきましょう。
「新しい企画が、上層部の掣肘を受けて進まなかった」
新しいアイデアを形にしようとしても、組織の意思決定により制限されることがあるでしょう。この場合、個人の意志ではなく、周囲の影響によって計画が進められないことを示しています。

「彼はチーム内で掣肘を受けることが多く、思うように動けなかった」
個人が自由に行動しようとしても、周囲の意見や方針によって制約を受けることがあります。特に、職場などの環境では、上下関係や役割によって判断が左右されることが少なくありません。
「掣肘を加えることで、組織のバランスを保つ」
この言葉は、他者の行動を制限する側の立場としても使われることがあります。自由な発想を尊重する一方で、組織の統制を維持するために必要な制約をかける場面で用いられることもあるでしょう。
「掣肘」の類語や言い換え表現
状況に応じて、適切な言葉を選ぶことで、表現の幅が広がるかもしれません。「掣肘」と似た意味を持つ言葉を見ていきましょう。
牽制(けんせい)
相手の行動を抑えるという意味で、「牽制」も近い表現です。ビジネスやスポーツなど、さまざまな場面で使われます。相手の自由な動きを妨げることで、一定の影響を与える状況で使うのに適しているでしょう。
例文:チーム内での競争が激しく、お互いを牽制しながら慎重に行動している。

制約(せいやく)
「掣肘」と同じように、自由な行動を制限する意味を持ちます。特にビジネスシーンでは、予算やルールの範囲内で行動しなければならない場面で使われることが多いでしょう。
例文:この仕事は時間の制約が厳しく、短期間で成果を出さなければならない。
束縛(そくばく)
自由を奪われる状況を表す言葉として、「束縛」も類語に含まれます。対人関係においても使われることがあり、制限を受ける側の心理的な負担を表現する際に用いられます。
例文:過去の経験に束縛されることなく、新しい挑戦をしてみたい。
最後に
「掣肘」という言葉は、何らかの制約を受け、自由に行動できない状況を表します。職場や社会の中では、自分の意志だけでは進められない場面があるかもしれません。状況に応じて適切な表現を選ぶことで、言葉のニュアンスをより正確に伝えられるでしょう。
TOP画像/(c) Adobe Stock