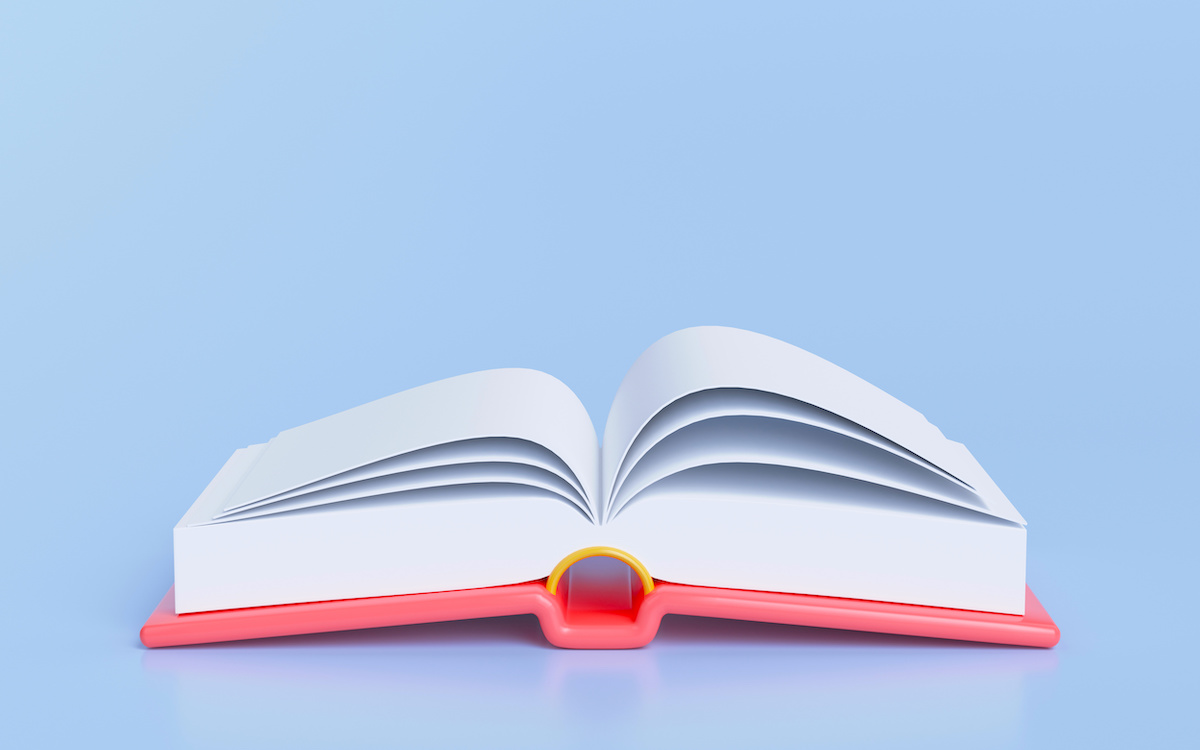御幸とは?
御幸とは、天皇が出かけることを、尊敬の意を込めて表現したものです。
ここでは、御幸の読み方や意味について解説します。
読み方や意味
御幸には、「ごこう」「ぎょこう」「みゆき」といった読み方があります。かつては、上皇・法皇・女院が外出する場合を「ごこう」と呼び、天皇は「ぎょうこう(行幸とも書く)」と音読して区別していました。
御幸は天皇が神社仏閣や地方などに出向くことに敬意を込めて表現した言葉であり、かつて天皇が訪れた場所は「御幸町(みゆきちょう)」「御幸通り(みゆきどおり)」といった地名が残されています。
ぎょ‐こう〔‐カウ〕【御幸】
出典:小学館 デジタル大辞泉
天皇が出かけること。行幸。みゆき。
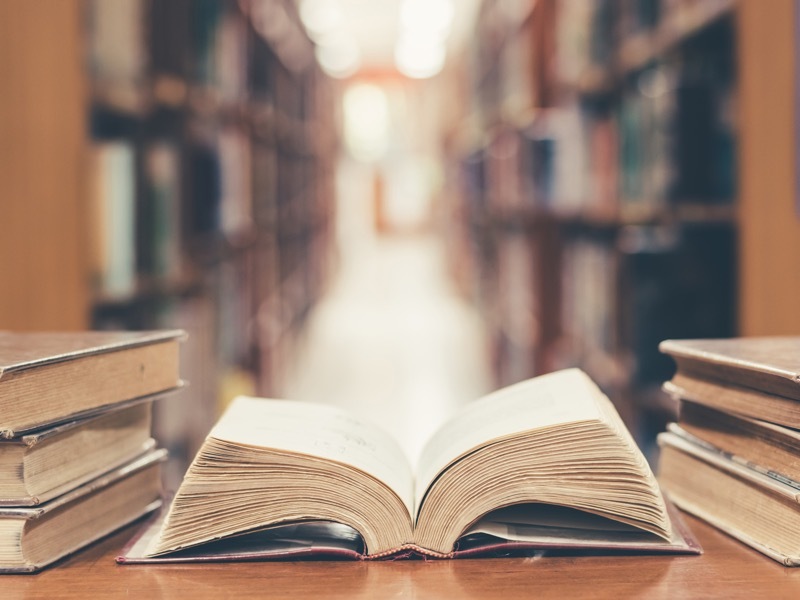
「行幸」との違い
御幸は「行幸」とも書き、「ぎょうこう」または「みゆき」と読みます。意味は御幸と同じです。「行幸」という言葉は、「天子の行く所、万民が恩恵に浴し、幸いを受けるので『幸』という」という古書の表現に由来しているようです。
また、訪問先が2か所以上にわたる場合には「巡幸(じゅんこう)」という言葉が使われ、天皇が訪問を終えて御所へ戻られる際には「還幸(かんこう)」と呼ばれます。これらはすべて、皇室の動静に関する特別な用語として、公式文書や報道などでも用いられています。
ぎょう‐こう〔ギヤウカウ〕【行幸】
出典:小学館 デジタル大辞泉
[名](スル)《「ぎょうごう」とも》天皇が外出すること。行く先が2か所以上にわたるときには巡幸という。みゆき。→行啓 (ぎょうけい)
「行啓」との違い
行啓(ぎょうけい)とは、皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃などの皇族が外出や訪問をされる際に用いられる言葉です。 これは、天皇の外出を意味する御幸とは明確に区別されており、皇室用語として格式を保ちながら使い分けられています。
この言葉は平安時代から用いられ、特に明治・大正期においては、皇太子が各地を巡って見学・視察により地域住民と交流を図る機会が増えたことから、「行啓」という言葉が広く一般にも知られるようになったようです。
今日でも皇室の動静を伝えるニュースなどでしばしば目にする用語であり、日本の伝統や皇室制度を理解するうえで、知っておきたい言葉のひとつといえるでしょう。
ぎょう‐けい〔ギヤウ‐〕【行啓】
出典:小学館 デジタル大辞泉
《古くは「ぎょうげい」とも》太皇太后・皇太后・皇后・皇太子・皇太子妃・皇太孫が外出すること。→行幸 (ぎょうこう)
御幸に関連する用語
天皇および皇族が外出したり戻られたりする際には、それぞれに応じた特有の表現が用いられます。これらの表現は皇室における慣習や格式を反映しており、公式行事や報道の中でも目にすることが多いものです。
ここでは、外出や帰還に関連する皇室特有の言い回しについて紹介します。
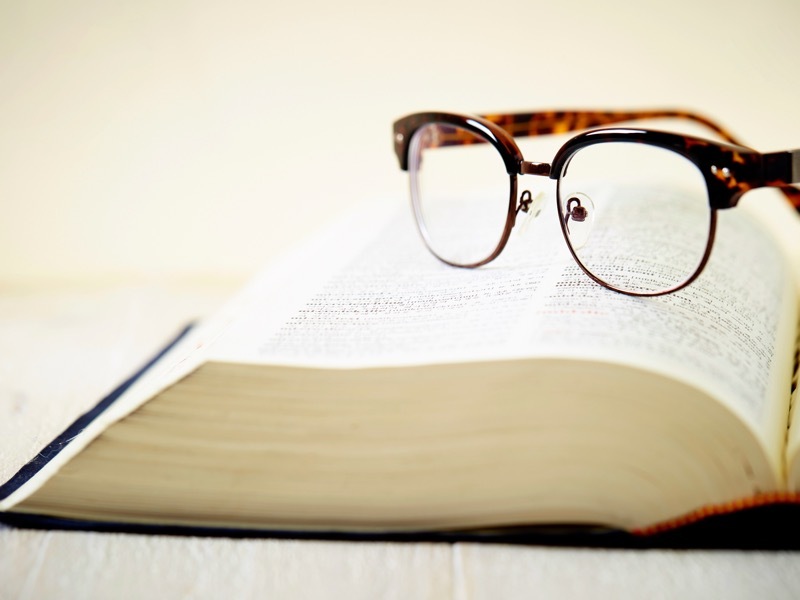
外出に関する用語
皇室関係で外出に関する用語は、次のとおりです。
・行幸(ぎょうこう):天皇が外出されること
・行啓(ぎょうけい):皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃が単独で外出されること
・行幸啓(ぎょうこうけい):天皇・皇后が一緒に外出されること
・お成り(おなり):皇族・摂家・将軍などの貴人を敬って、その外出や訪問・臨席を指す
これらの表現は、皇室関連のニュースや公式な報告書などでよく目にするもので、皇室の伝統と格式を感じさせる言葉といえます。特に「行幸」や「行啓」は、訪問先が儀礼的・公的な意味合いをもつ場面で使われることが多く、使用には一定の敬意が込められています。
帰還に関する用語
帰還に関する用語は、次のとおりです。
・還幸(かんこう):天皇が行幸先から帰ること
・還幸啓(かんこうけい):天皇・皇后が行幸啓先から帰ること
・還啓(かんけい):皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃が行啓先から帰ること
・ご帰還(ごきかん):天皇・皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃以外の皇族がお成り先から帰ること
「還」は「戻る」「帰る」という意味があり、行幸や行啓の対義語的に用いられます。たとえば、新聞記事や宮内庁の発表などで「天皇陛下は〇〇県へのご行幸を終え、午後に還幸されました」といった形式で使われます。
御幸にまつわる言葉
天皇の外出や訪問を指す御幸という言葉は、歴史的に重要な出来事や土地に深い関わりを持っており、地名などにもその名残が見られます。
ここでは、御幸という語が用いられている表現や地名についていくつか取り上げてみていきましょう。

御幸始め
御幸始め(ごこうはじめ)とは、上皇・法皇・女院が初めて御幸すること、あるいは新年に行われる最初の御幸を指す言葉です。また、新年に天皇が法皇や皇太后の邸を訪れて挨拶をする儀式「朝覲(ちょうきん)」としての御幸も含まれます。
御幸始めは、平安時代の文献『高倉院厳島御幸記』に「四日、よき日とて、御幸はじめあるべしとて」という言葉が残されています。
御幸の浜
「御幸の浜(ごこうのはま)」は、神奈川県小田原市にある地名で、明治天皇と皇后が滞在した際に海岸を訪れたことに由来しています。明治6年に天皇と皇后が漁夫の地引網をご覧になったことから「御幸の浜」と呼ばれるようになったようです。
現在も周辺地域には「御幸の浜通り商店街」などの名称が残っており、地域の歴史と伝統を感じることができるでしょう。
御幸山
愛知県名古屋市天白区に位置する御幸山(みゆきやま)は、明治天皇および大正天皇が当地を訪れたことにちなんで名付けられた地名です。
もとは「音聞山(おとぎきやま)」と呼ばれていましたが、明治・大正期の陸軍大演習の際に両天皇がこの地を視察地(御野立所)として利用したことを受け、記念および史跡としての保存を目的に「御幸山」と改称されました。
御幸の意味を正しく覚えよう
御幸とは、天皇の外出を意味する言葉です。「ごこう」「ぎょうこう」「みゆき」など複数の読み方があり、「行幸」と表記されることもあります。なお、天皇以外の皇族に対しては「行啓」や「行幸啓」といった別の表現が用いられます。外出だけでなく、帰還にもそれぞれ決まった言葉があるため、あわせて覚えておくとよいでしょう。
天皇が御幸された場所には、記念の地名として「御幸」の名が残されていることもあります。「御幸」と名のつく地名は、天皇や皇族の訪問に由来することが多いため、近くにそうした場所があれば、その由来をたどってみるのも興味深いでしょう。
メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock