目次Contents
この記事のサマリー
・「推敲」とは、文章をよりよくするために何度も練り直すことを意味する。
・唐代の詩人・賈島(かとう)と韓愈(かんゆ)の逸話から生まれた故事成語に由来する。
・「校正」は誤字脱字の修正、「推敲」は表現を磨く行為として区別される。
ビジネスメールや報告書を作成するときに「もっと分かりやすく表現できないかな?」と感じる場面は多いものです。筆者自身、研修で上司から「文章は必ず推敲(すいこう)しなさい」と指摘された経験があり、当時はその「推敲」の意味が分からず慌てて辞書を引いた記憶があります。
「推敲」とは、ただの「書き直し」ではなく、言葉を磨き上げる大切なプロセスです。本記事では、「推敲」の意味・由来から、実際の使い方、英語表現、推敲の効果と注意点までを網羅的に解説します。ぜひ最後までご覧ください。
「推敲」とは? 意味を確認
文章をよりよくするために欠かせないのが「推敲」というプロセスです。まずは、意味から確認していきましょう。
「推敲」の意味
推敲の意味は「文章の言葉や表現をよりよいものにするため、何度も練り直すこと」です。ここで注意したいのは、推敲が単なる誤字脱字の修正ではない点。
辞書では次のように説明されていますよ。
すい‐こう〔‐カウ〕【推×敲】
[名](スル)《唐の詩人賈島(かとう)が、「僧は推す月下の門」という自作の詩句について、「推す」を「敲(たた)く」とすべきかどうか思い迷ったすえ、韓愈(かんゆ)に問うて、「敲」の字に改めたという故事から》詩文の字句や文章を十分に吟味して練りなおすこと。「―を重ねる」「何度も―する」
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
「推敲」という言葉の由来
「推敲」という言葉は、実は中国・唐代の詩人、賈島(かとう)にまつわる逸話から生まれた故事成語です。詳しく見ていきましょう。
賈島と韓愈の逸話
「推敲」は、「苕渓漁隠叢話(ちょうけいぎょいんそうわ)」の故事によるものです。唐代の詩人・賈島が詩を作る際に「僧は月下の門を推す」とするか「僧は月下の門を敲(たた)く」とするかで悩んだという話です。
賈島はそのことを韓愈(かんゆ)に相談しました。韓愈は「敲(たたく)」の方がより情景に合っていると助言し、そこから「推敲」という言葉が「文章を練り直すこと」を意味するようになったのです。
参考:『故事俗信ことわざ大辞典』(小学館)

「推敲」と似た言葉との違い
「推敲」には似ているようで異なる言葉がいくつもあります。ここでは「校正」や「添削」「リライト」との違いを整理し、ビジネスシーンで誤用しないためのポイントを解説します。
「校正」との違い
「推敲」と「校正」はしばしば混同されますが、意味するところは異なります。「校正」とは、誤字脱字や文法の誤り、表記のゆれをチェックして修正する作業のことです。例えば「御社」と「貴社」を混在させないように整える、数字や日付の表記を確認する、といった作業が校正に当たります。
一方「推敲」は、文章そのものを練り直し、より自然で伝わりやすい形に整える行為のことです。
校正は「正しさ」を担保する作業、推敲は「質」を高める作業だと理解すると区別しやすいでしょう。
「添削」「リライト」との違いは?
推敲に近い表現として「添削」「リライト」があります。
「添削」は第三者が改め直すことを指し、先生や上司が部下の文章を直すときに多用されます。
一方、「リライト」は他人の原稿を書き直すことも指しますが、既存の文章を目的に合わせて書き直すことも指します。
「推敲」の使い⽅と例⽂集
「推敲」を使った例文をもとに、使い方をチェックしていきましょう。
「投稿する作品の推敲を重ねる」
「推敲」は「重ねる」とセットで用いられることが多いです。文章を「何度も何度も」練り直すことは、まるで文章をどんどん「重ねる」ようだといえるでしょう。
「この論文は、もう少し推敲する必要がある」
「推敲する」と動詞的に用いることも可能です。文章を何度も練り直し、修正することを意味します。他の用例として「書類を何度も推敲する」「推敲した自信作だ」などが挙げられますよ。
「この原稿はまだ推敲の余地がある」
「推敲」は「余地がある」と組み合わせて使われます。「推敲の余地」とは「推敲できる箇所」という意味です。反対に「推敲の余地がない」の場合は「もう推敲するところがない」「推敲し終わった」という意味になります。
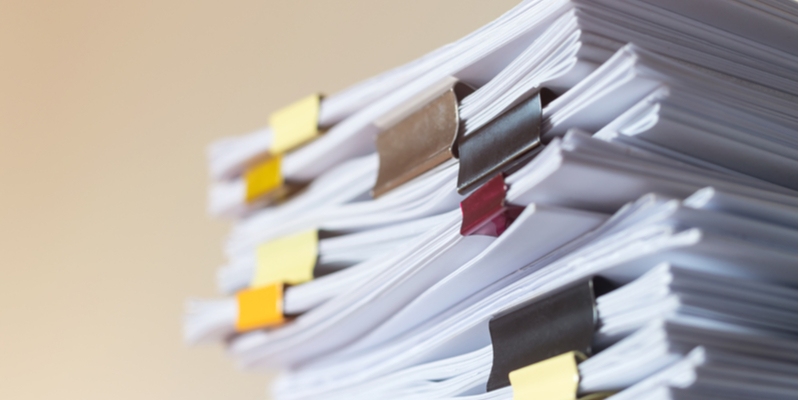
「推敲」の英語表現は?
「推敲」を英語で表現するなら、“refinement of sentences and paragraphs”が使えます。直訳すると、「文章や段落を洗練すること」。「推敲」と同じ意味を伝えることができますね。
参考:『ビジネス技術実用英語大辞典V6』(Project Pothos)
「推敲」を重ねる大切さと注意点
文章を仕上げる上で「推敲を重ねる」ことは欠かせません。初稿のままでは思い込みや表現の粗さが残り、伝えたいことが相手に正確に伝わらないことが多いからです。
筆者自身、報告書を一度提出した際、「読み手に意図が伝わりにくい」と上司に指摘され、推敲を加えたところ格段に理解されやすくなった経験があります。ただし、推敲には「やりすぎるリスク」もあり、バランス感覚が求められます。
推敲の効果
推敲を重ねると、文章は「読みやすさ」と「信頼性」が大きく向上します。例えば冗長な表現を削れば簡潔になり、文の主語と述語を整理すれば誤解を避けられます。また、語彙を整えることで相手に与える印象が柔らかくなり、配慮のあるコミュニケーションにつながります。
やりすぎに注意
一方で、推敲を繰り返しすぎると「終わりのない修正」に陥る危険があります。何度も書き直すうちに文章が冗長になったり、最初に伝えたかった核心がぼやけてしまうこともあるでしょう。
実務的には「3回程度を目安に見直す」「一晩寝かせて翌日に読む」といったルールを自分なりに設けるのが有効です。また、第三者に読んでもらいフィードバックを受けることで、主観的な迷いから抜け出すことができます。
推敲は「完成度を高めるための磨き」であり、完璧を追い求め続けることではありません。適度な区切りをつける判断力も、社会人にとって大切なスキルです。
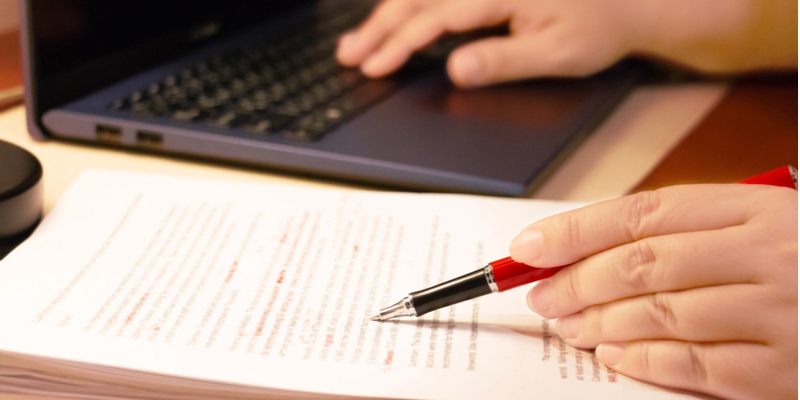
「推敲」に関するFAQ
ここでは、「推敲」に関するよくある疑問と回答をまとめました。参考にしてください。
Q1. 「推敲」と「校正」は同じ意味ですか?
A. 違います。
推敲は文章を練り直すこと、校正は誤字脱字や誤用を正すことです。文章の質を高めたいときは推敲、正確さを担保したいときは校正が必要になります。
Q2. ビジネスメールで「推敲」という言葉を使っても大丈夫?
A. 問題ありません。
ただし「推敲してください」では強すぎる印象になるため、「推敲いただけますでしょうか」というように丁寧なお願いをしましょう。
Q3. 推敲を繰り返すとどんな効果がありますか?
A. 読みやすさが増し、誤解や不快感を避けることができます。
最後に
「推敲」という言葉は、唐代の詩人・賈島の逸話から生まれ、現代まで大切に受け継がれてきました。
文章は、一度書いただけではなかなか相手に正しく伝わりません。推敲を重ねることで初めて、誤解のない、読み手に届く言葉になります。とはいえ「やりすぎないこと」も大切です。適度な見直しと工夫を心がけながら、あなたの文章をさらに洗練されたものへと磨き上げてください。
TOP画像/(c)Shutterstock.com























