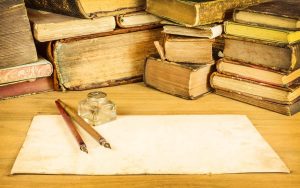抜山蓋世とは?
抜山蓋世は「ばつざんかいせい」と読み、並外れた力強さと圧倒的な気迫を備えた様子を表す言葉です。
ここでは、言葉の意味や語源、背景にある逸話などを解説します。
言葉の意味・成り立ち
抜山蓋世とは、圧倒的な力と気迫に満ちあふれ、勇ましく力強い様子を表す四字熟語です。
「抜山」とは、山をも根こそぎ引き抜くほどの強大な力を意味し、その力の大きさを強調しています。また「蓋世」は、世の中を覆い尽くすほどの手腕や気力を指しており、その影響力や存在感が大きいことを示しています。
おもに英雄や偉人の活躍、または圧倒的な勢いを持つものごとを称える際に用いられる言葉です。
ばつざん‐がいせい【抜山蓋世】
出典:小学館 デジタル大辞泉
《「史記」項羽本紀から》山を抜き取るほどの力と、世をおおいつくすほどの気力があること。英雄豪傑の力と意気の形容。力山を抜き気は山を蓋う。
抜山蓋世の由来
抜山蓋世は、中国の歴史書「史記・項羽本紀」に登場する「力は山を抜き、気は世を蓋う」という詩に由来しています。「自分には山を抜き取る力と世を覆い尽くす気力がある」という意味です。
楚の武将である項羽(こうう)が天下を争った漢の劉邦(りゅうほう)の軍に包囲され、寵愛した虞美人(ぐびじん)との最後の酒宴を開いた際に、自らを奮い立たせるために詠んだ詩と伝えられています。
抜山蓋世の使い方・例文
抜山蓋世を実際に会話や文章でどのように使うのか、例文を確認していきましょう。
・彼は抜山蓋世の勢いでプロジェクトを推進し、社内外から高い評価を受けた
・彼女の抜山蓋世の決断力が、会社の危機を救ったといっても過言ではない
・A社は創業から抜山蓋世の勢いで新しい事業を展開し、次々と成功させている
・彼は抜山蓋世の気概を持って会社を起業し、今でも挑戦を続けている
・新しい社長は抜山蓋世の勢いで改革を進め、わずか1年で業績を回復させた
・抜山蓋世の意気込みで挑んだ今回の営業戦略は、結果的に売上を大きく伸ばすことにつながった
・新規事業の立ち上げにあたり、社長は抜山蓋世の気迫で社員たちを鼓舞した

抜山蓋世の類義語・言い換え表現
抜山蓋世には、次のような類義語や言い換え表現が挙げられます。
・威風堂々(いふうどうどう)
・意気軒昂(いきけんこう)
どちらも、抜山蓋世と同じく、勢いがあって気力に溢れていることを指す言葉です。言葉の意味や例文を紹介します。
威風堂々
威風堂々とは、態度や立ち居振る舞いに威厳が感じられ、見る人に堂々として立派な印象を与える様子を表す言葉です。
「威風」は威厳を備えた風格を、「堂々」は落ち着きがあり自信に満ちた様子を意味します。これらの似た意味を持つ語を重ねることで、堂々とした印象をより強調しています。
〈例文〉
・彼女は会議で威風堂々と発言し、参加者の賛同を得た
・入社式で彼は威風堂々とした様子で壇上に立ち、答辞を述べた
意気軒昂
意気軒昂とは、意気込みが盛んで元気があり、威勢のよい様子を表す言葉です。「意気」とは、事をやり遂げようとする積極的な気持ちや気概のことで、「軒昂」は気持ちが高ぶり奮い立つ様子を意味します。
活力や勢いのある状態を表す点で、「抜山蓋世」とも共通するニュアンスを持つといえる言葉です。
〈例文〉
・新規プロジェクトの発足にあたり、チーム全体が意気軒昂としていた
・社長の激励スピーチを受け、社員は意気軒昂な様子で各部署へと戻っていった
▼あわせて読みたい
抜山蓋世の対義語
抜山蓋世とは対照的な意味をもつ言葉に「意気消沈(いきしょうちん)」が挙げられます。これは、やる気や気力が著しく低下し、気持ちが沈んでしまった状態を表します。
「意気」とは、物事に立ち向かおうとする強い意志や活力を指し、「消沈」はそれが静まり、失われることを意味します。つまり、意気消沈は、気力を失って落ち込んでいる様子を表す表現です。
〈例文〉
・企画案が却下され、チーム全体が意気消沈していたが、すぐに気持ちを切り替えて新しい案の検討に入った
・今月の売上が予想を大きく下回り、営業部のメンバーは意気消沈した

抜山蓋世に関連する言葉
抜山蓋世の由来となった中国の歴史書である「史記」には、ほかにも四面楚歌(しめんそか)や背水の陣(はいすいのじん)など、有名な四字熟語を生み出しているとされます。
ここでは、抜山蓋世に関連する言葉を紹介します。
四面楚歌
四面楚歌とは、周囲がすべて敵や反対者となり、完全に孤立して味方がいない状態を指します。抜山蓋世と同じく「史記」の「項羽本紀」に登場する言葉で、楚の項羽が漢の劉邦率いる軍に包囲され、砦に立てこもった際の出来事が由来とされています。
項羽は四方から敵軍に囲まれ、さらに楚の歌が聞こえてきたことで、自軍の兵までが敵に取り込まれたと感じ、驚きと絶望に打ちひしがれたといわれます。
〈例文〉
・彼が出した改革案に賛同者はおらず、会議では反対意見ばかりで、彼は四面楚歌の状態に追い込まれた
・競合他社が攻勢を強め、社内の協力も得られず、経営陣は四面楚歌の危機感を抱いている
▼あわせて読みたい
背水の陣
背水の陣とは、切羽詰まった状況で、一歩もあとには引けないぎりぎりの状態を指します。そのような状況に自ら身を置き、必死に物事に取り組む様子を表す言葉です。
背水の陣は、中国の歴史書「史記」の「淮陰侯伝(わいいんこうでん)」に登場します。漢の名将・韓信(かんしん)は、趙(ちょう)との決戦の際、わざと川を背にした陣を敷き、退却できない状況を作りました。自軍に決死の覚悟を促し、その結果、大勝利をおさめたという故事が由来の四字熟語です。
〈例文〉
・今期の売上目標を達成するため、社員は背水の陣で新たなプロジェクトに取り組んでいる
・絶対に契約を勝ち取らなければならず、今回のプレゼンは我が社にとって背水の陣である
▼あわせて読みたい
抜山蓋世の正しい意味を理解しよう
抜山蓋世とは、強い力と世を圧倒するほどの気迫を備えた、勇壮な様子を表す四字熟語です。中国の歴史書に由来し、「山を引き抜くほどの力(抜山)」と「天下を覆い尽くすほどの気力(蓋世)」という意味から成り立っています。
類義語には「威風堂々」や「意気軒昂」が、対義語には「意気消沈」が挙げられます。抜山蓋世とあわせて押さえ、シーンによって使い分けましょう。
メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock