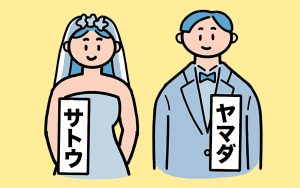命を迎え入れる前に考えたい、大切なこと
「エサは何をあげよう?」「家に早く帰らなきゃ」など、常に気にかけるべきペットの存在は生活を豊かにしてくれます。でも、ペットを迎え入れることは簡単なことではありません。飼う前の心構えは? どこで出会える? 病院に連れていくタイミングは? 知っておきたい、ペットとの暮らしに必要なこと。
今回の先生は…

▲田園調布動物病院院長、獣医学博士・田向健一さん
1973年、愛知県生まれ。幼いころから動物が大好きで、これまで治療した動物は100種類以上。著書に『生き物と向き合う仕事』(筑摩書房)『珍獣ドクターのドタバタ診察日記』(ポプラ社)など。
ペットとの理想の関係は? 動物本来の習性を理解して
Oggi編集部(以下Oggi):最近、知人がモモンガを飼い始めたんです。SNSでもウサギや子猫のかわいいペット動画が流れてきて、仕事の疲れも忘れてずーっと眺めちゃいます。
田向さん(以下敬称略):生き物はいいですよね。僕も子供のころからイグアナやウシガエル、ヤモリ、猫などさまざまなペットを飼ってきました。ペットがいると、毎日に張り合いが出て楽しいですよ。
Oggi:ペットとの暮らしには憧れつつ、実際に飼うとなると仕事も忙しいし、いろいろ不安が…。
田向:確かに、生き物を育てるということは簡単なことではありません。散歩や日々の世話など、さまざまな責任が伴いますし、鳴き声や足音などで近隣トラブルになることも。そんな認識が広まって、一時期ペットの飼育頭数が減った時期もあったんですよ。でもコロナ禍に自宅で過ごす時間が増えたのをきっかけに、またペット人気が盛り返しています。
Oggi:友人もコロナ禍に、室内犬を飼い始めました。
田向:ペットを迎え入れるうえでまず大切なのは、〝自分と相性のいい動物〟を選ぶこと。「この動物を飼いたい!」と心に決めている人もいるかもしれませんが、今は、ペットとして飼育される動物の種類も豊富。自分の性格や働き方、ライフスタイルをふまえつつ、ペットとどんな関係を築いて、どんな暮らしがしたいのか。その理想に適した習性を持つ動物を選ぶことが大切です。
Oggi:というと?
田向:たとえば犬猫は、毎日触れ合って一緒に遊びたいという人や在宅勤務などで家にいる時間が長い人におすすめ。特に犬は散歩や触れ合いなど飼い主とのコミュニケーションの時間が大好きで、構ってもらえないとストレスを溜めてしまうので、人間の子供を育てるのと同じくらいの覚悟が必要ですね。残業や会食が多い人は難しいかも。猫もクールなようで甘えたがりなので、ちゃんと構ってあげてほしいです。
Oggi:飲み会やデートも、頻繁には行けませんね(苦笑)。観葉植物もすぐに枯らしてしまう私には、ちょっとハードルが高そう…。
田向:その点、ウサギ、フェレット、ハリネズミなどの小動物は、働いているひとり暮らしの人でも比較的飼いやすいですよ。鳴き声やにおいも少なく、散歩の必要もないですし、犬猫ほど密接なコミュニケーションを求めません。
Oggi:「ウサギはさみしいと死んじゃう」のでは?
田向:科学的根拠はありません(笑)。単独行動をする生き物なので、基本的に1匹でも平気なんです。鳥のように本来集団生活をする動物のほうが、実はさみしがり屋。また、「美しい生き物をひたすら眺めていたい」「ただ同じ空間に生き物の気配があればいい」などドライな関係を求める人には、トカゲ、ヘビ、カメなどの爬虫類、カエルなどの両生類がおすすめ。人間との歴史のなかで家畜化された犬や猫とは異なり、触られることにあまり慣れていないので、ある程度の距離感を持って暮らせます。
Oggi:そういえば、知り合いが飼っているカメは、一年のうち半分は土の中で冬眠していて、会えるのは半年だけだとか。ペットとのつきあい方は人それぞれなんだと驚きました。
田向:はい。ベタベタしたいのか、ドライにいきたいのか。〝自分が望む関係〟と〝動物本来の習性〟とのマッチングを間違えてしまうと、お互い不幸になってしまうので、ここはじっくり見極めたいところ。とはいえ、同じウサギでもすぐに抱っこさせてくれる子もいれば、いつまでたっても触られるのをいやがる子もいるなど、性格には個体差もあります。ペットショップでもある程度個体ごとの気質は把握していますが、飼い主との相性は、正直飼ってみないとわかりません。
働く女性でも比較的お世話しやすいペットは?
ウサギ
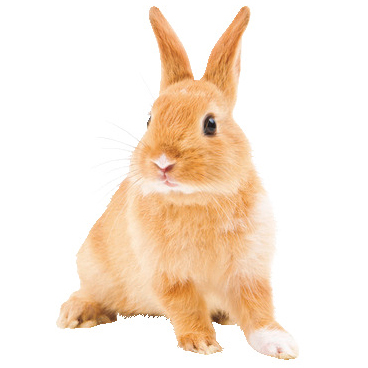
長い耳と丸いしっぽ、愛らしいしぐさが特徴。ちょっとしたストレスで体調を崩しやすいデリケートな一面も。
ヘビ

エサやりは週1〜2回とお世話は比較的ラク。脱皮を繰り返し成長する姿や冷凍マウスを飲み込む姿は圧巻。
フェレット

胴長短足の体型がキュート。性格は人懐っこく好奇心旺盛。早朝と夕暮れに活動し、一日の大半は寝て過ごす。
チンチラ

ふわふわの毛と愛らしいしぐさで人気上昇中。アンデス山脈の高地に生息するため、高温多湿に弱く、エアコン必須。
トカゲ

恐竜のようなルックスで観賞用として人気。鳴かず、においも少ないためペット初心者でもお世話しやすい。
ペットとの出会いはどこで? 迎え入れる準備は?
Oggi:飼いたい動物が決まったとして、どこで動物たちと出会えばいいのでしょうか。
田向:街のペットショップのほか、ホームセンターのペット売り場でもさまざまなペットを販売しています。ネットで直接ブリーダーを見つけて、やり取りする人も増えています。飼い主のいない保護犬猫の里親を募るサイトや譲渡会を通して引き取るという手も。また、一緒の時間を過ごして、気に入った犬や猫をペットとして迎え入れられるペットカフェや、ペット業者が一堂に会すペットフェアにも出会いのチャンスがあります。
Oggi:いろいろな選択肢があるんですね。
田向:実は10年ほど前までは、ハムスターなどの小さいペットは通信販売でも売買されていたんですが、2013年の動物愛護管理法の改正で、今は禁止されています。
Oggi:実際に会って、詳しく説明を受けておきたいですね。では、ペットを迎える前に準備しておくべきことは?
田向:まず、住環境を整えること。ケージやトイレはもちろん、忘れてはいけないのが空調。動物は、暑すぎたり寒すぎたりする空間では体調を崩してしまいます。夏や冬は、出かけている間も24時間エアコンをつけておく心づもりで。特に爬虫類や両生類などの変温動物は専用のヒーターなどを設置して、生息地域の環境になるべく近づけてあげましょう。
Oggi:ケージにヒーターに… 出費がかさみますね(汗)。
田向:動物にもよりますが、設備などの初期費用は3万〜5万円ほど見ておきましょう。また、いざというときのために、近所の動物病院を探したり、去勢・避妊を検討したりすることも大切。犬猫以外のペットを診てくれる病院は意外と少ないので、ペットショップやブリーダーさんに近場のおすすめを聞いてみるのもいいですね。
Oggi:旅行や出張などで家を空けるとき、気をつけることはありますか?
田向:泊まりで家を空ける場合は、知り合いやペットシッターさんにエサやりやトイレ掃除をお願いするのが安心。ペットホテルに預けるという手もありますが、ペットによっては環境が変わるとストレスになってしまうこともあるので注意して。ヘビやトカゲは水さえあれば4〜5日エサを食べなくても平気なので、短い出張なら自宅のお留守番で大丈夫でしょう。
思わぬ事故や脱走のリスクも… 留守番させるときに気をつけたいことは?
特に小動物や爬虫類は脱走して行方不明になってしまうこともあるため、ケージの戸締まりは厳重に。

「閉じ込めてはかわいそう、とペットを部屋に放し飼いにする人もいますが、ゴミ箱を漁って危険なものを口にしてしまったり、家具を倒してしまったりと、思わぬ事故につながることも。飼い主の留守中はケージやサークルに入れておくのが安心です」(田向さん)
病院に連れていくサインは? 責任と覚悟を持ってお世話を
Oggi:ペットが不調のとき、病院に連れていくべきタイミングは、どう見極めたら?
田向:少しでも不安を感じたら受診することをおすすめします。動物は言葉を話せないので、「最近エサをあまり食べないな」「なんとなく元気がないな」と飼い主さんが気づいたときには、すでに相当症状が進んでしまっている可能性が。特に小さい動物は、ちょっとした体調不調でも命に関わることもあり、早めの対応を心がけたいですね。
Oggi:毎日ちゃんと観察していないと気づけませんね。
田向:特に最近は、SNSでかわいいペットを見て「私も!」と衝動的に飼い始める人が増えた気がしています。十分な知識を持たないまま、ネットで拾った情報で、間違った飼育を続けてペットを弱らせてしまうケースも…。
Oggi:胸が痛いですね。
田向:ペットも私たちと同じ生き物です。寒さや怖さも感じるし、病気もするし、寿命がくれば死ぬ。パソコンや車のように「壊れたら買い換えればいい」というものではありません。ちゃんと最後まで面倒を見る責任と覚悟を持って飼い始めてほしいですね。
Oggi:ペットロスがつらくて、もうペットは飼えない、という人もいます。ペットの死とはどう向き合えばいいのでしょう?
田向:長く連れ添ったペットは大切な家族。いなくなってしまう悲しみは、はかりしれません。飼い主さんの中には「私がもっと早く不調に気づいてあげていれば」「私のせいでこうなってしまった」と自分を責めてしまう方もいます。けれど、たいていの場合、ペットは飼い主より先に年老いて、先に旅立っていくもの。病気になって弱っていくのも、自然の摂理なんです。「僕が飼っていたとしても、同じようになっていたと思います」とお伝えしています。人間より寿命が短い彼らは、〝命には終わりがある〟ということを、身をもって教えてくれる存在。逆説的ですが、飼い始める前から〝終わり〟を意識すると、ペットとの〝今〟をより大切にできるのではないでしょうか。
Oggi:限られた時間を精一杯味わって、元気なうちに思い出をたくさんつくるようにしたいですね。
田向:目の前の生き物と向き合って、お世話をしたり触れ合ったりすることは、日々の生活をぐっと豊かにしてくれます。機会があればぜひ家族の一員としてペットを迎え入れてみてください!
いざというときの治療費、10割負担で大丈夫? ペット保険は入るべき?
ペットの治療費は全額自己負担。1回の治療や手術で数万円単位のお金が飛んでいくことも…。保険料は基本的に掛け捨てで、ペットの種類やサイズ、年齢などによって金額が異なる。複数のプランを比較検討してみて。

「急なケガや病気に備えて保険に入っておくと安心。犬猫だけでなく、ウサギやハムスターなどの小動物、鳥類や爬虫類を対象にしたプランも」(田向さん)
覚えておきたいキーワード
ペットに関連するワードや知っておきたいワードをピックアップ!
保護犬猫

飼育放棄や迷子、虐待などさまざまな理由で保健所や民間団体に保護された犬や猫のこと。譲渡会や里親探しサイトなどで新しい飼い主を募集し、殺処分を減らすための選択肢のひとつとして広まっている。犬猫以外を扱う団体も。
動物愛護管理法
人と動物が共生できる社会を目指し、飼い主の責任や動物取扱業者の規制を定めた法律。虐待禁止、危険動物の飼育規制、対面販売の義務化など、動物の習性を踏まえた適正な飼育や取り扱いを求める。
去勢・避妊
近年では、望まない妊娠を防ぐ目的より、発情期特有の尿のマーキングや〝発情鳴き〟などを抑える目的で行うケースがほとんど。高齢になった際の生殖器系の病気を予防できるというメリットも。
ペットシッター

飼い主に代わって自宅でペットの世話をするサービス。食事や散歩、トイレの世話などのほか、トレーニングや介護、リハビリに対応することも。依頼の際は、事前に打ち合わせを行い、ペットの性格や生活リズムを伝える。
※掲載している情報は2025年2月10日現在のものです。
TOP画像/(c)Adobe Stock
2025年Oggi4月号「Oggi大学」より
構成/中村茉莉花、酒井亜希子(スタッフ・オン)
再構成/Oggi.jp編集部