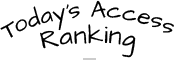ワークライフバランス、とひと言で言うけれど、本当にバランスをとりながら生きていくのはむずかしい。今を生きる女性にとって「キャリア」って何だろう? この連載では「都心で働くアラサーしごとなでしこ」の仕事人生に迫ります。今回は、パラリンピックのサポートセンターに勤務する、前田有香さんにお話を伺いました。
特別支援学校の教員から大学院、研究員などを経て、パラリンピックサポートセンターへ

前田有香さん(30歳)
公益財団法人 日本財団パラリンピックサポートセンター
推進戦略部 プロジェクトリーダー
立教大学文学部教育学科を卒業、新卒で神奈川県立特別支援学校(知的障がい・肢体不自由)の教員に。3年で退職して立教大学大学院文学研究科に入学、社会人大学院生となる。博士課程後期課程在籍中に、共栄大学教職アカデミー特別研究員、日本財団パラリンピック研究会研究員などを経て、2015年より現職に。
Q現在の仕事内容を教えてください
パラリンピック競技団体の自立支援が主な仕事です。パラリンピックの正式競技である31の競技団体(※)が、2021年以降も自立した活動が続けられるように、広報やマーケティング、普及活動、人材育成等に関する助成事業やスタッフ向けのセミナーの実施など、さまざまなプロジェクトを同時に走らせている感じです。センターには約20名のスタッフがいますが、競技団体支援の専従は3人。私は11団体のサポートを担当しています。
なぜ自立支援が必要かというと、もともとパラスポーツの競技団体はボランティア組織であることが多く、法人としての運営が困難な場合が多いんですね。どうやってスポンサーを獲得し、選手数を増やしたり、ファン層を拡大したりしていくのかなど、課題解決のアドバイスは多方面からするようにしています。
私自身、初めて経験することばかりで、中小企業の自立運営の参考書や、ひとり社長(社員が社長ひとりの会社の社長)さんの本などを読んで、日々勉強しています。合宿や遠征には国の税金が使われるだけに経理がしっかりしていることも大切で、きちんとチェックできるようになるために、最近簿記3級の本も買ったりしました。
いちばん大変なのは、マネージメントの部分ですね。今は助成金ありきの支援ができますが、パラサポの支援は2021年までで終了なんです。予算を使っても収益0円の事業ばかり立ち上がってしまわないように、助言しなければならない場合も。何か正解なのかがわからない中、ときにはトライアンドエラーしながら導くときもあり、プレッシャーや難しさを感じることもたくさんあります。
Q今の仕事を選んだきっかけは何でしたか?
小学校時代は教師に憧れていました。でも、大学時代のボランティアで障がい児と接する機会があって、彼らの純粋さや素直さに惹かれたんです。これまで私はどちらかというと優等生タイプできたので、何かひとつでもうまくいかないことがあると、そこで立ち止まったり、悩むことも多かったんですね。ところが、彼らはできないことがあっても、そのまんまの自分らしさで存在している。教えてもらうことがたくさんあるなと感じたんです。

いざ特別支援学校で勤務してみたら、この仕事は自分にとって天職だと思えました。でも、学校で教えるボールペンの組み立て作業やパンづくりは、社会に出てもなかなか工賃としてつながらないという厳しい現実に直面。学校で能力を高めても、社会に受け皿がないんです。これは社会が柔軟になったほうがいいな、どうしたら社会を変えられるかなと考え、特別支援教育における職業教育の勉強をしようと、教師を辞めて大学院に入学しました。これが今の仕事につながる大きな分岐点になりました。
大学院時代は、どうしたら彼らが社会に受け入れられるかを模索しましたが、職業だけではだめかもしれないという考えにいきついて。たとえば音楽やスポーツ、ファッションとか、学校以外で彼らが社会と接点がもてる“ハブ”になるものを探したらどうだろうかと。その中でパラスポーツに出合ったんです。
気づけば2020年の東京オリンピック・パラリンピックが決定し、それを機にパラスポーツ研究のため「日本財団パラリンピック研究会」に研究員として参画するようになりました。そんな中、パラサポセンターの常務から仕事のお声がかかったのが、現職についたきっかけです。団体のビジョンが“インクルーシブ社会(多様性を認めあう社会)の実現”だったので、私も「まさにこれだ!」と直感しました。
常務にはいまだに言われるんですよ、「パラリンピックのオタクだったから採用した」って。実際、まさにオタク採用かもしれません(笑)。障がいのある選手が体育館での練習中に感じるアクセシビリティの研究をしながら、ウィルチェアラグビーの追っかけもしていたので、そのあたりが評価されたんじゃないでしょうか。
いちばん最初にハマったパラスポーツが、ウィルチェアーラグビーなんです。単純に、カッコいいんですよ。選手たちは頸椎損傷を抱える場合も多く、試合中にガチンコでぶつかって車いすごとひっくり返っても自分では立ち上がれません。なのに、彼らは数々のハードルを乗り越え、競技を純粋に楽しんでいるんだと気づいたとき、またひとつ、そこに可能性を感じました。「なんで私はいちいち、あれできない、これできないと落ち込んでいたんだっけ…」という自分自身の気づきにもつながりました。
リア充になれない自分を励ましてくれたのがパラスポーツだった
ちょうど、当時20代女子として社会から求められるものに応えられない自分に、どこか負い目を感じていたというか。リア充が流行る中、リア充ブームにのりきれない自分がいたんです。フォトジェニックな写真を撮ってインスタに上げるのは「全然楽しそうに思えない」けれど、それにのりきれていない自分は女子としてダメなんじゃないか。みたいなモヤモヤを勝手に感じて、勝手に落ち込んでいたんですよね。
でも、ウィルチェアーラグビーを応援する中で、誰かの価値観に合わない自分を気にしなくてもいいということを教えてもらったような気がしたんです。自分にできることを最大限楽しむ選手たちの姿に励まされた。それはほかの競技も同じで、たとえば“自分は見えないからこそ、耳を使ってゴールボールをやっているんだ”という選手の方がおられたり。日々、尊敬の念で仕事をしています。
Q 密かにあたためている「夢」について教えてください
『マツコの知らない世界』で、イケメンパラアスリートの紹介をすること(笑)。
マツコさんは、社会課題に対して関心が高い方。発言にインパクトがありますし、マツコさんにパラアスリートに「イケメン!」と太鼓判を押していただけたら、一般の方にももっとパラスポーツのことを知ってもらえるかなと。
個人的な夢は、今の組織は2021年までの“時限組織”なので、東京パラリンピック後もパラスポーツに関わっていけたらなと思っています。2020年以降も自分が必要だと言ってもらえるように、今をがんばります。
Qズバリ、あなたにとって、仕事とは?
仕事があるからこそ、自分らしくいられるんだと思っています。大学院を退学して仕事だけに軸足を置くようになってからは、プライベートな時間とのオンとオフをしっかりつけられるようになりましたし、パフォーマンスもあがった実感があります。
大学院は去年の3月に退学しました。教授は「現場経験を活かして論文を書け」と応援してくれ、私もパラスポーツ研究の論文を書きたいという欲求がありましたが、でも論文を書く時間をとることが物理的に難しいという苛立ちがありました。そこにストレスを感じるのは、エネルギーのムダ使いをしているのと同じような気がして、学校をやめたら、すごくすっきりしました。退路を断ったのが良かったんですね。2020年が終わったら戻ればいいのではなく、今、この仕事に専念して成功させるんだという目標が明確になったことで、動きやすくなったんです。

それ以降、健康にも留意するようになりました。発酵玄米にこだわったり、オーガニックのハーブティを飲んでみたり。職場の人に誘われて、ゴルフも始めました。週2回、朝7時から1時間、会社近くのゴルフ場で練習してます。朝5時半に起きて7時から体を動かすと、9時にはちょうどいい形でスタートがきれるんです。ほかにも2020年にそなえて、英会話教室に通い出しました。パラスポーツの話題で会話できるのが楽しいですね。
気づけば、24時間パラリンピックにつながる何かをしているんですよね。もう仕事というよりは、趣味の延長のような感じです。ほかのことを考えていても、いつのまにか自然にパラリンピックに戻ってくるんですよ。
今は、この1年間企画を温めていた“障がいのある方もない方も、自分に合うパラスポーツがみつかるマッチングサイト”づくりのプロジェクトが軌道に乗り始めたところで、「このサイトがハブになって、何かが変えられるかもしれない!?」とワクワクしているところです。毎日ハードな日が続いてもワクワク感がパワーになって、がんばれているのかもしれません。
※2016年のリオパラリンピック、2018年の平昌パラリンピック、2020年の東京パラリンピックの正式競技における競技団体は計31。
撮影/豊田亮 取材/谷畑まゆみ
初出:しごとなでしこ
谷畑まゆみ フリーランスエディター
編集プロダクションで女性誌編集者としてキャリアをスタート。Oggi、Domani、Preciousなどで読み物企画を担当。働くこと、産むことにまつわる30代女性の本音を掘り下げる連載を担当して以来、「女性の生き方」企画がライフワークに。
心理学を学ぶために40代で会社を離れて大学院へ。目白大学大学院心理学研究科にて「30代女性の主観的幸福感」について論文を執筆。修了後はキャリアコンサルタントや産業カウンセラー資格を取得し、心理学の知識をもつエディターとして始動。現在は女性誌やWebメディアでの編集・執筆に加えて、国際NGO法人のオウンドメディアにおける編集コンサルティングのほか、心理援助職としても活動中。