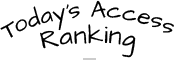――吉高さんは、蓬莱さんの作品のファンだそうですが、蓬莱作品のどんなところに魅力を感じていますか?
吉高:ちゃんと傷つくところ、ですね。自分の中で慣れてしまっていた感覚を呼び戻されるというか、「あ、そうだった」とハッとさせられる瞬間があるんです。気づかされる部分が多くて、私にとってはすごく魅力的な刺激です。

――今回の舞台は「他人のお別れの会に出席して、ビュッフェを食べる」という設定です。蓬莱さんはどういうきっかけでこの設定を思いつかれたのでしょうか。
蓬莱: お別れの会に「毎回なぜか来て、食べていく人がいる」という話を聞いたんです。「そんな人がいるんだ」と思ったのと同時に、もしその人が通い続けるうちに、ある日それが“自分の知人のお別れの会”だったのに、自分は呼ばれていない、と気づいたらどうなるんだろう、と思ったのがきっかけです。
「他人のお別れの会に出席して、ビュッフェを食べる」という行動そのものには闇があるけれど、「そうせざるを得ない」心の状態って、現代社会の隙間に確かに存在している気がしていて。そこから物語が広がっていくんじゃないか、と思ったんです。
吉高: プロットを読んだときは、「人のお別れの会って、そんな簡単に入れるの?」と思いました。しかも、ビュッフェがずらっと並んでいるようなお別れの会は、行ったことがなくて。
私、同級生が亡くなったときに、そこまで仲が良かったわけではないけれど、お葬式に参加したことがあるんです。思い出も少ないし、話した回数も数えるほどなのに、なぜか涙が出てきて。悲しいというより、すごく奇妙な感覚でした。目の前には“肉体だけがある”という現実があって、でも生きていた実感も確かにある。「もういない」と言われるのに、肉体同士が対峙している。その不思議さに戸惑ったのかもしれません。
蓬莱さんの作品って、意図していなくても、忘れていた感覚をいきなり呼び起こされるところがあると思います。それって、もしかしたら「無意識の暴力」みたいなものも含んでいるのかな、と感じました。

――蓬莱さんは、吉高さんを主演に迎えると決まったとき、作品や人物の描き方に変化はありましたか?
蓬莱: 吉高さんは、非常に素直な芝居をされる方だという印象がずっとあります。それが魅力です。
ただ今回の役は、どこか“人に迷惑をかけてしまう人”にしたいという思いがあって。本人に悪意はないまま、「よかれと思って」発言してしまうような、それこそ「無意識の暴力」を内包している人物です。いわゆる「いい人」では片づけられない側面ですね。端から見れば「いい人」にも見えるけれど、ある人にとっては被害を受けている、ということもある。そういう部分に無頓着でいる人物像が、面白く立ち上がるんじゃないかと思いました。
――「無意識の暴力」という言葉が印象的です。本作でも描かれる女性同士の関係にも通じる部分があるように感じたのですが、その点についてどう思われますか?
蓬莱:母親が三姉妹なんですが、親戚が集まると、その三人が延々としゃべっているんです。でも、誰もお互いの話を聞いていないんですよね。高校時代もデザイン科で女性が多くて、微妙な喧嘩や空気感をたくさん見てきました。男性とはまったく違う関係性だな、と感じることは多いですね。
吉高:学生時代の女子の関係って、依存でもあるし、派閥で立ち位置が決まっていたりして、正直ちょっと気持ち悪さもある。 美しさを求めれば求めるほど、歪になっていくこともあるんだろうな、と思います。

――――今作では「主観の不確かさ」もテーマのひとつかと思います。“人の記憶って、こんなに歪むんだな”と感じた瞬間はありましたか?
吉高:しょっちゅう(笑)。「言った・言わない」もそうだし、「いつ出会ったか」も人によって全然違う。成人式で出会ったと思っていたら、実は21歳のときだった、なんてこともありますね。
蓬莱: 自分の中で都合よく改ざんされていることもあります。一度そう思い込むと、それが本当だと思ってしまう。でも、あとで答え合わせをすると全然違う、ということもある。
吉高:海外でホテルを取るとき、最後まで二つで迷って、結局二つ目にしたんですけど、一つ目への未練がすごく残っていて。気づいたら、その一つ目のホテルに行っていたことがありました(笑)。
蓬莱:それはもう、記憶というより願望の修正だね(笑)。

――今回の作品を書いていて、「これは自分の中の矛盾だな」と気づいた部分はありましたか?
蓬莱:それは、いつもあります。今まで百本以上書いてきましたけど、毎回「どうやって書いてきたんだろう」とわからなくなる。書こうとすると、いつもパニックになるんです。演劇をやりたいと思ってやっているのに、同時に怖いし、やりたくないとも思う。顔合わせの時期が一番つらくて、稽古場に行くのも正直、地獄です。このまま事故って入院とかになればいいのにな…とか思ったりすることも。
吉高:わかる!寝坊したときも、そういう気持ちになるかも。
蓬莱:そう。それも矛盾ですよね。結局、演劇って個人プレーではなく、チームプレー。本当の意味でのチームプレーは、性格的にあまり得意じゃないと思っています。だから、何をやっても趣味が続かない。唯一続いているのが演劇で、でもそれはもう趣味ではない。なぜ続けているのかは、今でも自分ではよくわからないんです。

――最後に、演劇だからこそ描ける、人間のリアルな部分について教えてください。
蓬莱:演劇は、その場で起こっている空気感を伝えられますよね。例えば飲み会でも、部屋に入って数秒で「盛り上がってないな」とわかることがありますよね。表面上は盛り上がっているけど、実はそうでもない、という空気。 人間は、そういう空気を察知する能力を持っている。演劇は、その空気感をそのまま届けられる。映像とは違って、ライブだからこそ伝わるものがあると思います。
吉高:同じ空間にいるからこそ、その世界に1時間半、2時間と連れて行かれる。迷い込んだ空間が、自分の人生の関係者になったような感覚になる瞬間がある。それがすごく面白い。期間や制限があるからこそ、人間にしかできないことが立ち上がる。ドラマや映画では出せない部分だと思います。
パルコ・プロデュース2025『シャイニングな女たち』
【作・演出】 蓬莱竜太
【出演】吉高由里子 さとうほなみ 桜井日奈子 小野寺ずる 羽瀬川なぎ 李そじん 名村辰 山口紗弥加
<Story>
金田海(吉高由里子)は、社会人として働く傍ら、他人のお別れの会に紛れ込み、ビュッフェを食べて帰るという行為を繰り返していた。ある日、入り込んだ会場で、金田は見覚えのある顔ぶれと再会する。それは、かつて自分がキャプテンを務めていた大学時代の女子フットサル部の仲間たちだった。親友の姿。 かつて敵視していた顧問の姿。そして、遺影に写るのは、同じピッチに立っていた後輩の姿。
——なぜ、私は呼ばれていないのか。
告別式の会場と、輝いていた大学時代の記憶が交錯していく。 あの輝きは、本当に“輝き”だったのか。
<スケジュール>
東京 PARCO劇場
〜2025年12月28日(日) ※上演中
大阪 森ノ宮ピロティホール
2026年1月9日(金) 〜2026年1月13日(火)
福岡 福岡市民ホール 中ホール
2026年1月16日(金) 〜2026年1月18日(日)
長野 サントミューゼ(上田市交流文化芸術センター) 大ホール
2026年1月24日(土) 〜2026年1月25日(日)
愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
2026年1月29日(木) 〜2026年1月30日(金)
吉高由里子(よしたか・ゆりこ)
1988年生まれ、東京都出身。映画・ドラマを中心に幅広い役柄を演じ、柔らかさと芯の強さを併せ持つ表現力で支持を集める。本作は大河ドラマ『光る君へ』終了後、初の舞台出演となる。
蓬莱竜太(ほうらい・りゅうた)
1976年生まれ、兵庫県出身。劇団モダンスイマーズ主宰。日常に潜む人間の矛盾や葛藤を鋭く捉え、ユーモアとリアリティを併せ持つ作風で高い評価を得る。舞台のみならず映像作品の脚本も多数手がける。
撮影/女鹿成二 ヘアメイク/中野明海(吉高さん) スタイリスト/申谷弘美(吉高さん)
(吉高さん衣装クレジット)
ドレス¥336,600/Max Mara(マックスマーラ ジャパン 0120-030-535) 、パンプス¥166,100/sergio rossi(セルジオ ロッシ ジャパン カスタマーサービス 0570-016600)、イヤリング¥803,000、リング¥759,000/ともにPOMELLATO(ポメラート クライアントサービス 0120-926-035)