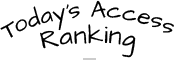日本では考えなかった社会、アジア人としてではなく私を確立させる!
2019年の年末、私はN.Y.で遊び狂っていた。年明けに人類を震撼させるウイルスが世界に蔓延することなんて信じられないほどに。N.Y.の年末は本当にお祭り騒ぎだ。11月に入ってからクリスマスまで、みんなまともに働いていないように見えるほど、毎日パーティーやら、イベントやら目白押し。
その真逆で、テレビ局員時代の年末は毎年地獄絵図だった。年末年始の特番が目白押しで、作っても作っても、次の特番が待ち構えている。なるべく自分のところに特番の依頼が来ないことをいつも10月くらいから祈り続けていた。
ひどい時は、クリスマス前から、センター試験辺りまでまともに家に帰れなかった時もあった。今思えば、私にはそんな忍耐力が備わっていると思うと、今後も何でもやれそうな気がする。
◆N.Y.で受けた洗礼… 私がアジア人だから?

話を戻すと、とにかくN.Y.の年末は身体がパーティーのことしか考えていない。そんな在住歴1ヶ月くらいの私が、調子に乗って誘われるパーティーにどこもかしこも出向いていたら、ある時、リアルな洗礼を受けたことがあった。
その日は、「ちゃんとしたパーティーだからね」と誘われた方に釘を刺されていた。しかし、外は寒いし、雨が降っているし、ジャケットは羽織ったものの、足元を楽にしたくて、買ったばかりのオシャレな白いスニーカーを履いていた。日本ではフォーマルな場でも、“オシャレな人ってスーツにスニーカー履いてるよね”なんて思いながら。
土砂降りの中、到着した建物を見た瞬間、本能的に嫌な予感がした。何だかかなり格式ばっていて、ブロンドヘア、ブルーアイの男性しか目に入って来ない。何やら歴史ある会員制のサロン? クラブ? のようで、空気が怖いとすら感じた。私の直感はしっかり当たっていた。

入り口で強面のドアマンに入館を止められた。「スニーカーではこの中には入れません」
同行していた方が「そこをなんとか!」と英語で交渉しようとしてくれたが、一切聞く耳を持たない。「近くにデパートがあるから、そこでヒールを買って来なさい」と一点張り。
日本でドレスコードを意識したことがなかった自分の経験不足を呪う。ドアマンは目さえ合わせてくれなかった。「これだから…」と言われているようにすら感じた。なんだかショックすぎて、もし私が生粋のアメリカ人だったら、こっそり見逃してくれたのではないかと嫌なことを考えてしまった。
土砂降りの中、格安のヒールがあることだけを祈ってデパートへ向かう。綺麗に巻いた髪もボサボサになり、白いスニーカーも泥だらけ。これからパーティーに行く人とは思えない形相だったと思う。
ヒールを履いたびしょ濡れの私を、ドアマンはようやく受け入れてくれた。「Nice shoes!」なんて適当に言っちゃってさ。
◆移民を痛感、だからこそ私という存在を確立させてやる!

これは私がTPOに合わせて行動出来なかったことが敗因だが、N.Y.にいると色んな局面で、「あれ?」という違和感を感じることがある。
「あんなに席が空いているのに、何で私はこんな入り口の、柱に隠れるような席にしか案内されないのか?」
「ちょっと英語の発音が悪いだけで、なぜ『あ~あ』みたいな呆れた顔を明らかにされるのか?」
「マンションではドアマンによって、明らかに西洋人のルックスのひとには丁寧なのに、私には笑顔を絶対見せない人がいるのか?」
日本でこの「ん?」という気持ちはもちろん味わったことがない。私という人間じゃなくて、見るからにアジア人である私を何か違う目線で見ているような、不思議な空気。これを感じる度に、「私は移民だ。この国で私は外国人だ」と痛感する。
トランプ大統領は明らかに移民に手厳しい。ビザだって、オバマ大統領の時より格段に取得が難しくなっている。
日本で堂々と、偉そうに、日本人として生きて来た私にとっては、拳を強く握り締めたくなる体験の連続。ただ、これを経験して初めて、グローバルに、インターナショナルに生きる力と術を私も何とか獲得してやろうと、自分に火が付くのだ。
このアメリカ人社会の中で、自分という存在を絶対に確立してやろうと。これだけは住んでみないと気づけない。海外旅行では火が付かない。
◆これまでの連載はこちら

古瀬麻衣子
1984年生まれ。一橋大学卒。テレビ朝日に12年勤務。「帰れま10」などバラエティ番組プロデューサーとして奮闘。2020年、35歳で米国拠点のweb会社「Info Fresh Inc」代表取締役社長に就任。現在NY在住。日本人女性のキャリアアップをサポートする活動も独自に行なっている。
Instagram:@maiko_ok_
HP