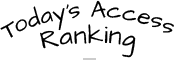都内で一人暮らしをしている、恋に臆病なイズミ。そんな彼女をいつも見つめているユキ。ひとつ屋根の下に暮らしながら言葉を交わすことはないが、イズミへの思いは誰よりも強い。もどかしい関係の「ふたり」の間に、新たな男性の存在が。果たしてイズミの凍った心を溶かす恋は始まるのか。そしてユキの正体とは…。
アナタダケニ──ユキ
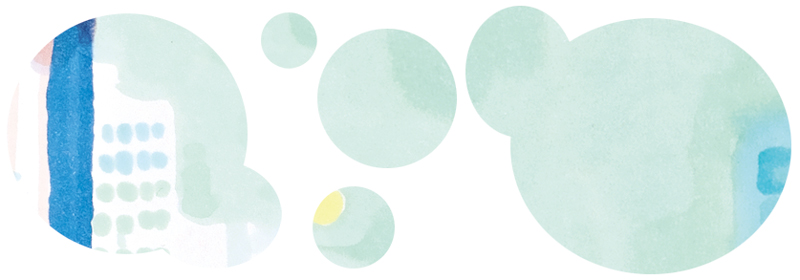
昼間は人通りの少ない住宅街の細い路地。その行き止まりに建つアパートの二階の出窓から、ボクは今日もひとりぼっちで外を眺めていた。真冬の空は朝からずっと淡い灰色に濁っていて、夕暮れどきのいまも風景は単調なモノクロームだ。地に沿って肩を寄せ合う一軒家の屋根たちも、かさかさに乾いて色彩を失い、どこか退屈そうに見える。そんななか、路地に面したブロック塀の上を、一匹の黒猫がこちらに向かって歩いてきた。ピンと立てた長い尻尾。悠々として、迷いのない足取り。この辺りを縄張りにしている毛並みの美しい黒猫だ。
ふいに、その黒猫が立ち止まった。黒猫は空の匂いでも嗅ぐように、すっと視線を上げ、そして、しばらくの間、灰色の冬空を見上げていた。
空に、何かあるの?
気になってボクも出窓のガラス越しに空を見上げてみた。でも、空はやっぱり何の変哲もないモノクロの広がりで、とくに何も見えやしなかった。ただの寒々しい灰色の広がりじゃないか。ボクがそう思ったとき、黒猫がおもむろに視線を下ろして、こちらを見た。
なぁに?
ボクも見詰め返す。黒猫のよく光る黄色い目は、ボクに「何か」を伝えようとしていた。そして、次の刹那──。
ボクは心のなかで「あっ」と声を上げた。黒猫の言わんとしていたことが分かったのだ。
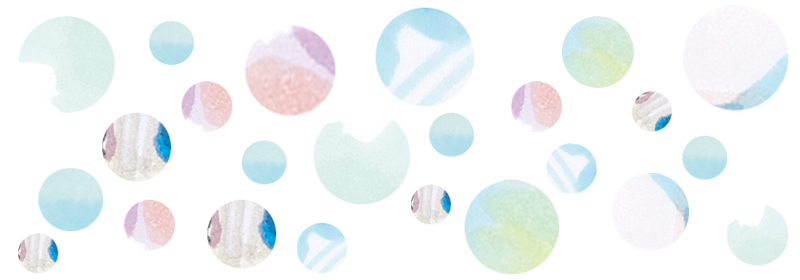
ひらり。
ひらり。
冬空から白い綿のようなモノが落ちてきた。牡丹雪。塀の上の黒猫は、まだ、じっとこちらを見ていた。うん。気づいたよ。雪だね──。灰色の空で生まれた純白。雪のかけらはみるみるその数を増やしていき、乾いたアスファルトに落ちて、てんてんと黒いシミを作っていく。
雪は白いのに、アスファルトと触れ合うことで正反対の黒を生み出す。ボクはガラス越しに何度も空を見上げ、そして地面を見下ろした。やがて、ひとひらの純白が、黒猫の背中にそっと舞い降りた。そのひとひらは、純白のまま在り続けた。しかし、黒猫はボクから視線を外すと、ぶるると身体を揺すって、背中の雪を落としてしまった。そして、艶めくしなやかな身体をひるがえし、塀の向こう側へと消えてしまった。
ボクは、また、ひとりぼっちになった。朝から代わり映えしない風景のなかで、雪だけが音もなく動いている。弱い風に揺られながら、ひたすら、上から、下へ。そして、白から黒へ。しばらくすると、アスファルトは黒一色で塗りつぶされていた。牡丹雪のひとひらはいっそう大きくなり、どこか不自然なくらいにゆっくりと空から落ちてくる。するとなぜだろう、時間までもがゆっくり流れはじめた気がした。
ボクは、彼女を想う。
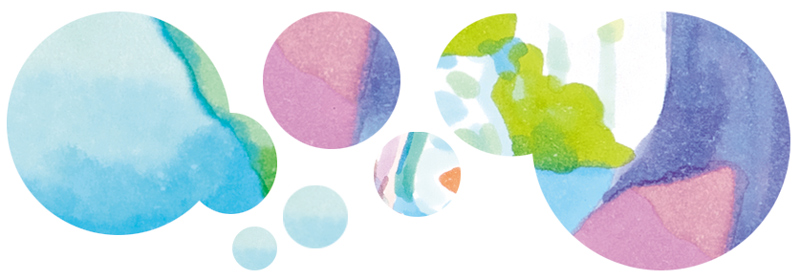
イズミ。
彼女は傘を持っているだろうか? 今朝、ボクが、この出窓からイズミを見送ったとき、空はまだ薄ぼけたような水色をしていた。そしてイズミはその空とよく似た色のコートを着て職場へと向かったのだ。夕方から雪が降るなんて、思いもしなかったのではないか? なんとなく、そんな気がする。イズミに触れた雪は、何色に変わるのだろう? 赤だったらいいな、とボクは思う。
奇跡でもなければ有り得ないけれど。さっきまで黒で埋め尽くされていたアスファルトが、いつの間にか白で覆われていた。
うっすらと雪が積もったのだ。こつこつと降り続けた白の勝利。家々の屋根も、黒猫のお気に入りの散歩道であるブロック塀の上も、白一色で統一されている。
それは、ボクが生まれてはじめて目にする積雪だった。
『ぷくぷく』森沢 明夫(著/文)

▲発行:小学館、¥1,600(税抜)
購入はこちらから
森沢明夫
1969年千葉県生まれ。早稲田大学人間科学部卒業。青森を舞台とした『津軽百年食堂』(2011年映画化)、『青森ドロップキッカーズ』、そして『ライアの祈り』(2015年映画化)は、青森三部作として話題に。また、高倉健主演映画の小説版『あなたへ』、吉永小百合主演の映画『虹の岬の喫茶店』原作など、多くの作品が映像化に関わっている。