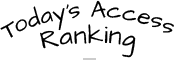アーティスト イ・ランさんインタビュー

《Profile》い・らん/1986年、ソウル生まれ。2006年、韓国芸術総合学校映画学科入学。ミュージシャン、作家、エッセイスト、イラストレーター、映像作家として活動。アルバム『神様ごっこ』(2016)で韓国大衆音楽賞・最優秀フォークソング賞を受賞し、授賞式でトロフィーを競売にかけたスピーチが話題に。続く『オオカミが現れた』(2021)は韓国大衆音楽賞で「今年のアルバム」など主要賞を受賞。社会問題に声を上げながら、音楽と文筆で心の内を描き続ける。日本での公演も多数。邦訳エッセイ『悲しくてかっこいい人』『話し足りなかった日』でも共感を呼んだ。
立つことさえ怖かった、あの日のデモのステージ。震えながら歌ったその声が次のだれかの勇気に
20代には、もう絶対に戻りたくありません。当時の韓国で20代を生きるのは、なかなかの地獄でした。仕事をしていても、話していても、歩いているだけでも、見た目で判断される。〝人〟ではなく〝性的な対象〟として扱われている気がして、息が詰まりそうで。社会が男性からの目線の基準に合わせて構築されていたので、化粧も、髪型も、服装も「女性ならこうあるべき」という基準があり、少しでも外れると価値がないとみなされる。私の場合はただ自分の意見を言っただけで、「女性なのにうるさい」とよく言われていましたね。
その生きづらさがどこから来たのかもわからず、問題について話して解消することもできず。30代になって、やっと楽になりました。顔や体ではなく、何をしているか、私の作品や仕事を少しずつ見てもらえるようになったからです。若い女性の修行を終えた―― そんな気分でした。
音楽活動は私の軸のひとつですが、最初から歌をつくろうと思ったわけではありません。苦しいとかつらいといった感情をどこにも置けなかったから、自分に向かって話すように小さな声でつぶやいていました。だれもいない部屋で、猫だけが聞いてくれていたそのひとり言を録音してみたら、思いがけず歌になっていったんです。歌に限らず、私は10代からものづくりをして発信してきて、今もやっていることは同じです。ただ、その声を社会に投げかけて、お金になって返ってきたとき、「あ、これが自分の職業になったんだ」と思いました。

記憶に強く残っているのは、「舞台の上では、目を醒ましていなさい」という言葉です。感情のままに表現していた私にとって、衝撃でした。つくることは自由でも、見せるときは相手がどう受け取るかを徹底的に考えなければならない。作品の中の感情をきちんと届けるには、計画が必要なんだと知ったんです。つくる自分と見せる自分。その切り替えを意識するようになってから、ステージに立つ準備の仕方が変わりました。
私はシンガーソングライターであると同時に、演出家でもあります。映画制作を学んだ経験があるので、観る人が「ここは本当に存在する世界だ」と信じられるように、声やトーン、衣装、照明、舞台、セットリスト、MC―― そのすべてをスタッフさんの力も借りて組み立てます。けれど、生の反応は毎回違う。前日笑った場面で、今日はだれも笑わないことも珍しくない。だから現場に立って人の呼吸を読み、公演のたびに少しずつ形を変えながら、伝わるまで探っていく。そのたびに思うんです。人間って難しくて、でもとてもシンプルだなと。
一方で、私は韓国では珍しい、社会に問いを投げかけるタイプのアーティストでもあります。だから、権力のある大きな会社や放送局からは、ブラックリスト扱いで敬遠されることも。でも、社会の隅で居場所をなくした人たちが、いつも私を呼び、支えてくれています。そのひとつが、2016年に起きた「江南駅通り魔殺人事件」でした。20代の女性が、「女性だから」という理由だけで見知らぬ男性に命を奪われた事件です。私はその追悼デモで歌いました。最初はだれもが怖がっていて、出演を断る人も多かった。脅迫が届き、私も同じように怯えていました。ですが、私が大勢の人の前で歌う姿を見て、「自分も立とう」と声を上げるアーティストが、少しずつ増えていったんです。
私自身、性暴力の被害者でもあります。外に出られず、家から駅まで歩くのも怖くて、友人に送り迎えを頼んでいた時期がありました。ただ、ある日ふと「どうせ死ぬのは一度だけ。だったら、言いたいことを言って死のう」と思ったんです。あの瞬間から、私は声を出すようになりました。デモや運動の一環でステージに立つときは、こう伝えます。「私はイ・ランです。見てください。私も勇気を出します。あなたたちも勇気を出して助けてください」と。それは、命を守るための〝取引〟のようなもの。顔を出して声を上げておけば、もしどこかで危険に遭っても、だれかが私に気づいてくれるかもしれない。そんな願いを込めて、マイクの前に立っています。
日本でのライブには、子供から60、70代までの多様なお客さんが来てくださいますが、韓国では若い女性、そしてLGBTの人や障害のある人といったマイノリティの方が多いです。特にLGBTの人々は、韓国の歴史や宗教の影響もあって、家族からも排除され、若いうちから苦しんでいて。みんなで泣いたり、笑ったり、抱き合ったりして、「生きてていい」と確かめ合う。祈りの場に近いかもしれません。お客さんや読者が私の表現をきっかけに、「自分の話をしてみたくなった」と言ってくれることがあります。そういう瞬間に立ち会えるときが、いちばんうれしいですね。声を上げることは、自分を守ることでもありますから。

幼少期からの家族関係や、さまざまに悩んできた体験を綴った新刊『声を出して、呼びかけて、話せばいいの』も、その延長にあります。私は長い間、「死にたい」と思いながら生きてきました。寝る前になると、精神と体が乖離して、すべてが遠くに感じられる時間があります。それでも、書くことで現実に戻ることができる。皆さんの中にも、この世界から消えたいと思う人がいるかもしれません。けれど、幸せだから生きるのではなく、生きているから感じられることがある。あなたの体で生きている存在は、あなただけです。ひとつしかないその体で、この不思議ばかりの世界を生きてみてほしい。そう伝えたいと思っています。
私自身は長年ずっと脳優位の生活でした。不眠症で、インスタントラーメンばかり食べて、タバコもたくさん吸って。気づいたらストレスで体がごちゃごちゃになっていて、「さて、これからどうしよう」と(笑)。39歳の今、少しずつ整えているところです。2年前に珍しい目の病気が見つかり、そこからは〝口で書く〟ようになりました。散歩をしながら、スマートフォンに話しかけるとAIが文字にしてくれる。パソコンに向かわなくても原稿が書けますし、息の長さや間が漂うので、文章にも声のリズムが生かせる気がしています。疲れたときのリフレッシュ方法は、お風呂にゆっくり浸かること。湯気の中で観るドラマも楽しみのひとつで、日本の作品では特に坂元裕二さんの脚本が好きですね。
この先の望みは、ただ「長生きしたい」ということです。これから何が起こって、自分がどう感じるかいろいろと体験したい。体の痛みも、視力の不安も全部含めて、今の自分。これからも、この世界を感じながら、生きていきたいです。
痛みの奥に、光を見つける。新刊エッセイ『声を出して、呼びかけて、話せばいいの』

突然の姉の死をきっかけに、母や祖母との関係、受け継がれてきた痛みや愛を見つめ直したエッセイ集。家族という小さな社会の中で繰り返される抑圧と赦しを、冷静に、深い情をもって描く。韓国社会の背景、日常の会話、舞台作品の言葉、18年寄り添った愛猫との別れ── 生の断片を渾身で綴りながら、〝生き続ける力〟を確かに灯してくれる。¥1,980/河出書房新社
ワンピース¥27,500(ステュディオス ウィメンズ 表参道店〈ステュディオス〉) パンツ¥26,400(THÉ PR〈アディクシー〉) 靴¥39,600(銀座かねまつ6丁目本店〈銀座かねまつ〉) その他/本人私物
銀座かねまつ6丁目本店 03-3573-0077
THÉ PR 03-6803-8313
ステュディオス ウィメンズ 表参道店 03-6434-9288
2026年Oggi1月号「The Turning Point~私が『決断』したとき~」より
撮影/石田祥平 スタイリスト/角田かおる ヘア&メイク/後藤若菜(ROI) 通訳/チャ・ユンジョン 構成/佐藤久美子
再構成/Oggi.jp編集部
Oggi編集部
「Oggi」は1992年(平成4年)8月、「グローバルキャリアのライフスタイル・ファッション誌」として小学館より創刊。現在は、ファッション・美容からビジネス&ライフスタイルテーマまで、ワーキングウーマンの役に立つあらゆるトピックを扱う。ファッションのテイストはシンプルなアイテムをベースにした、仕事の場にふさわしい知性と品格のあるスタイルが提案が得意。WEBメディアでも、アラサー世代のキャリアアップや仕事での自己実現、おしゃれ、美容、知識、健康、結婚と幅広いテーマを取材し、「今日(=Oggi)」をよりおしゃれに美しく輝くための、リアルで質の高いコンテンツを発信中。
Oggi.jp